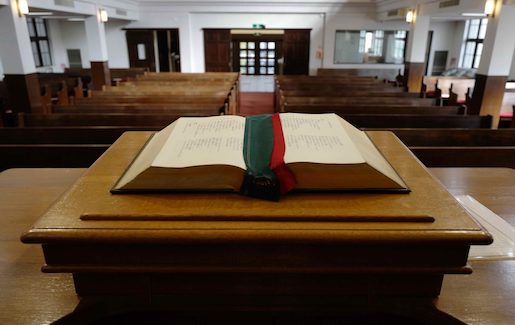説 教「わたしの霊を御手に」 副牧師 川嶋章弘
旧 約 詩編第31編1-9節
新 約 ルカによる福音書第23章44-49節
絶望の叫び
ルカによる福音書が語る主イエスの十字架の場面を読み進めてきて、本日の箇所では、いよいよ主イエスの十字架の死が語られます。主イエスは父なる神様に、「父よ、わたしの霊を御手にゆだねます」と言われて、十字架上で死なれました。そのようにして息を引き取られた主イエスのお姿は、マタイ福音書やマルコ福音書が語る主イエスのお姿とは随分と違いがあるようにも感じます。マタイ福音書やマルコ福音書で、主イエスは「わが神、わが神、なぜわたしをお見捨てになったのですか」と大声で叫ばれました。それは、神様から見捨てられたことへの絶望の叫びでした。神様の怒りと裁きを受け、神様から見捨てられ滅ぼされることへの絶望の叫びであったのです。しかしまさにそのように主イエスが神様から見捨てられる絶望を引き受けてくださったゆえに、本来、神様から見捨てられ、滅ぼされるしかなかった、罪人である私たちが救われました。私たちの代わりに、主イエスが私たちの罪をすべて引き受けて、神様から見捨てられて十字架で死んでくださったことによって私たちが救われたのです。「わが神、わが神、なぜわたしをお見捨てになったのですか」という主イエスの叫びは、そのことを告げています。主イエスが神様から見捨てられてくださったゆえに、私たちはもはや神様から見捨てられることがない。たとえどんな苦しみの中でも、私たちは神様から決して見捨てられることがない。その大きな慰めを告げているのです。
人間を回復する言葉
それに対して、「父よ、わたしの霊を御手にゆだねます」というお言葉は、絶望の叫びとは随分と違う、むしろ神様への信頼の言葉のように思えます。十字架上で死を迎えるまさにそのときも、主イエスが神様への信頼を貫かれた、それを言い表しているように思えるのです。私たちもこのような言葉を語りたい。苦しみの中でも、たとえ死を迎えるときも、主イエスのように神様への信頼に満ちた言葉を語りたいと思います。主イエスはこの言葉でこのときだけでなく、いつも祈っていたのかもしれません。この言葉は、共に読まれた旧約聖書詩編31編6節の言葉で、この31編を、ユダヤ人は夕べの祈りとして、一日の営みを終える時の祈りとして用いていたそうです。主イエスもしばしば詩編の言葉で祈られました。一日の営みを終えられると、31編を祈られて眠りに就かれたのかもしれません。毎晩、この言葉で祈っていたから、十字架上で死を迎えるそのときも、この言葉で祈ることができ、神様への信頼は揺らぐことがなかった。だから私たちもその主イエスを見習って、日々この言葉を祈りつつ歩み、たとえ死を迎えるときも神様への信頼を貫かなくてはならない、そういうことなのでしょうか。もしそうであるなら、私たちはそのように生きられない自分を突きつけられ、打ちのめされるだけです。確かに神様への信頼に満ちた言葉を語りたいと思います。しかしそう思いながら、神様に信頼することができない、神様に信頼して自分の霊を、自分の命と人生を、自分の存在全体を神様にゆだねることができない。それが私たちです。そうなると、この十字架上の主イエスのお言葉は立派な言葉ではあるけれど、私たちには真似できない言葉ということになります。私たちの救いや慰めとは関わりのない言葉ということになるのです。でも、本当にそうなのでしょうか。この言葉は、もっと違うことを示しているのではないか。この主イエスの十字架上のお言葉は、私たちを「本当の人間」に回復する言葉、その道を切り開くための言葉だと思います。いわば「人間を回復する言葉」なのです。このことは、この言葉だけを取り出しても見えてきません。前後の文脈の中で読むことによって見えてくるのです。
暗闇が全地を覆った
この箇所の冒頭44節から45節の前半で、このように言われています。「既に昼の十二時ごろであった。全地は暗くなり、それが三時まで続いた。太陽は光を失っていた」。原文を直訳すれば、「既に昼の十二時頃であった。太陽は光を失って、暗闇が三時まで全地の上に生じた」となります。太陽が光を失って暗闇が全地の上に生じたとは、何を指し示しているのでしょうか。日蝕が起こったとか、起こらなかったとか、そういう議論は、まったく的はずれな議論だと思います。ここでは天文学について語ろうとしているわけではないからです。アモス書8章9節にこのようにあります。「その日が来ると、と主なる神は言われる。わたしは真昼に太陽を沈ませ 白昼に大地を闇とする」。その日が来ると、つまり主の日が来ると、真昼に太陽が沈み、白昼に大地は闇に覆われる、と預言されています。そうであれば「太陽が光を失って暗闇が全地の上に生じた」とは、主の日の到来を指し示しているのです。「主の日」と聞くと、私たちはすぐに救いの日、救いの完成の日だと思ってしまいます。しかし「主の日」は、本来、神様が私たちをお裁きになる日です。主の日に私たちの罪がすべて明らかにされ、その私たちの罪を神様がお裁きになるのです。それゆえ同じくアモス書5章18節以下では、このように言われています。「災いだ、主の日を待ち望む者は。主の日はお前たちにとって何か。それは闇であって、光ではない……主の日は闇であって、光ではない。暗闇であって、輝きではない」。主の日は、私たち罪人にとって闇であって光ではありません。主イエスが十字架で死なれるまさにそのとき、主の日が到来し、私たち人間の罪の現実が露わにされました。それゆえ全地が暗闇に覆われたのです。人間の罪の現実という暗闇が全地を覆った、と言って良いかもしれません。いえ、普段は隠されている人間の罪の現実という暗闇が露わにされた、と言ったほうが良い。暗闇は突然生じたのではなく、隠されていたのです。その暗闇が、神様の独り子イエスを十字架に架けるという私たち人間の罪の極みにおいて、露わになり、世界を覆ったのです。
暗闇に覆われているように思える世界
この暗闇は、今も私たちの社会と世界を覆っているように思えます。私たちの目に映るのは、むしろ夜になってもまばゆい光に照らされている街々です。私たちの暮らす街は、人間の罪の現実という暗闇などどこにもないかのように、人工的な光で溢れています。しかしそれは、暗闇が隠されているだけに過ぎません。私たちが自分たちの罪の現実を直視しなくて良いように隠されているだけに過ぎないのです。私たちが一度(ひとたび)、この社会と世界の悲惨な現実に、私たちの苦しみの現実に目を向けるならば、それらの現実の根本にある、人間の罪の現実を見ないわけにはいかないのです。
私たちの罪の現実とは、主イエスを十字架に架けた私たち人間の罪の現実とは、私たちが自分の命と人生を神様にゆだねることができないということです。それどころかそれらは自分のものだと思っていることです。自分の思い通りにできると、自分の好き勝手にして良いと思っているのです。しかし自分の命や人生を自分のものだと思って生きるとき、私たちは神様との関係を失い、神様なしに自己中心的に生きます。自分さえ良ければ、自分の仲間さえ良ければ、自分の国さえ良ければ、そのような自己中心的な思いに駆られて生きるのです。今、私たちの社会や世界では、このような自己中心的な思いがますます肥大化しているように思えます。そのために国と国との関係が破壊され、人と人との関係が破壊され、あるいは自然との関係も破壊されているのです。私たちは自分の全存在を神様にゆだねることができず、自分の思い通りにしようとして、神様との関係を破壊し、隣人との関係を破壊しているのです。この私たち人間の罪の現実という暗闇が、この世界と社会を覆っているように思えるのです。
神殿の垂れ幕が真ん中から裂けた
45節の後半には、「神殿の垂れ幕が真ん中から裂けた」とあります。このことはマタイ福音書やマルコ福音書にも記されています。「神殿の垂れ幕」というのは、神殿の聖所と至聖所とを分ける垂れ幕のことです。至聖所は神様が住んでおられるところではありませんが、しかし神様が臨んでくださるところ、現臨してくださるところです。その意味で、神様と出会い、交わりを持つところと言えます。その至聖所に、年に一度、大祭司だけが入ることができました。とはいえ罪ある人間は、そのままでは神様のみ前に立つことができませんから、大祭司は自分自身と民の罪の贖いのために、犠牲の動物の血を携えて行く必要がありました。このように「神殿の垂れ幕」とは、私たちと神様を隔てるものでした。この垂れ幕を通らなければ、神様と出会い、交わりを持つことができないし、それが出来るのは、年に一度、大祭司だけであったのです。しかし主イエスの十字架の死によって、この神殿の垂れ幕が裂けた。それは、主イエスの十字架の死によって、私たちと神様を隔てるものが取り除かれた、ということです。しかも私たちは神様のみ前に進み出るのに、もはや犠牲の動物の血を携えていく必要はありません。主イエスが十字架で流された血によって、私たちの罪の完全な贖いを実現してくださったからです。私たちは手ぶらで神様のみ前に進み出て、神様と出会い、交わりを持って生きることができるようになったのです。しかしこのことは、マタイ福音書とマルコ福音書には当てはまっても、ルカ福音書には当てはまらないと思います。「神殿の垂れ幕が裂けた」という点では同じでも、マタイ福音書とマルコ福音書が主イエスの十字架の死の後に、このことを語っているのに対して、ルカ福音書は主イエスの十字架の死の前に語っているからです。十字架の死の前であれば、神殿の垂れ幕が裂けたことが、主イエスの十字架の死によって神様と私たちを隔てるものが取り除かれたことを見つめている、とは言えないと思うのです。
礼拝の喪失
それでは何を見つめているのでしょうか。44節、45節前半と結びつけて読むならば、人間の罪の現実によって、神殿が破壊されたことを見つめているのではないでしょうか。神殿というのは神様と出会う場所、つまり神様を礼拝する場所ですから、人間の罪の現実によって、神様を礼拝する場所が破壊され、神様を礼拝することが失われたことを見つめているのです。私たちは自分の命と人生を神様にゆだねようとせず、自分自身で握りしめて離さないことによって、神様なしに自己中心的に生きています。それは、神様との関係の破壊であり、要するに神様を礼拝して生きることの破壊であり、礼拝の喪失です。太陽が失われ、暗闇が全地を覆い、神殿の垂れ幕が裂けたことは、私たち人間の罪によって、私たちと神様との関係が破壊され、神様を礼拝して生きる道が完全に失われたことを見つめているのです。
父よ、わたしの霊を御手にゆだねます!
しかし主イエスは、そのように人間の罪の現実が全地を覆い、神様と人間との関係が破壊され、神様を礼拝して生きる道が完全に失われたかのように思える中で、なお私たち人間を見捨てることがありませんでした。私たちが自分の命と人生を神様にゆだねようとせず自分自身で握りしめて、神様なしに、神様を礼拝せずに生きるのであれば、その先には滅びしかありません。しかし主イエスは私たちが滅ぶのを「良し」とされませんでした。滅んで行くのを放って置かれませんでした。私たちが神様にゆだね、神様を礼拝して生きることができるために救い出そうと、回復させようとしてくださったのです。
「父よ、わたしの霊を御手にゆだねます」。それは、私たちを救い出し、回復させようとする主イエスの叫びです。人間の罪の現実という深い暗闇を切り裂く叫びなのです。私たちは主イエスがこの言葉を穏やかに語ったように思っているかもしれません。十字架上で神様に信頼して、穏やかに、平安の内に、このように祈られたと思っているのです。しかし「イエスは大声で叫ばれた」とあります。原文を直訳すれば、「イエスは大きな叫びで叫ばれた」となります。叫ぶのですからそもそも大きな声です。しかしさらに「大きな叫びで」という言葉が重ねられています。穏やかとは程遠い、激しい叫びです。英訳聖書を見ると、この主イエスのお言葉の最後に感嘆符(いわゆる「びっくりマーク」)が付されています。原文に感嘆符があるわけではありません。この言葉が主イエスの叫びだから、感嘆符を付けたのだと思います。「父よ、わたしの霊を御手にゆだねます!」。そう大声で、激しく叫ばれて、主イエスは十字架上で息を引き取られました。自分の命と人生を神様にゆだねることができず、神様との関係を破壊し、神様を礼拝して生きられなくなっている私たちを救うためです。神の独り子を十字架に架けるという人間の自己中心の罪が極まり、暗闇が全地を覆っている中で、誰もが自分の命と人生を神様にゆだねようとせず握りしめている中で、ただ主イエスお一人はご自分の霊を、ご自分の命を、ご自分の全存在を父なる神様の御手にゆだねられ、十字架で死なれたのです。「息を引き取られた」と言われていますが、これは日本語的な表現です。原文の言葉を直訳すれば、「息を吐き出した、命を、魂を吐き出した」となります。主イエスはまさにご自分の息をすべて吐き出すようにして、ご自分の命、全存在を注ぎ出すようにして、神様に完全にゆだねられたのです。そのことによって私たちが破壊した神様との関係を回復してくださいました。この叫びをもって、主イエスが十字架で死んでくださったことによって、私たちが神様にゆだねて生きる道が、神様を礼拝して生きる道が切り開かれたのです。神様に造られた者として、「本当の人間」として回復されて生きる道が切り開かれたのです。
礼拝の回復
それゆえ主イエスのこの叫びと十字架の死によって、世界はまったく変わりました。主イエスの叫びが全地を覆っていた暗闇を引き裂き、その十字架の死によって暗闇が取り除かれ、光がもたらされたのです。十字架の死の前と後で世界が変わったことが、この主イエスの十字架の出来事を見ていた百人隊長や群衆の姿から分かります。47節には、「百人隊長はこの出来事を見て、『本当に、この人は正しい人だった』と言って、神を賛美した」とあります。百人隊長はローマの兵隊の隊長であり、主イエスの十字架刑の責任者でした。その彼が主イエスの十字架の出来事を見てこのように言ったのは、自分が無実の人を死刑に処してしまったことへの恐れや反省からではありません。この百人隊長は「神を賛美した」と言われています。恐れや反省から神様への賛美は生まれません。神殿の垂れ幕が真ん中から裂けたことが神殿の破壊、礼拝の喪失を意味しているならば、この百人隊長が神様を賛美したことは、礼拝の回復を意味しているのです。しかも単に失われたものがもとに戻ったというだけではありません。神殿の礼拝にはユダヤ人だけしか参加できませんでした。しかしここでは異邦人である百人隊長が神様を賛美し、礼拝しているのです。主イエスが「父よ、わたしの霊を御手にゆだねます!」と叫ばれ、十字架で死なれることによって、神様を礼拝して生きる道がユダヤ人だけでなく、すべての人に開かれたのです。神様と共に生き、神様を礼拝して生きるのが「本当の人間」の姿、人間のあるべき姿です。神様は人間を、神様と共に生きる者として、神様を礼拝して生きる者としてお造りくださったからです。その「本当の人間」として回復されて生きる道が、すべての人に開かれたのです。
神を賛美する者へと変えられる
48節には群衆の姿がこのように語られています。「見物に集まっていた群衆も皆、これらの出来事を見て、胸を打ちながら帰って行った」。主イエスの十字架を見物していた群衆とは、数日前まで夢中になって主イエスを支持し、しかし自分たちの期待が外れると、主イエスを「十字架につけろ」と叫び、その十字架を見物するために、刑場に引いて行かれる主イエスについて行った民衆のことです。「胸を打つ」というのは、悔い改めの仕草ですから、民衆たちも、「父よ、わたしの霊を御手にゆだねます!」と叫ばれて、十字架で死なれた主イエスを目の当たりにすることを通して、悔い改めに導かれたのです。「帰って行った」と訳されている言葉は、ルカ福音書とその続きである使徒言行録に特徴的な言葉です。しばしば単に「帰って行く」というより、神様を賛美しながら帰って行く、という文脈で用いられます。ここでも民衆は悔い改めへと導かれ、神様を賛美しながら、それぞれの生活の場へと帰って行ったのではないでしょうか。それは神様を賛美し、神様を礼拝して生きる者へと変えられた、ということです。もちろん民衆は、百人隊長のように「本当に、この人は正しい人だった」と信仰を告白したわけではありません。ですから民衆が悔い改めて、神様を賛美し、神様を礼拝して生きる者となった、というのは言い過ぎかもしれません。しかしその芽生えが起こっている。神様を賛美し、神様を礼拝して生きる者へと変えられ始めているのです。主イエスの十字架によってもたらされた、暗闇ではなく光に覆われている世界に、人間の罪ではなく神の恵みに覆われている世界に入れられて生き始めているのです。私たちもこの世界に入れられています。神様と共に、神様を礼拝して生きることができる世界に私たちも入れられているのです。そしてこの神様を礼拝して生きる世界に、すべての人が招かれています。49節で「イエスを知っていたすべての人たちと、ガリラヤから従って来た婦人たちとは遠くに立って、これらのことを見ていた」と言われていますが、同じように今はまだ「遠くに立って」、主イエスの十字架を見つめている人たちが、主イエスの十字架のもとに集い、神様を賛美して生きるよう招かれているのです。
十字架のもとに集う
礼拝とは、主イエスの十字架のもとに集い、その十字架による神様の赦しの恵みにあずかり、神様を賛美することにほかなりません。もちろん私たちは主イエスの復活なしに、神様を礼拝することはできません。十字架のもとに集うというのは、主イエスが十字架に架けられっぱなしということでは決してありません。私たちは十字架で死なれ、復活され、今も生きて働かれる主イエスのもとに集い、罪の赦しにあずかり、神様の愛と恵みを豊かに受けて、それに感謝して神様を賛美するのです。このように私たちが神様を賛美し、神様を礼拝して生きられるようになるために、主イエスは十字架で死んでくださったのです。
神の御手の中にある
確かに私たちの社会と世界は暗闇に覆われているように思えます。人間の罪が溢れているように思えます。しかしそれでも、主イエスが十字架で死なれる前に、全地を覆った暗闇と私たちの世界を覆っているように思える暗闇は同じではありません。私たちの世界を覆っている暗闇は、すでに「父よ、わたしの霊を御手にゆだねます!」という主イエスの叫びによって引き裂かれているからです。主イエスの十字架によって、すでに暗闇に勝利し、光がもたらされているのです。この世界の悲惨な現実も、私たちの苦しみや悲しみの現実も決して侮ることはできません。しかしそれでも、主イエスの十字架の死によって、私たちは神様と共に、神様を礼拝して生きる者とされています。なお暗闇に覆われているように思える世界にあって、神様と共に生き、神様を礼拝して生きていく中でこそ、私たちは自分の命と人生を、自分の全存在を神様にゆだねて生きるよう変えられていくのです。詩編31編9節までを読みましたが、その少し先の16節に、聖書協会共同訳では、「私の時は御手にあります」というみ言葉が記されています。私たちは死を迎えるときにだけ、あるいは夕べの祈りのときにだけ、自分を神様にゆだねるのではありません。今日も明日も明後日も、死を迎えるときも、そして死んでからも、「私の時は御手にある」と信じ、自分の命と人生のすべてが神様の御手の中にあると信じ、神様にすべてをゆだねて生きていくのです。自分だけではありません。私たちは自分の愛する人、大切な人の命と人生も神様の御手の中にあると信じ、神様にゆだねることができます。「私の時」も、「愛する人の時」も、神様の御手の中にある。私たちがそのことを信じ、神様を礼拝し、自分の全存在を神様にゆだねて生きる道を、主イエスは切り開いてくださった。「父よ、わたしの霊を御手にゆだねます!」と十字架上で叫ばれ、死なれることによって、切り開いてくださったのです。