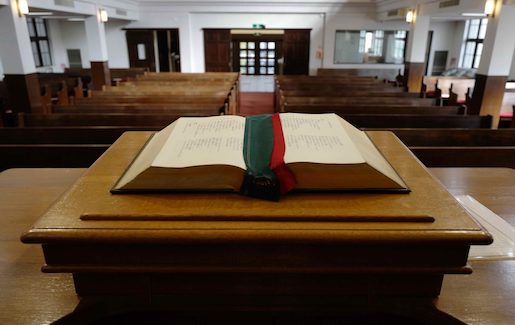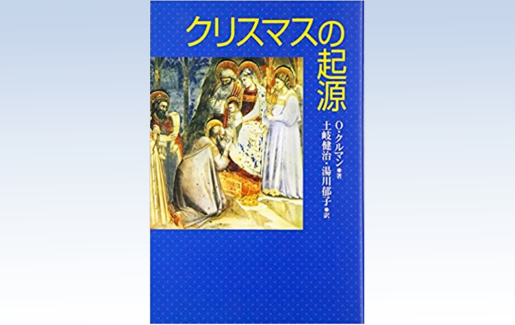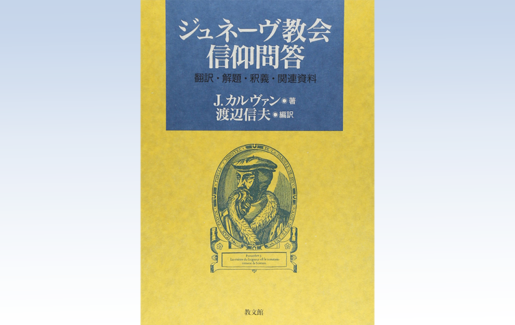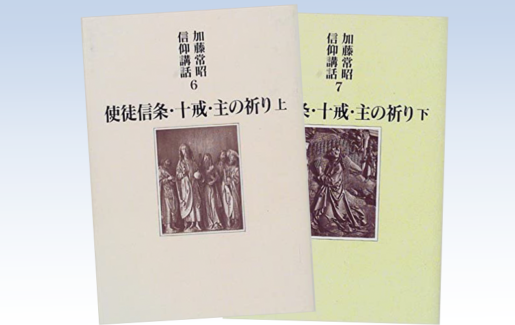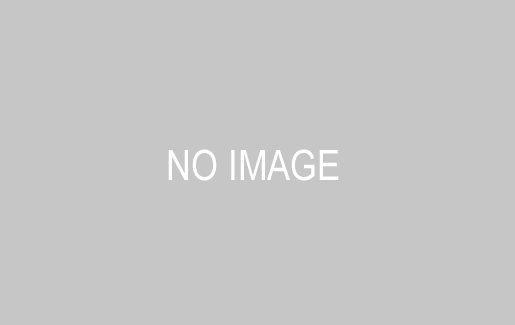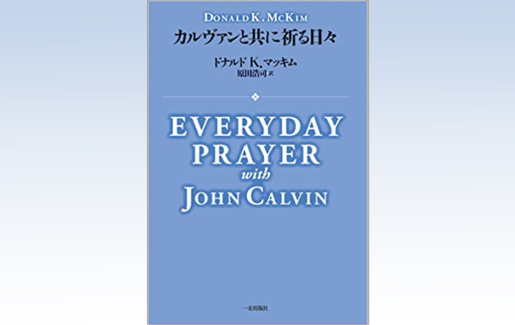2025年4月の聖句についての奨励(4月2日 昼の聖書研究祈祷会) 牧師 藤掛順一
「神はこのイエスを死の苦しみから解放して、復活させられました。」(24節)
使徒言行録第2章22-28節(聖書協会共同訳)
主イエスの十字架の死と復活を覚えつつ
主イエス・キリストの十字架の苦しみと死とを覚えるレント(受難節)を歩みつつ、新しい年度を迎えました。4月13日からが受難週、そして4月20日にはイースター(復活祭)を迎えます。そのことを覚えて、4月の聖句を選びました。今年に入ってからは月間聖句を「聖書協会共同訳」から選んでいますが、この4月の聖句は、新共同訳においても聖書協会共同訳においても全く同じです。22〜28節全体を比較すればいろいろ違いがあるので、紹介の意味で聖書協会共同訳をお読みしましたが、今回は翻訳の比較をしようというのではなくて、主イエスの苦しみと死、そして復活を語るこの24節のみ言葉を味わいたいのです。
使徒言行録第2章のこの箇所は、ペンテコステの日に、聖霊を受けた弟子たちを代表してペトロが立ち上がり、人々に語った説教です。聖霊を受けて弟子たちは、主イエスによって実現した救いを宣べ伝えていったのです。中でもこの24節には、主イエスの十字架の苦しみと死そして復活のことが語られています。まさに今私たちが覚えつつ歩んでいることが凝縮されて語られているのです。
あなたがたがイエスを殺した
24節には、主イエスが「死の苦しみ」に捕えられていたことが見つめられています。そのことがどのようにして起ったかを、ペトロは23節でこう語っています。「このイエスを神は、お定めになった計画により、あらかじめご存じのうえで、あなたがたに引き渡されたのですが、あなたがたは律法を知らない者たちの手によって、はりつけにして殺したのです」。ここに、主イエスの十字架の死において起ったことは何だったのかがはっきりと語られています。「あなたがた」と呼びかけられているのは、22節から分かるように「イスラエルの人たち」です。神に選ばれて神の民として歩んでいたはずのイスラエルの人々が、「神から遣わされた方」(22節)である主イエスを「はりつけにして殺した」のです。主イエスに十字架の死刑の判決を下し、それを執行したのは、イスラエルの人々ではなくてローマ帝国の総督ポンティオ・ピラトでしたが、しかしペトロは、これは全て「あなたがた」つまりイスラエルの人々がしたことだと語っています。「あなたがたは律法を知らない者たちの手によって」というのはそういうことです。あなたがたイスラエルの人々が、律法を知らない者たちつまり異邦人であるピラトらの手によって、主イエスを十字架につけて殺したのです。それはあなたがたの仕業であり、あなたがたの責任だ、とペトロは言っているのです。
神のお定めになった計画
しかしペトロはそれと同時に、このことは全て、神のご計画によることだった、と語っています。「このイエスを神は、お定めになった計画により、あらかじめご存じのうえで、あなたがたに引き渡されたのですが」というのはそういうことです。イスラエルの人々が主イエスを十字架につけて殺す、ということが起ったのは、神がイエスを彼らに「引き渡した」ことによるのです。それは神の「お定めになった計画」によることであり、神は「あらかじめご存じのうえで」、つまりイスラエルの人々が主イエスを十字架につけて殺すことを分かったうえで、主イエスを彼らに引き渡したのです。つまりこの23節には二つのことが語られています。第一は、主イエスの十字架の死は「あなたがた」イスラエルの人々のしたことであり、彼らの罪だということ。第二は、しかしそのことは神のご計画によって、つまり神のみ心によって起ったのだ、ということです。この二つのことが、主イエスの十字架の死において起ったのです。
自分が主イエスを殺した、ということこそが主イエスと私たちを結びつける
第一のことをさらに掘り下げて見つめたいと思います。イスラエルの人々は神によって引き渡された主イエスを、自分たちの思いによって「はりつけにして殺した」のです。だから「あなたがたこそ、イエスを殺した張本人だ」とペトロは言っています。たとえそれが神のご計画、つまり神のみ心によって起ったとしても、だから自分たちに責任はない、罪はないと言うことはできないのです。しかしペトロはそう語ることによって、主イエスを十字架につけて殺したイスラエルの人々つまりユダヤ人への憎しみを煽ろうとしているのではありません。「イスラエルの人たち」とは、神によって選ばれ、召されて神の民として歩んでいる人々です。それは今は私たちのことです。「あなたがたは」というペトロの言葉を私たちは、誰か他の人々ではなくて、自分自身に向けて語られている言葉として読まなければならないのです。「神から遣わされた方」である主イエスをはりつけにして殺したのは私たちなのです。その罪は私たちにあるのです。「いやそんなことをした覚えはない」と思うかもしれません。しかし、主イエスの十字架の死による罪の赦しにあずかるには、このことを受け入れなければなりません。主イエスが、この自分の罪を背負って、十字架にかかって死んで下さったからこそ、罪の赦しが与えられたのです。つまり主イエスはこの私の罪のために死んだのです。「私たちが主イエスをはりつけにして殺した」というのはそういうことです。そしてこのことこそが、主イエスの十字架の死と私たちとを結びつけるのです。そうでなければ、およそ二千年前の主イエスの十字架の死は、私たちとは何も関係のない出来事となります。「私たちが主イエスを十字架につけて殺した」ということを受け入れることによってこそ、主イエスと私たちとの間に繋がりが生まれるのです。そしてそこであの第二のことが生きてきます。私たちの罪によって起った主イエスの十字架の苦しみと死は、すべて神のみ心、神のご計画によることだった、ということです。そこに、主イエスの十字架の死によって神が私たちの罪を赦して下さった、という神の救いのみ業が明らかになるのです。ペトロがここでイスラエルの人々に「あなたがたがイエスをはりつけにして殺した」と言っているのも、そのことを認めることによってこそあなたがたに神のみ心による救いが与えられるのだ、ということを語るためだったのです。
主イエスの復活は神のみ業
さて24節に戻りますが、そこには、主イエスはこのようにして死の苦しみに捕えられたけれども、「神はこのイエスを死の苦しみから解放して、復活させられました」と語られています。主イエスの復活が見つめられているわけですが、それは「神が主イエスを死の苦しみから解放して復活させた」という出来事だったのです。主イエスの復活は、勿論自然現象ではないし、主イエスがご自分の力によって死者の中から復活したのでもありません。父なる神が、死に支配されていた主イエスをそこから解放して復活させたのです。つまり父なる神の「お定めになった計画」は、主イエスの十字架の死だけでなく、その復活にも及んでいたのであり、神がそのみ心によって主イエスを十字架の死へと引き渡し、そしてその苦しみから解放したのです。
主イエスは私たちの死の苦しみを味わって下さった
ここで改めてよく味わうべきなのは、主イエスが「死の苦しみ」を体験したということです。私たちは時として、主イエスの十字架の死の苦しみを軽く考えてしまうことがあるのではないでしょうか。主イエスはご自分が神の子であり、父なる神から遣わされて人間となってこの世に来たことを知っておられました。そして人々の手に引き渡され、十字架につけられて殺されることを知っておられました。そして三日目に復活することをも予告しておられました。それらのことが全て分っていたなら、主イエスにとって、十字架の死はそんなに深い苦しみではなかったのではないか、この苦しみの先には復活があることが分かっていたのだから…、と感じてしまうのです。しかしそれは、主イエスが何のために「死の苦しみ」を負って下さったのかをわきまえない、浅はかな考えです。主イエスが「死の苦しみ」を体験して下さったのは、私たちのためなのです。このことによってこそ、およそ二千年前の主イエスの十字架の死は私たちと関係のある出来事となるのです。「主イエスにとって十字架の死はどの程度の苦しみだったのか」と第三者として考えているうちは、私たちにとって主イエスの死は自分とは関係のない他人事です。しかし主イエスは、私たち自身の死の苦しみを味わって下さったのです。私たちは、三日目の復活を約束されている神の子ではありません。私たちの死の苦しみは、その先に復活があることがあらかじめ分かっているものではないし、また死んだら天国に行って先に亡くなった人たちと楽しく暮らせる、などという根拠のない慰めを語れるようなものでもありません。生まれつきの私たちにとって死は、神に背いている罪人としての死であり、神が与えて下さった命を失い、神の恵みから引き離されてしまうことです。つまり死は深い苦しみであり絶望なのです。この私たちの死の苦しみを、まことの神であり、神の独り子である主イエスが味わい、体験して下さったのです。そのことを覚える時にこそ、主イエスの十字架の死は私たちと関係のある出来事となるのです。それは、主イエスをはりつけにして殺したのはこの自分だ、ということを認めることによってこそ、主イエスと私たちとの関係が生まれ、そこに神による赦しが与えられるということと繋がります。主イエスは私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださることによって、私たちが直面している「死の苦しみ」をご自身が味わい、その死の苦しみから解放されることによって、死の苦しみの中にいる私たちを解放する救い主となって下さったのです。
主イエスの復活による希望
その「解放」は、父なる神が主イエスを復活させて下さったことによって与えられました。この復活は、主イエスご自身の力によるのではなく、父なる神のみ業でした。そのことによって、主イエスの復活もまた、私たちと関係のある出来事となったのです。もしも主イエスが自分の力で復活したのなら、それは私たちとは何の関係もないことになります。私たちにはそんな力はないのですから、「へえ、すごいですね」と言うしかありません。しかし私たちが直面している「死の苦しみ」を背負い、味わって下さった主イエスを、父なる神が復活させて下さったのなら、そこには私たちにとっての希望が見えてきます。「神はこのイエスを死の苦しみから解放して、復活させられました」ということが、主イエスにだけでなく、私たちにも起るという希望です。このことは、主イエスの十字架の苦しみと死が、父なる神のお定めになった計画によることだったということによって、主イエスの十字架の死によって私たちの罪の赦しが実現したことが示される、ということと繋がります。主イエスの十字架の死と復活の全体が、神の救いのご計画の実現だったのです。このご計画によって私たちは、「死の苦しみ」から解放されて、新しく生きることができるのです。
ダビデが主イエスの復活を予告していた
24節の後半以降には、「イエスが死に支配されたままでおられるなどということは、ありえなかった」ということが、ダビデが歌ったとされる詩編第16編8節以下の引用によって示されています。そこに、主イエスの復活が予告されていたのです。復活が直接語られているのは27節の「あなたは私の魂を陰府に捨て置かず/あなたの聖なる者を朽ち果てさせない」でしょう。ここでの「私」はダビデ自身のことではなくて主イエスのことであり、「あなた」は父なる神だとペトロは語っているのです。ここに、ダビデの口を通して、主イエスの復活がはっきりと予告されていたのです。だから「イエスが死に支配されたままでおられるなどということは、ありえなかった」のです。
復活した主イエスが共にいて下さる喜び
「ダビデは、イエスについてこう言っています」と25節にあります。それは、今見たようにダビデが主イエスに代って父なる神による復活を予告している、ということでもありますが、それだけではありません。25、26節の「私は絶えず目の前に主を見ていた。主が私の右におられるので/私は揺らぐことがない。それゆえ、私の心は喜び/私の舌は喜び踊った。私の肉体もまた希望のうちに安らう」というところは、ダビデ自身に与えられている喜びと希望です。つまりここでの「私」はダビデであり、「主」は主イエスです。ダビデは、復活して生きておられる主イエスを目の前に見ており、その主が自分の右にいて下さることを感じていたのです。つまりここには、主イエスの復活によって私たちに与えられる喜びと希望も語られているのです。主イエスは父なる神によって、死の苦しみから解放され、復活させられました。死の支配から解放された主イエスは、今も生きておられるのです。私たちはその主イエスを絶えず目の前に見ているのです。またその主イエスが私の右にいて支えて下さっているので、私は揺らぐことがない、ということを体験しているのです。それゆえに、私の心は喜び、私の舌は喜び踊り、私の肉体もまた希望のうちに安らうことができるのです。また28節にあるように「あなたは、命の道を私に示し/御前にいる私を喜びで満たしてくださる」のです。これが、「神はこのイエスを死の苦しみから解放して、復活させられました」という救いのみ業によって私たちに与えられている喜びであり希望です。その喜びと希望は「絶えず目の前に主を見て」おり、「主が私の右におられる」ということの中で与えられます。それは、礼拝を中心とする信仰の生活の中で与えられることです。礼拝こそ、復活した主イエスが私たちの目の前にご自身を示し、絶えず私たちの右にいて支えて下さることを体験することができる場です。その礼拝に支えられて、日々、神のみ言葉である聖書に親しみ、祈りつつ歩むことによって私たちは、命の道を示され、御前にいる喜びで満たされるのです。そして「私の心は喜び」「私の肉体もまた希望のうちに安らい」「私の舌は喜び踊る」つまり感謝と賛美の声をあげ、主イエスの十字架と復活によって与えられた救いを証ししつつ生きることができるのです。