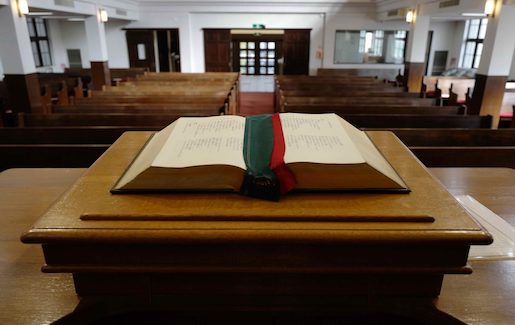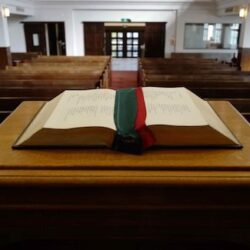説教 「地は誰のものか」牧師 藤掛順一
旧 約 列王記上第21章1-29節
新 約 使徒言行録第17章22-34節
アハブとイゼベルの罪
私が夕礼拝の説教を担当する日には、旧約聖書列王記上からみ言葉に聞いており、今、預言者エリヤの物語を読んでいます。エリヤが活動したのは、ダビデ、ソロモンのイスラエル王国が南北に分裂した後の、北王国イスラエルにおける、アハブ王の時代です。アハブ王については、本日の21章の25、26節にこう語られています。「アハブのように、主の目に悪とされることに身をゆだねた者はいなかった。彼は、その妻イゼベルに唆されたのである。彼は、主がイスラエルの人々の前から追い払われたアモリ人と全く同じように偶像に仕え、甚だしく忌まわしいことを行った」。アハブは、イスラエル王国の歴史において最も甚だしく罪を犯した最悪の王されているのです。本日の21章にも、そのアハブの罪が語られています。そして今読んだ25節にあったように、アハブの罪は妻イゼベルに唆されたものでした。そのことが本日のところにも語られています。イゼベルは、イスラエルの北、フェニキア地方のシドンの王の娘で、その地で拝まれていた偶像の神バアルをイスラエルに持ち込みました。アハブはイゼベルの影響によって、国内にバアルの神殿を築き、積極的にバアル信仰を広めたのです。そのアハブ王と対峙した主なる神の預言者がエリヤでした。列王記上第18章には、エリヤが一人で450人のバアルの預言者と対決して勝利したことが語られていました。しかしイゼベルはそのことによって力を落とすどころか、激しく怒ってエリヤを殺そうとしていました。これが、本日の21章の前までに語られていたことです。
嗣業の土地
さてこの21章に語られている、アハブ王とイゼベルの悪行ですが、事はアハブの宮殿のそばにあった、ナボトという人のぶどう畑をめぐってのことです。アハブはその畑を手に入れたいと願い、ナボトに話を持ちかけます。2節です。「お前のぶどう畑を譲ってくれ。わたしの宮殿のすぐ隣にあるので、それをわたしの菜園にしたい。その代わり、お前にはもっと良いぶどう畑を与えよう。もし望むなら、それに相当する代金を銀で支払ってもよい」。この提案は、私たちの感覚においては、そんなに悪辣なものとは思えません。代わりの、もっと良いぶどう園と交換してくれ、あるいは、きちんと代金を払うから売ってくれ、ということです。このところ、いくつかの教会において、町の再開発のために、それまでの土地を譲って、すぐ近くに代替地をもらって移転し、新しい建物を建てる費用も援助を受けて、立派な会堂が建った、ということが起こっています。今私たちの教会がそういうことを考えているわけでは決してありませんが、そういうこともあり得るのです。しかしナボトはアハブの提案をきっぱりと断りました。3節です。「先祖から伝わる嗣業の土地を譲ることなど、主にかけてわたしにはできません」。ナボトは、最初は断ることによって、売り値をつり上げようとしているのではありません。ここに「先祖から伝わる嗣業の土地」とあります。私たちはこれを、「ここはご先祖様から受け継いだ大事な土地だから」というふうに受け止めてはなりません。「嗣業の土地」という言葉は、イスラエルの人々にとって特別な、とても大事な意味があるのです。イスラエルの人々は、エジプトでの奴隷状態から、主が遣わした指導者モーセの導きによって脱出し、40年の荒れ野の旅を経て、神の約束の地カナンに入りました。そしてそこに先に住んでいた民を滅ぼしてその地を手に入れました。主なる神がその地を彼らに与えて下さったのです。そしてその地を、12の部族の代表がくじを引いて分け合いました。そのことは民数記の第34章に語られています。そのようにしてそれぞれの部族のものとなった土地が「嗣業の土地」です。くじを引く、というのは、聖書においては、神のみ心を尋ねるためのことです。ですからこれは、ただ占領した土地を山分けした、ということではなくて、主なる神が与えて下さった地が、主なる神によってそれぞれの部族そして人々に分け与えられ、その土地が代々受け継がれていく、ということです。ですから「嗣業の土地」は、「ご先祖様から受け継いだ土地」と言うよりも、「主なる神が恵みによって与えて下さった土地」なのです。ナボトが、その土地を譲ることなど、「主にかけてわたしにはできません」と言っているのはそのためです。その土地を手放すことは、主なる神の恵みを無にしてしまうことなのです。
イスラエルの人々が、カナンの地、現在のパレスチナを、主なる神によって自分たちに与えられた土地だ、と考えていることは、いわゆるパレスチナ問題の、そして現在のガザ地区をめぐる悲惨な戦いの一つの原因となっており、今日の人権感覚からして容認できることではありません。つまり私たちはこの聖書の記述を現在の国際政治にそのままあてはめるべきではありません。しかしこの列王記上21章を読む上で私たちが受けとめておくべきことは、ナボトにとって、自分のぶどう畑は、主なる神が恵みによって与えて下さった「嗣業の土地」であり、それを譲ったり売ったりすることは、主なる神の恵みを無にすることだった、ということです。
地は誰のものか
ナボトに断られたアハブはがっかりして塞ぎ込み、食事も取らなくなってしまいました。それは、アハブも「嗣業の土地」とは何かを理解していたからです。だからこれは、条件次第でどうにかなることではないのです。もはや交渉の余地はないことをアハブは悟ったのです。そこに、妻イゼベルが登場します。彼女はこう言いました。7節です。「今イスラエルを支配しているのはあなたです。起きて食事をし、元気を出してください。わたしがイズレエルの人ナボトのぶどう畑を手に入れてあげましょう」。弱気になっている夫の尻をたたいて奮い立たせようとしている強い妻という、今日よく見られる光景ですが、ここにはとても大事なことが語られています。彼女は「今イスラエルを支配しているのはあなたです」と言っています。「あなたがイスラエルの王なのだ、イスラエルを支配する権力を握っているのはあなただ、あなたこそがこの地を支配しているのだ」と彼女は言っているのです。そしてさらに彼女は「わたしがイズレエルの人ナボトのぶどう畑を手に入れてあげましょう」とも言っています。つまり、あなたの王としての権力を用いることによって、自分がナボトの土地を手に入れることができる、権力さえあれば、土地を思い通りにすることができるのだ、ということです。そしてイゼベルは直ちにそれを実行に移します。アハブの名による手紙を書いて、ナボトの町の有力者たちを動かし、ナボトに対する冤罪をでっちあげて、彼を死刑にしてしまったのです。そして所有者のいなくなったぶどう畑を、王のものにしてしまったのです。まったくひどい話ですが、今日でもこういうことは起っています。国家権力が独裁者によって牛耳られると、こういうことが行われるのです。しかしここに語られている大事なことは、イゼベルが、主なる神のご支配を全く否定して、人間の権力こそがこの世を支配している、と思っている、ということです。イスラエルの民の一人であるアハブは、いろいろと悪逆非道なことをしてきた、最悪の王ですけれども、そして主なる神を軽んじてバアル崇拝を導入した人でもありますけれども、しかし彼の心の中には、自分たちが生きているこの地は、主なる神が与えて下さった嗣業の土地だ、という感覚がなお残っているのです。その感覚の根本にあるのは、自分たちが生きているこの地、この世界は主なる神のものであり、自分たちのものではない、ということです。そのことがはっきり語られているのが、レビ記第25章です。そこには、「ヨベルの年」のことが語られています。主なる神が与えて下さる約束の地に入り、それぞれの土地を与えられてから、五十年目ごとの年を「ヨベルの年」とすることを主は命じておられます。その年には、13節にあるように、「おのおのその所有地の返却を受ける」のです。それは、生活に困って土地を売らなければならなくなった人も、ヨベルの年には主に与えられた嗣業の土地を返してもらうことができる、ということです。つまり、イスラエルにおいては、主の嗣業の土地は、たとえそれを売ることがあっても、それはヨベルの年が来るまでの間の使用権を売るのであって、その年になればもともと主なる神がお与えになった所有者のもとに返されるのです。その理由が語られているのが、レビ記25章23節です。そこにはこうあります。「土地を売らねばならないときにも、土地を買い戻す権利を放棄してはならない。土地はわたしのものであり、あなたたちはわたしの土地に寄留し、滞在する者にすぎない」。つまり、主なる神に与えられた嗣業の土地は、本来主なる神のもので、それを与えられた人間は、主なる神の土地に寄留し、滞在しているに過ぎないのです。土地の本当の所有者は人間ではなくて、主なる神だ、というのが、イスラエルの民の根本的な信仰なのです。
ご利益の神は人間に仕える神
それは土地だけの話ではありません。このことが意味しているのは、この世界と私たちの人生の全体を本当に支配しておられるのは主なる神だ、ということです。本日の新約聖書の箇所、使徒言行録第17章にそのことが語られています。パウロは、アテネの町にいろいろな神々の祭壇があり、その中には「知られざる神に」という祭壇まであることから説き起こして、あなたがたが知らずに拝んでいるのは、「世界とその中の万物とを造られた神」なのだ、と語りました。そして25節後半以下にこうあります。「すべての人に命と息と、その他すべてのものを与えてくださるのは、この神だからです。神は、一人の人からすべての民族を造り出して、地上の至るところに住まわせ、季節を定め、彼らの居住地の境界をお決めになりました。これは、人に神を求めさせるためであり、また、彼らが探し求めさえすれば、神を見いだすことができるようにということなのです」。天地万物も、またすべての民族も、その住んでいる地も、主なる神がお造りになり、与えて下さったものなのです。私たちの人生は、この主なる神から預けられた、この世を生きる時間です。私たちはそれを自分の所有物にしてしまうことはできません。主がそれぞれに預けて下さった人生を生き、主がお定めになった時が来たら、それを主にお返ししなければならないのです。私たちがこの世でどんなに力を持っても、このことは変わりません。どんなに強大な権力を握っても、この世界を自分のものとして思い通りにすることはできないのです。それがおできになるのは、主なる神お一人です。イゼベルは、そのことを全く意識していません。人間の王こそがこの世を支配しており、その権力を用いれば、土地の所有者を排除してそれを手に入れることなど簡単にできる、と思っているのです。彼女も、バアルという神を信じ、拝んでいるはずです。しかし偶像の神バアルは、作物の豊作という人間が求めるご利益を与える神です。つまりそれは人間に仕える神です。そのような神をいくら信じて拝んでいても、そこでの主人は、支配者は人間です。偶像とご利益の神は、人間の支配に仕え、それを正当化するものでしかないのです。ですから、ここに描かれているアハブとイゼベルの違いは、気弱な夫と気性の激しい妻、というだけのことではありません。根本的にはこれは、信じている神の違いです。アハブは主なる神を真剣に信じているとは言えませんが、しかし彼も主なる神のもとで養われてきた民の一人であり、その民の王なのです。「主の嗣業の土地」という言葉の持つ厳粛な意味と、その背後にある、この地は主なる神のものであって、人間は主から預けられた地に住んでいるのだ、という感覚、つまり主なる神を畏れる感覚が、彼の中にはなお残っているのです。しかしイゼベルにはそれは全くありません。バアルを拝んでいる彼女にとって、神は、人間の都合次第でどうにでもなる存在なのです。つまりご利益の神、偶像の神を拝んでいる者は、本当の意味で神を信じてはいないのです。神などないと言っている無神論者と、根本的には同じなのです。その彼女にとっては、王こそが、つまり人間の権力を握っている者こそがこの世を支配しているのです。だから神など恐れることなく、自分の欲望を叶えるために、どんな悪逆非道なことでもすることができるのです。
ぶどう畑と菜園
このイゼベルの影響の下でアハブが犯している罪のもう一つの意味がここに象徴的に語られています。2節に、彼がナボトのぶどう畑を「わたしの菜園にしたい」と言っていることにそれが現れています。「ぶどう畑」は聖書において、主なる神が養い、守り、導いておられるイスラエルの民を象徴するものです。その代表的な箇所がイザヤ書第5章です。そこには「ぶどう畑の歌」という小見出しが付けられていますが、その7節に「イスラエルの家は万軍の主のぶどう畑/主が楽しんで植えられたのはユダの人々」とあります。主なる神はイスラエルの人々をご自分の大切なぶどう畑として手入れし、世話をしておられるのです。アハブはそのぶどう畑を「菜園」つまり野菜畑にしようとしています。その言葉は、申命記第11章10節に出て来ます。10節以下読んでみます。「あなたが入って行って得ようとしている土地は、あなたたちが出て来たエジプトの土地とは違う。そこでは種を蒔くと、野菜畑のように、自分の足で水をやる必要があった。あなたたちが渡って行って得ようとする土地は、山も谷もある土地で、天から降る雨で潤されている。それは、あなたの神、主が御心にかけ、あなたの神、主が年の初めから年の終わりまで、常に目を注いでおられる土地である」。このように、「野菜畑」という言葉は、イスラエルの民が奴隷とされていたエジプトの地を表しています。「あなたたちが渡って行って得ようとする土地」、つまり主が与えて下さる嗣業の土地は、エジプトの野菜畑とは違う、と言われているのです。ですからアハブが「ぶどう畑」を「菜園」にしようとしていることは、主なる神によってエジプトの奴隷状態から解放され、その救いにあずかったイスラエルの民を、再び奴隷状態に、今度は偶像の神バアルの奴隷にしようとしている、ということを象徴的に表しているのです。主なる神のご支配を否定して自分が支配者となろうとする時に、私たちはこの世の力の奴隷となってしまうのです。
主の裁きによる王朝の断絶
このような罪を犯したアハブに対して主なる神は、エリヤを遣わしてみ言葉を語られます。17節に「そのとき、主の言葉がティシュべ人エリヤに臨んだ」とあるのはそういうことです。エリヤを通してアハブに告げられた主の言葉は、厳しい裁きの言葉でした。そこにはいろいろなことが語られていますが、その中心となっているのは21節以下です。このようにあります。「見よ、わたしはあなたに災いをくだし、あなたの子孫を除き去る。イスラエルにおいてアハブに属する男子を、つながれている者も解き放たれている者もすべて絶ち滅ぼす。わたしはあなたが招いた怒りのため、またイスラエルの人々に罪を犯させたため、あなたの家をネバトの子ヤロブアムの家と同じように、またアヒヤの子バシャの家と同じようにする」。これがアハブに対する主の裁きの中心です。ここに語られているのは、アハブ個人が主の怒りによって死ぬ、ということではありません。「あなたの子孫を除き去る」と言われています。アハブの罪によってその子孫が除き去られるといのは理不尽なことのように私たちは感じますが、これは、王朝の断絶ということを語っているのです。「あなたの家をネバトの子ヤロブアムの家と同じように、またアヒヤの子バシャの家と同じようにする」というのも同じ意味です。ヤロブアムは、北王国イスラエルの最初の王となった人でした。しかしその王朝は、その子ナダブの時代に、アヒヤの子バシャの謀反によって滅びました。そのことは15章に語られていました。そのようにして王となったバシャの王朝は、その子エラの時代に、やはり家臣ジムリの謀反によって滅びました。そのことは16章に語られていました。しかしジムリは七日間しか王であることはできず、軍司令官だったオムリがジムリを殺して王となったのです。そのオムリの子がアハブです。つまりアハブはオムリ王朝の二代目の王です。その王朝はこの後、アハブの子アハズヤに受け継がれ、アハズヤの死後はアハブのもう一人の子であるヨラムによって受け継がれます。そのヨラムは、イエフの謀反によって殺され、アハブの王朝(つまりオムリ王朝)はそこで滅びるのです。そのことは列王記下の9章に語られています。エリヤが告げた主の裁きはそこで実現したのです。
主を侮ってはならない
このことは、アハブがイゼベルに唆されて犯した罪、主なる神によって造られ、与えられたこの地は、この世界は、そして自分の人生は、主なる神のものであることを見失い、主なる神のご支配を否定して、それを自分のものにしてしまおうとした罪に対する主の怒りと裁きは、ただ個人に及ぶのみでなく、一族全体に、そして国の歴史にさえ及ぶほど大きいことを示しています。私たちはエリヤが告げたこの主の怒りと裁きをしっかり見つめて、主を畏れなければなりません。主のご支配を否定して主を侮ることは滅びをもたらすのです。
アハブの悔い改め
しかしこの21章の最後のところ、27節以下には、不思議なことが語られています。エリヤが告げた主の裁きの言葉を聞いたアハブは「衣を裂き、粗布を身にまとって断食した」のです。これは悔い改めのしるしです。あれほどの罪を重ねてきた、最悪の王であるアハブが悔い改めたのです。そして主は、それを真実な悔い改めと認め、彼が生きている間は災いを下さない、つまり王国の断絶をもたらさない、とお語りになったのです。しかし先ほど見たように、主の裁きはアハブの子の時代に実現するわけで、アハブの悔い改めがもたらしたのは、裁きの先送りでしかありませんでした。そのために、アハブの罪に対する裁きをその子が負わなければならなくなったという、私たちの感覚においてはかえって不可解なことになっています。そういういろいろな疑問は確かにありますが、しかしここには、主なる神が、あれほどの罪を犯したアハブにも、悔い改める機会を与えて下さっていることが示されていると言えるでしょう。主なる神は、基本的に、罪人である私たちを怒りによって裁いて滅ぼそうとしておられる方ではないのです。私たちが悔い改めて赦しを得ることを期待しておられるのです。私たちは、その主の期待に応えることができずに、結局罪に罪を重ねていってしまう者です。イスラエルのどの王朝もそうだったから、滅びを免れることはできなかったのです。しかし主は、私たちを救おうとして下さるそのみ心によって、独り子主イエス・キリストを遣わして下さいました。主イエスは、私たちの悔い改めによってではなく、ご自身が私たちの罪を背負って十字架にかかって死んで下さることによって、罪の赦しと救いの道を開いて下さいました。エリヤが告げたアハブに対する主なる神の厳しい裁きと、その中にも示されている主の救いへのご意志は、主イエス・キリストの十字架の死による救いを指し示しているのです。私たちは、罪に対する主の怒りと裁きを畏れなければなりません。しかしその裁きを、主イエス・キリストが、私たちに代って、ご自分の身に負って十字架にかかって死んで下さったことをも示されています。だから私たちは、主を畏れつつも、その赦しの恵みに感謝して生きることができるのです。