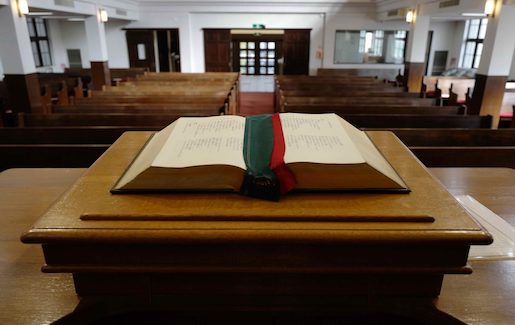説 教 「大きい信仰」 牧師 藤掛順一
旧 約 イザヤ書第56章1-8節
新 約 マタイによる福音書第15章21-28節
異邦人の地に避難した主イエス
本日の聖書の箇所の冒頭のところ、マタイ福音書15章21節に、「イエスはそこをたち、ティルスとシドンの地方に行かれた」とあります。「そこをたち」の「そこ」とは、ガリラヤ湖のほとりの町カファルナウムです。そのカファルナウムでの出来事を私たちは先週まで二週間に亘って読んできました。エルサレムから来たファリサイ派の幹部たちが、主イエスを批判したのです。その批判に応えて主イエスが語られたお言葉が20節までに語られていました。ファリサイ派との厳しい論争、対決がカファルナウムで行われたのです。そのカファルナウムを去って、主イエスはティルスとシドンの地方に行かれました。聖書の後ろの付録の中の「新約時代のパレスチナ」という地図を見ていただくと、ティルスとシドンは地図の一番左上の、フェニキアと呼ばれる地方です。そこはもうユダヤ人の地ではなくて、外国、異邦人の地です。主イエスは何のためにそこに行かれたのでしょうか。異邦人にも福音を宣べ伝えるためでしょうか。そうではありません。この福音書の10章5節で、主イエスは弟子たちを伝道へと派遣するに当って、異邦人のところには行くな、イスラエルの家の失われた羊のところへ行け、と命じておられます。主イエスの伝道は基本的に、神の民であるイスラエルの人々を対象としていたのです。また本日の箇所の24節にも「わたしは、イスラエルの家の失われた羊のところにしか遣わされていない」という主イエスのお言葉があります。だから主イエスがティルスとシドンの地方とう異邦人の地に行かれたのは、伝道のためではないでしょう。では主イエスは何のために異邦人の地に行かれたのか。主イエスは一時、そこに避難したのではないでしょうか。
主イエスはこれまで、神の民であるイスラエルの人々に、神の国の福音を語ってこられました。つまり、神の恵みのご支配が今や始まろうとしていることを告げ、そのしるしとして病気などで苦しんでいる人を癒してこられたのです。しかし人々の反応は鈍いものでした。彼らは、癒しの奇跡には驚き、自分たちも苦しみを癒してもらおうとして押し寄せては来ましたが、主イエスが語っておられる福音を受け入れ、信じる者はほんの僅かでした。民の信仰を指導していたファリサイ派の人々に至っては、むしろ主イエスを拒み、難癖をつけ、殺してしまおうとすらしていたのです。主イエスが彼らの批判に堂々と答え、彼らの間違いを指摘なさったことが先週のところにも語られていました。しかしその主イエスのお心には、「いいかげんしろ」という苛立ちがあったのではないでしょうか。あなたがたは神に選ばれ、恵みをいただいている神の民であり、さらにその指導者ではないか、そのあなたがたがなぜ、父なる神に遣わされた私が語っている福音を拒むのか。堂々と論争をしながら、主イエスのお心はそういう思いで疲れ果てていたのではないでしょうか。そういう思いの中で主イエスは、ユダヤ人たちのもとを一旦離れて、異邦人の地へと避難されたのではないだろうか。はっきり言えば少し休みたいと思われたのではないでしょうか。
主イエスの救いを求めたカナンの女
そのようにして行ったフェニキアの地で、主イエスは一人の女性と出会いました。「この地に生れたカナンの女」と22節にありますから、彼女も異邦人です。しかし彼女は、主イエスがおられることを伝え聞いて、救いを求めてやって来たのです。たまたま出くわしたのではありません。「出て来て」とあるように、彼女はわざわざ主イエスに会いにやって来たのです。そしてこう言いました。「主よ、ダビデの子よ、わたしを憐れんでください。娘が悪霊にひどく苦しめられています」。彼女の娘は悪霊にとりつかれて苦しんでいました。どんな医者も、祈祷師も、娘を治すことはできませんでした。彼女はその苦しみからの救いを主イエスに求めたのです。「主よ、ダビデの子よ」というのは、イスラエルの民の救い主を意味する言葉です。イスラエルとは何の関係もない異邦人の女が、主イエスを、イスラエルの民の救い主と呼んで救いを求めたのです。イスラエルの民の指導者だったファリサイ派の人々は、主イエスに対して決してこのような呼びかけをしません。彼らはイエスが主であるとも、ダビデの子であるとも思っていないのです。イスラエルの民でない異邦人の女性が、このように主イエスに語りかけて来たのは、とても不思議なことであると共に、皮肉なことでもあります。
主イエスの拒絶
しかし主イエスはこの女性の救いを求める叫びに、何もお答えになりませんでした。無視したのです。しかし彼女はそれでも叫び続けながらついて来ました。弟子たちは「この女を追い払ってください。叫びながらついて来ますので」と言いました。主イエスはそれに対して、先ほど読んだように、「わたしは、イスラエルの家の失われた羊のところにしか遣わされていない」とおっしゃいました。自分が遣わされたのは、イスラエルの家の失われた羊のためなのであって、異邦人のためではない、と言って主イエスは、この女性の願いをはっきりと拒絶されたのです。
ところが、主イエスのこの拒絶にもかかわらず、彼女は主イエスの前にひれ伏し、「主よ、どうかお助けください」と言いました。この「ひれ伏し」という言葉は、「礼拝する」という意味でもあります。彼女は主イエスを礼拝しつつ願ったのです。それに対して主イエスはなお、こう言われました。「子供たちのパンを取って小犬にやってはいけない」。「子供たち」とは、イスラエルの民のことです。子供たちのパン、それは、イスラエルの民に与えられるべき神の救いの恵みです。それを小犬にやるわけにはいかない。その小犬とは、異邦人のことです。主イエスは異邦人であるこの女性に、あなたがたは犬だ、私の救いは子供であるイスラエルの民のためのもので、あなたがた犬に与える分はない、とおっしゃったのです。
私たちが体験している現実が語られている
このように主イエスは、この女性の願いを三度にわたって拒絶しました。最初は何も答えないことによって、次は「イスラエルの家の失われた羊のところにしか遣わされていない」と言うことによって、そして最後に「子供たちのパンを小犬にやるわけにはいかない」と言うことによってです。この主イエスのお姿は私たちには不可解に思えます。主イエスは、苦しみからの救いを求めてやって来た人に対して、その願いを拒んだり、無視したりなさらない方であられたはずだ。弟子たちがうるさがって追い返そうとしても、それをたしなめて救いのみ業をして下さる方だったはずだ。それなのにここではどうしてこんなに冷たい態度をとられたのだろうか、と思うのです。このことはこの箇所の一つの大きな謎ですが、それについてはこう考えるべきだろうと思います。それは、この女性が体験したことはそのまま、私たちが信仰をもってこの世を生きていく中で体験することだ、ということです。私たちも、様々な悩みや苦しみをかかえて主イエスのもとに来て、救いを求めます。「主よ、ダビデの子よ、わたしを憐れんでください」というのは私たち一人ひとりの叫びでもあるのです。私たちはそういう思いを抱いて主イエスの前にひれ伏して礼拝をします。礼拝しつつ主イエスの救いを求めるのです。けれども、その私たちの求めや願いに対して、主イエスがすぐに答えて下さるわけではありません。願っても、祈っても、神からは、主イエスからは何の答えもない、ということを私たちは体験するのです。主イエスは自分の願いを無視しておられる、と感じることがあります。さらには、自分のような者は神の救いや主イエスの恵みにはふさわしくない、ということなのか、と思ってしまうこともあります。つまり、私たちが体験している現実が、この女性の置かれた状況に描き出されているのです。
あきらめずに願い求め続けること
そのことに気づく時に、彼女の姿は私たちにとって俄然身近で意味深いものとなります。彼女は、無視されても、拒絶されても、あきらめずに、しつこく、主イエスの救いを求めていったのです。願い求めても答えがなく、苦しみの現実が少しも変わらない中で、私たちはしばしば、簡単にあきらめてしまいます。どうせ自分には救いは与えられないのだ、イエスに救いを求めても無駄なんだ…と思ってしまうのです。しかし彼女は、それでもなお、必死に、願い求め続けたのです。この話は私たちに、あきらめずに願い求め続けることを教えている、と言うことができるでしょう。
子供たちのパンを取って小犬にやってはいけない
けれども、この話のポイントはそこにあるのではありません。あきらめずに願い続ければいつか必ず通じる、ということが言われているのではないのです。この話のクライマックスは何と言っても、「子供たちのパンを取って小犬にやってはいけない」という主イエスのお言葉に対する彼女の応答です。彼女は、「主よ、ごもっともです。しかし、小犬も主人の食卓から落ちるパン屑はいただくのです」と言ったのです。これは、あきらめずに求め続ける、というのとは違うことです。この彼女の言葉の意味をしっかりと受け止めたいと思います。主イエスは、「子供たちのパンを小犬にやるわけにはいかない」と言って彼女の願いを拒絶しました。つまり、彼女は主イエスによって犬呼ばわりされてしまったのです。私たちだったらどうするでしょうか。「犬とは何だ。馬鹿にするな。もう金輪際あんたには頼まない」と真っ赤になって怒るのが普通の反応ではないでしょうか。そうなっても不思議でないことを主イエスはおっしゃったのです。ところが彼女はそうしなかった。怒って立ち去るのではなくて、「主よ、ごもっともです」と言ったのです。これは原文を直訳すれば、「そうです、主よ」というまことに単純な言葉です。彼女は、「子供たちのパンを小犬にやるわけにはいかない」という主イエスのお言葉を、「その通りです」と認めたのです。つまり、自分は子供ではなくて犬です、と言ったのです。それは、自分は主イエスの救いにあずかることを当然の権利として主張できるような者ではありません、ということです。ここに、彼女のこの言葉の第一の重要なポイントがあります。彼女は、異邦人である自分は、主イエスの救いの恵みにあずかることなど本来できない者であり、そんなものを求めることすらもおこがましいのだということを意識しているのです。しかし彼女はそれによってあきらめてはしまいませんでした。そのことを受け入れた上で、なお主イエスに救いを求めたのです。そこに、彼女と私たちとの大きな違いがあるのではないでしょうか。私たちも、苦しみ悲しみの中で、主イエスに救いを求めます。礼拝に集って、「主よ、憐れんでください」と願います。そして「私たちはあなたのみ前に立つことのできない罪人です」などと祈ったりもします。けれども、本当にそう思っているのでしょうか。私たちは、心の中では、自分は主イエスの救いにふさわしくない、などとは少しも思っていない。むしろ神や主イエスは自分に救いを与えるべきだ、それが神の義務だと思っている。神の方でその義務を果たして、自分の願う救いを与えてくれるなら、自分も神を信じてやる、と思っている。それが私たちの本音なのではないでしょうか。だから、ちょっと求めて得られないとすぐに苛立って、あきらめると言うよりも、神が救ってくれないことに腹を立ててそっぽを向いてしまうのです。それは私たちが心の中で、「自分は犬ではなくて子供だから救われる権利がある」と思っているということです。「犬とは何だ、馬鹿にするな」という、一見当然に思える反応の中には、そのような人間の傲慢が潜んでいるのです。
小犬も主人の食卓から落ちるパン屑はいただくのです
しかしこの女性は、そういう傲慢から解き放たれています。彼女は、自分が本当に、主イエスの救いに相応しくない、それにあずかることなど本来できない、小犬のような者であることを知っていたのです。それは人間としての尊厳やプライドを失った卑屈な姿なのでしょうか。そうではありません。この女性からは、卑屈さや惨めさは感じられません。むしろ感じられるのは、彼女の不思議な明るさ、落ち着き、そしてユーモアです。それはどこから来るのでしょうか。「主よ、ごもっともです。しかし、小犬も主人の食卓から落ちるパン屑はいただくのです」と彼女は言いました。ここに彼女のユーモアがあります。「イエス様その通りです。私は小犬でしかありません。でもイエス様、小犬は主人が投げてくれるパン屑をいただいて、主人たち家族の余りものをもらって、それで養われていくんですよ。私だって、イエス様が子供たち、イスラエルの民にお与えになる救いのおこぼれにあずかったっていいんじゃあありませんか。そのことすらも拒むあなたではないはずです」と彼女は言ったのです。彼女は、「私のことを犬呼ばわりするなんてあなたは人を差別している、私だって人間として救いにあずかる権利がある」などと青筋立てて主張しはしませんでした。主イエスの救いは、そのような権利の主張によって獲得できるものではありません。それはただ、主イエスの、神の憐れみのみ心によって与えられるものであり、私たちは、権利としてではなく、まさに食卓からのおこぼれにあずかるようにして、その救いにあずかるのです。
主イエスの恵みへの招き
彼女はそのことを本当に知っていました。それを知っているがゆえに、自分はその救いにふさわしくない、犬のような者だということを素直に受け入れることができたのです。そしてその犬のような者である自分に、なお主イエスの慈しみが注がれており、救いにあずかる希望があることを見つめることができたのです。その希望は、主イエスご自身が暗示して下さったことでもあります。主イエスがおっしゃった「小犬」という言葉は、家で飼われ、かわいがられている小犬を言い表す言葉です。つまり主イエスは彼女に、「おまえは人間様よりも一段低い犬だ」と軽蔑を込めて語られたのではありません。彼女は、主イエスの「小犬」というお言葉の中に、恵みのみ心の暗示を聴き取ったのです。それができたのは、彼女が、自分は主イエスの救いに全くふさわしくない、それにあずかる権利などない者だ、ということを認めていたからです。自分は犬に過ぎない者だと認めていたから、「犬とは何だ」と怒るのではなくて、「小犬」という言葉の中に、主イエスの恵みのみ心と救いへの招きを聴き取ることができたのです。
大きい信仰
主イエスはこの彼女の言葉を聞いて、「婦人よ、あなたの信仰は立派だ」とおっしゃいました。「立派だ」という言葉は、文字通りには「大きい」という意味です。「あなたの信仰は大きい」と主イエスは言われたのです。信仰が大きいとはどういうことなのでしょうか。それは、信仰によって立派な行いができる、とか、愛に溢れた人になれる、ということではありません。信仰が大きいというのは、この女性のように、自分が主イエスの救いに全く価しない者であり、本来それにあずかることなどできない者であることを、言葉の上の立て前としてではなく、本当に知っていることです。そして、その全く価しない自分に、主イエスがその憐れみのみ心によってみ手を差し伸べて下さり、救いの恵みを与えて下さることを信じて疑わないことです。それを信じるがゆえに、無視されても、拒絶されても、おまえなんかお呼びじゃない、という思いをさせられても、あきらめずに求め続けることです。「信仰が大きい」とはそういうことなのです。
主イエスはこれまでに何度か、「あなたがたの信仰は小さい」とおっしゃいました。最初は6章30節で、「何を食べようか、何を飲もうか」と思い悩む者たちに、次は8章で、嵐で舟が沈みそうになって慌てふためいている弟子たちに、それから14章で、主イエスを信じて水の上を歩き始めたのに、風を見てこわくなり、溺れかけたペトロにです。いずれも「信仰の薄い者よ」と訳されていますが、直訳すれば「信仰が小さい」です。この世の厳しい現実の中で、神の、主イエスの恵みを信じ切ることができずに、疑いと恐れに陥っていくこと、それが「小さい信仰」です。それに対してこの女性の、主イエスに拒絶されているような厳しい現実の中で、自分は救いに相応しくない者であることをはっきりと受け入れつつ、なおそこに主イエスの恵みにあずかる希望を見出していく、それが「大きい信仰」なのです。
主イエスご自身も癒され、励まされて
「あなたの願いどおりになるように」と主イエスはおっしゃいました。その時、彼女の娘は癒されたのです。徹底的に拒絶されているとしか思えなかった救いが、豊かに彼女に注がれたのです。このことは、彼女にとって救いの出来事であったことは勿論ですが、それと同じくらい、主イエスにとっても、ある意味で救いとなったのではないでしょうか。神の民イスラエルの不信仰のために疲れを覚え、異邦人の地へと避難していた主イエスが、異邦人である彼女の「大きい信仰」に触れて、疲れを癒され、励ましを与えられたのではないでしょうか。主イエスはこの後ガリラヤに戻り、再び精力的に、父なる神によって遣わされた救い主としてのみ業を続けていかれます。そのことがこの後の29節以下に語られています。そしてその歩みは、私たちの全ての罪を背負って、十字架にかかって死んで下さることにまで至るのです。そして、主イエスの十字架の死と復活によって実現した神の救いの恵みは、イスラエルの民、ユダヤ人だけに与えられたのではなくて、そこから豊かに溢れ出て、異邦人たち、全世界の人々へと広められていったのです。私たちも今、その恵みにあずかっています。全くふさわしくない、何の権利もない私たちが、主イエスの恵みの「おこぼれ」にあずかって、その「食卓から落ちるパン屑」によって養われているのです。この女性と同じことを、私たちも体験しているのです。だから私たちも、この世の厳しい現実の中で、明るさと、落ち着きと、ユーモアを失わずに、主イエスの恵みを信じて求め続けていく大きな信仰に生きることができるのです。