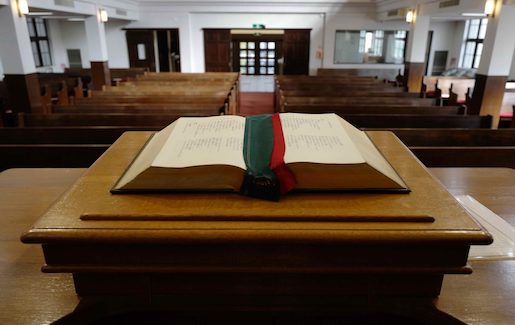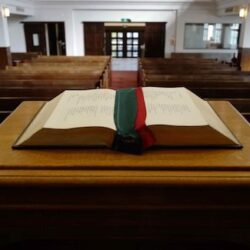説教「主イエスの昇天」 副牧師 川嶋章弘
旧約聖書 詩編第47編1-10節
新約聖書 使徒言行録第1章6-11節
第一巻と第二巻を結びつける出来事
先週から使徒言行録を読み始め、使徒言行録の連続講解説教が始まりました。先週はその冒頭1章1~5節を読み、使徒言行録がルカによる福音書の続きであることを見ました。ルカ福音書と使徒言行録の著者とされるルカは、ルカ福音書を第一巻として、使徒言行録を第二巻として書いたのです。
本日の箇所1章6~11節では、主イエスの昇天が語られています。主イエスの昇天は、ルカ福音書の終わり24章50、51節でも語られていて、このように言われていました。「イエスは、そこから彼らをベタニアの辺りまで連れて行き、手を上げて祝福された。そして、祝福しながら彼らを離れ、天に上げられた」。このように主イエスの昇天の出来事は、使徒言行録の始まりだけでなくルカ福音書の終わりでも語られていて、第一巻と第二巻を結びつける蝶番(ちょうつがい)のような働きをしているのです。しかしそれは単なる繰り返しではありません。そこには視点の違いがあります。そのことにも目を向けつつ、使徒言行録が語る主イエスの昇天の出来事に目を向けていきたいのです。
天にのぼり、神の右に座し
ところで本日の説教題を見ると分かるように、主イエスの昇天の「昇天」は、「昇る」「天」と書きます。同じ「しょうてん」でも、キリスト教の特にプロテスタント教会で、キリスト者の死を言い表すときは、「召される」「天」と書きます。この二つの言葉が時々混同されることがあるので、注意が必要です。キリスト者の死は、天に召されること、神様の御許に迎え入れられることですから、「召される」「天」と書いて「召天」です。しかし主イエスの昇天はそれとは違います。この「昇天」という言葉も一般的には死を意味することもありますが、主イエスに用いられる場合は、主イエスの死を意味するのではありません。主イエスは十字架で死なれ、墓に葬られ、しかし三日目に神様によって復活させられました。しかもそれは、からだを持った復活でした。ルカ福音書の終わりで、復活の主イエスはご自分の手と足をお見せになり、また焼いた魚を一切れ食べて、ご自分がからだを持って甦られことを示してくださったのです。主イエスの昇天とは、からだを持って甦られた主イエスが、そのからだを持ったままで天に昇られた、ということです。私たちが毎週の礼拝で告白している使徒信条に、「三日目に死人のうちよりよみがえり、天にのぼり、全能の父なる神の右に座したまえり」とあるように、主イエスは天に昇られ、父なる神の右に座しておられます。それは天に昇られ、天におられる主イエスが、父なる神様から委ねられて、この世界を統治してくださっている、ということなのです。
愛と恵みによる世界統治
共に読まれた旧約聖書詩編47編は、教会の暦に沿った聖書日課では、主イエスの昇天を記念する日に読まれる箇所の一つです。その6節には「神は歓呼の中を上られる。主は角笛の響きと共に上られる」とあり、さらに9節には「神は諸国の上に王として君臨される。神は聖なる王座に着いておられる」とあります。つまり、神が上られて王座に着き、「諸国の上に王として君臨される」ことが預言されているのです。この預言が、主イエスの昇天において実現しました。つまり47編の「神」とは、父なる神ではなく、子なる神イエス・キリストを指し示しています。復活のからだを持って天に昇られたイエス・キリストは、天におられ、王としてこの世界を統治してくださっているのです。その統治は、この世の支配者の権力や軍事力による統治とはまったく異なり、愛と恵みによる統治です。十字架でご自分の命を犠牲にされたほどに、私たちを憐れみ、愛してくださる主イエスが天におられ、この世界と私たちを統治してくださっているのです。
王国再興についての問い
さて冒頭6節に、「さて、使徒たちは集まって」とあります。初めに見たようにルカ福音書は、主イエスがベタニアの辺りで天に昇られたことを語っていました。ベタニアはオリーブ山の南東に位置する村です。また、本日の箇所の続きである12節には、「使徒たちは、『オリーブ畑』と呼ばれる山からエルサレムに戻って来た」とあるので、冒頭6節で言われているのは、使徒たちがベタニアの辺りに、あるいはオリーブ山に集まった、ということでしょう。
そのとき使徒たちは、一つの問いを主イエスに投げかけました。「主よ、イスラエルのために国を建て直してくださるのは、この時ですか」。「イスラエルのために国を建て直してくださる」とは、イスラエル王国の再建、再興を意味します。イスラエル王国は、旧約聖書を読むと分かるように、サウルに始まり、続くダビデ、ソロモンの時代に最盛期を迎え、しかしその後、北王国と南王国に分裂し、やがて両王国とも滅亡しました。以来、イスラエルの人たちは長く国を失い、あるいは国はあっても、外国の支配のもとで本当に独立しているとは言えない状態にありました。そのような状況の中でイスラエルの人たちは、外国の支配から解放され、独立した国となることを、王国の再興を待ち望んでいたのです。そして神様によって遣わされたメシア、救い主こそが王国の再興を実現する、と信じていました。このことが使徒たちの問いの背景にあります。彼らは十字架で死なれ復活された主イエスが、救い主としてイスラエル王国を再興し、その王として君臨してくださると期待して、王国の再興が実現するのは「この時ですか」、と尋ねたのです。
知りたがる
それに対して主イエスは、このようにお答えになりました。「父が御自分の権威をもってお定めになった時や時期は、あなたがたの知るところではない」。主イエスの復活によってイスラエル王国の再興が実現すると期待していた使徒たちに対して、主イエスはそれがいつ実現するかを知ることはできない、と言われたのです。使徒たちの問いには、いくつかの勘違いがありますが、その一つは、いつ王国が再興するのかを自分たちは知ることができる、という勘違いです。しかしその「時や時期」は、父なる神様がご自分の権威をもってお定めになることであり、使徒たちは知ることができないのです。
このような勘違いは私たちにもしばしば起こります。私たちはいつも、時期や場所、あるいは理由を知りたがります。もちろん「もっと知りたい」という欲求のすべてを否定する必要はありません。「もっと知りたい」と思うからこそ、探求や向上が生まれていくからです。信仰においても、聖書のこと、神様のことを「もっと知りたい」と思うのは、基本的には良いことでしょう。しかし私たちが、聖書に書かれていることを超えて、「もっと知りたい」と思うなら、私たちは自分たちが何でも知ることができる、と勘違いしているのです。私たちは聖書に書かれていることで満足すべきです。「満足すべき」というのは、不十分だけどそれで我慢しなさい、ということではありません。聖書に書かれていることで十分だ、ということです。別の言い方をすれば、神様は私たちが知るべきことはすべて教えてくださっている、ということです。私たちが時期や場所、あるいは理由を知りたがるのは、それが分からないと安心できないと思っているからです。しかし私たちは、神様が知らなくてよい、とお決めになったことを知ろうとするのではなく、神様に委ねることによってこそ、本当の安心を得ることができるのです。
キリストの証人となる
主イエスは使徒たちに、王国再興の時期を知りたがるよりも、ほかになすべきことがある、と言われます。それが8節です。「あなたがたの上に聖霊が降ると、あなたがたは力を受ける。そして、エルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また、地の果てに至るまで、わたしの証人となる」。彼らがなすべきことは、キリストの証人となることです。キリストが十字架で死んで、復活されたことによって実現した救いを証ししていく者、宣べ伝えていく者となることなのです。それは彼ら自身の力でできることではありません。聖霊が彼らの上に降り、彼らが聖霊による力を受ける必要があるのです。この聖霊によって与えられる力とは、必ずしも奇跡を行う力ではないでしょう。それも含むのかもしれませんが、むしろこの力とは、キリストの証人として歩む力、キリストを証しすることに命がけになれる力です。証人と訳された言葉はギリシア語で「マルトゥース」で、これが英語の「マーター」(殉教者)の語源となりました。キリストの証人とは、命がけでキリストを証しする者なのです。それはもちろん殉教しなければならないということではありません。そうではなく自分の思いと時間を割いてキリストを証しする、ということです。私たちは自分にはそんな力はないとか、まだ準備が整っていないと言ったり思ったりします。しかし自分の力でキリストの証人として歩もうとしても、そんなことはできません。いつまでたっても準備ができていない、と思い続けるだけです。私たちは聖霊の力を受けることによって、聖霊の力に全身を覆われることによって、命がけで、自分の思いと時間を割いてキリストを証しする者とされるのです。主イエスは弟子たちに、王国再興の時期を知りたがるのではなく、命がけでキリストを証しするキリストの証人となるために、聖霊が降り、聖霊の力を受けることに心を向けるよう言われました。私たちも聖書に書かれていることを超えて知りたがるのではなく、このことに心を向けて、聖霊が私たちにも降り、私たちが聖霊の力を豊かに受けて、キリストを証ししていくことができるよう祈り求めていくのです。
新しい神の民、教会の誕生
さて、使徒たちは地上の国家として、イスラエルの国が再興されることを期待していました。しかしそれとは違う形で、イスラエルは再興される、と言うことができます。それが2章で語られている聖霊降臨の出来事、ペンテコステの出来事です。つまり聖霊が降り、教会が誕生することこそイスラエルの再興であり、新しい神の民の誕生なのです。教会こそ、再建され、再興されたイスラエルであり、新しい神の民です。しかしこの新しい神の民は、イスラエルの人たちだけ、つまりユダヤ人だけの群れではありません。使徒たちの問いのもう一つの勘違いは、そもそも彼らがユダヤ人だけの国の再興を考えていたことにあります。しかし主イエスは8節後半でこのように言われていました。「エルサレムばかりではなく、ユダヤとサマリアの全土で、また、地の果てに至るまで、わたしの証人となる」。これは使徒言行録の目次と言われることもあります。使徒言行録では、7章までが「エルサレム」において、8章から9章31節までが「ユダヤとサマリアの全土で」、そしてそれ以降は、「地の果てに至るまで」、キリストの証人である弟子たちの働きによって、福音が宣べ伝えられていくことを語っているからです。ユダヤ人だけでなく、サマリア人にも、異邦人にもキリストによる救いが宣べ伝えられていくのです。ユダヤ人だけでなく、サマリア人も異邦人も、すべての人が新しい神の民へと、教会へと招かれていきます。そしてその招きに応え、洗礼を受けた者たちが新しい神の民に、教会に加えられていくのです。使徒たちは、聖霊が降って誕生する教会にすべての人を招いていくために、キリストの証人として、主イエスの十字架と復活による救いを証ししていくのです。
最後の言葉
9節冒頭に「こう話し終わると」とあります。しかしそれは主イエスの話が単に終わったということだけではありません。先ほど8節は、使徒言行録の目次と言われると申しました。しかしそれ以上に、8節は地上を歩まれた復活の主イエスが語った最後の言葉です。この後、使徒言行録は、天におられる主イエスが弟子たちに語りかけてくださることを記しています。しかし地上においては、「あなたがたの上に聖霊が降ると、あなたがたは力を受ける。そして、エルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また、地の果てに至るまで、わたしの証人となる」という言葉が、主イエスが使徒たちに語った最後の言葉なのです。この最後の言葉は、私たちの教会に向かっても語られています。この言葉を与えられて、この言葉に押し出されて、私たちの教会は伝道していくのです。聖霊が降るのはペンテコステだけではありません。今も聖霊は私たちの群れの上に降り、私たちは聖霊による力を受けているのです。今もなお、主イエスによる救いの良い知らせ、福音は、「地の果てまで」、すべての人に宣べ伝えられたわけではありません。私たちの教会は、この主イエスの最後の言葉を与えられて、聖霊による力を受けて、まだ主イエスに出会っていない人々に福音を宣べ伝えていくのです。
主イエスの昇天
しかしそのためには、つまり聖霊が降り教会が誕生し、弟子たちが、そして私たちがキリストの証人として、福音を宣べ伝えていくためには、主イエスが昇天する必要がありました。主イエスの昇天はあってもなくても良いことではありません。新しい時代、つまり教会の時代が始まるために不可欠な出来事であったのです。9節でこのように言われています。「イエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなった」。ルカ福音書では「祝福しながら彼らを離れ、天に上げられた」と言われていて、主イエスが弟子たちを祝福しながら天に上げられたことが語られていました。しかし使徒言行録では、それとは異なる視点で語られています。弟子たちの目に見えていた主イエスが、天に上げられることによって見えなくなった、と言われているのです。主イエスの昇天によって、弟子たちはその目で主イエスのお姿を見ることができなくなったのであり、また10節に「イエスが離れ去って行かれるとき」とあるように、主イエスは弟子たちから、弟子たちが生きている地上から離れ去って行かれたのです。主イエスの昇天以後の時代を生きている私たちもこの目で主イエスのお姿を見ることはできません。私たちが生きているこの地上に主イエスがおられるわけではないのです。
昇天によって与えられる恵み
そうであるなら主イエスが昇天しなかったほうが良かったのでしょうか。主イエスが天に昇られなければ、私たちもこの地上で主イエスにお会いすることができたかもしれません。そのほうが良かったのかな、とも思います。しかしそうではありません。主イエスの復活は、からだを持った甦りでした。この地上においてからだを持っているということは、時間と空間の制約を受けるということです。ある時間にある場所にいたら、同じ時間にほかの場所にはいることはできません。そうなると、ある場所で伝道している弟子とは主イエスが一緒にいてくださるけれど、同じ時にほかの場所で伝道している弟子とは一緒にいてくださらない、ということになります。私たちにも同じことが起こります。主イエスがあの人と一緒におられるなら、同じ時にほかの場所にいる自分とは一緒にいてくださらない、ということになるのです。しかし主イエスが天に昇られたとは、地上の時間や空間の制約を受けることがなくなった、ということです。天に昇られることによって主イエスは、いつでもどこでも私たち一人ひとりと一緒にいてくださるようになったのです。あの主イエスの最後の言葉は、私たち自身の力によって実現していくのではありません。主イエスがいつも共にいてくださらなければ、私たちがキリストの証人として「地の果てに至るまで」福音を届けることなどできるはずがないのです。そして、天におられる主イエスが私たちといつも共にいてくださるのは、聖霊のお働きによってです。昇天の主イエスが聖霊を送ってくださったことによって、このことは実現したのです。天におられる主イエスが聖霊のお働きによって私たち一人ひとりといつも共にいてくださり、私たちを導き、支え、守っていてくださる。この計り知れない大きな恵みは、主イエスの昇天があってこそ私たちに与えられているのです。
伝道の使命と責任
また、主イエスが地上におられるなら、弟子たちも私たちもキリストの証人として歩む必要はありません。主イエスが天に昇られたからこそ、私たちはキリストの証人として、地上にはおられない主イエス・キリストを証ししていくのです。そのことを通して、新しい神の民に、教会に加えられる人々が起こされていきます。主イエスはご自分が伝道されるのではなく、聖霊によって誕生した教会に、新しい神の民に、伝道の業を委ねられました。あの主イエスの最後の言葉は、このことをも告げています。私たちの教会は伝道という重い使命と責任を与えられているのです。教会の歩みに天におられる主イエスが聖霊の働きによっていつも共にいてくださることに信頼して、私たちの教会はこの伝道の使命と責任を果たしていくのです。
主イエスの再臨の約束
使徒たちに、そして私たちには、主イエスの最後の言葉だけでなく、約束も与えられています。主イエスが天に昇り、使徒たちの目から見えなくなった後、彼らは天を見つめていました。すると「白い服を着た二人の人」が、つまり主の使いが彼らのそばに立って、このように告げました。「ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなたがたから離れて天に上げられたイエスは、天に行かれるのをあなたがたが見たのと同じ有様で、またおいでになる」。天に昇られた主イエスが、また来てくださる。これが使徒たちと私たちに与えられている約束です。しかも、「天に行かれるのをあなたがたが見たのと同じ有様で」、つまりからだを持って復活され、天に昇られた主イエスが、からだを持って再び来てくださるのです。これを「主イエスの再臨」と言います。主イエスが再び来てくださるとき、私たちの救いが完成し、私たちは復活と永遠の命にあずかるのです。教会は、主イエスの昇天と再臨の間を歩んでいます。その歩みは、いつ主イエスの再臨が起こるのかとあれこれ思い悩む歩みではありません。それは、ただ天を見上げて突っ立っているような歩みでしかないでしょう。そうではなく教会は、主イエスの昇天と再臨の間にあって、「地の果てに至るまで」、主イエスの十字架と復活による救いを宣べ伝えていくのです。その教会の歩みに、主イエスの再臨の約束が伴っています。主イエスが再び来てくださり、救いを完成してくださるときに、私たちが復活と永遠の命にあずかり、目に見える、体をもった主イエスといつまでも共に生きるようになる、という約束が伴っているのです。この約束に希望をおいて、また天におられる主イエスが聖霊のお働きによって共にいてくださることに信頼して、私たちの教会は、福音を宣べ伝えていくのです。
隣人に仕えることを通して
しかしそれは、言葉によって宣べ伝えるだけではありません。私たちの教会は、毎週の礼拝で、主イエスが私たちの救いのために十字架で死なれ、復活されたことを告げ知らせます。しかしそれだけが伝道ではありません。それだけで伝道は終わりません。教会に連なる私たち一人ひとりが、礼拝から遣わされた先で、日々の生活の中で、隣人を愛し、隣人に仕えることを通して、主イエスの救いを証ししていくのです。私たちは主イエスの再臨と救いの完成に希望をおいて、天におられる主イエスが聖霊によっていつも共にいてくださることに信頼して、隣人を愛し、隣人に仕えて歩みます。それは決して簡単なことではありません。困難があり、葛藤があります。あきらめてしまいそうになることもあります。それでもなお聖霊によって力を与えられ、主イエスが私たちに仕えてくださったように、私たちも隣人に仕えていくのです。仕えていこうとするのです。その私たちの歩みを通して、職場や学校や家庭での歩みを通して、主イエスの救いが証しされていくのです。そのようにして私たちはキリストの証人として歩んでいきます。福音が「地の果てに至るまで」、すべての人に宣べ伝えられるまで、キリストの証人として歩んでいくのです。