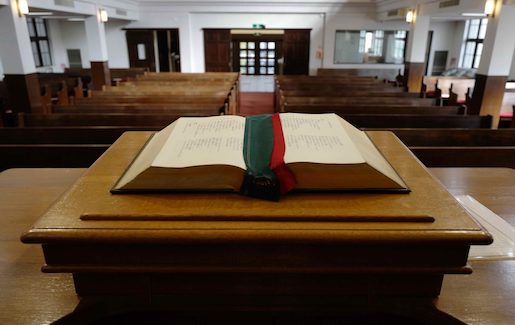説教 「主イエスの家族」 牧師 藤掛順一
旧 約 詩編第1編1-6節
新 約 マタイによる福音書第12章43-50節
主イエスの母と兄弟たち
マタイによる福音書第12章46節には、主イエスの母と兄弟たちが出てきます。主イエスの母がマリアという名だったことは、この福音書の第1章に語られていました。マリアはヨセフと婚約していましたが、一緒になる前に聖霊によって身ごもり、主イエスを生んだのです。ヨセフは天使のお告げにより、自分によらずに身ごもったマリアを妻として迎え入れ、そして1章の最後の25節にあるように「男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかった」のです。この文章は、主イエスが生まれた後、ヨセフとマリアは普通の夫婦としての関係を持っていったことを暗示しています。つまり主イエスには弟、妹たちがいたのです。その母ときょうだいたちが、ガリラヤ地方を巡って伝道をしている主イエスのもとに来た、というのが本日の箇所です。しかし本日の箇所で主イエスは母と兄弟たちについて、大変冷たい、厳しいお言葉を語っておられます。ある人が「御覧なさい。母上と御兄弟たちが、お話ししたいと外に立っておられます」と言ったのに対して主イエスは、「わたしの母とはだれか。わたしの兄弟とはだれか」と言われたのです。まるで、そんな人たちは母でも兄弟でもない、関係ない、と言っているようです。主イエスはどうしてそんなことを言われたのでしょうか。
身内としての心配?
マルコによる福音書の第3章31節以下には、この出来事がマタイとほぼ同じ内容で語られています。しかしマルコは、その前の21節に、主イエスの家族が何のためにやって来たのかを語っています。そこには「身内の人たちはイエスのことを聞いて取り押さえに来た。『あの男は気が変になっている』と言われていたからである」とあります。主イエスは、ルカ福音書3章23節によれば、およそ三十歳の時に家を出て、神の国の福音を宣べ伝え始められました。それまでは、長男として、そしてマリアの夫ヨセフは早くに亡くなっていたようですから、一家の大黒柱として、家業を継いで家を守っていたのです。その主イエスが家を出て、家族を離れ、伝道の生活に入るというのは、母マリアや兄弟たちにとって大変なことだったでしょう。そしてうわさによれば、イエスはあちこちで、律法学者やファリサイ派の人々と論争をしたり、病人を癒す奇跡を行っているという。母やきょうだいたちは、イエスは気が変になってしまった、と思ったに違いありません。だから家族として、このまま放っておくわけにはいかない。なんとかして家に連れて帰らなければ、と思ったのです。マルコ福音書からはそういうことが見えてきます。「母と兄弟たちが、話したいことがあって外に立っていた」という、その「話したいこと」というのは、「もうこんなことはやめて、私たちと一緒に家に帰ろう、そしてしばらく休んだ方がいい」ということです。そのように主イエスを説得するために彼らは主イエスのもとにやって来たのです。この母や兄弟たちは、決して主イエスに敵対しているわけではありません。むしろ身内として心配しているのです。そういう意味では彼らは、この12章14節で、イエスを殺そうと相談した、あるいは24節で、主イエスの癒しの業を悪霊の頭ベルゼブルの力によるのだと言ったファリサイ派の人々とは違います。しかし結果的には、彼らの家族としての愛と心配も、主イエスの救い主としてのお働き、その伝道と癒しのみ業を妨げるものになってしまっています。主イエスはそういう母や兄弟たちに、「わたしの母とはだれか。わたしの兄弟とはだれか」という厳しい、冷たい言い方をなさったのだと言えるでしょう。
外に立っている
しかしこれは、マルコ福音書の記述から見えてくることです。マタイは、母や兄弟たちが何のために主イエスのもとに来たのかを全く語っていません。マタイはマルコを土台として書かれていると言われていますから、マタイも、マルコの記述を知っていたと思います。しかしマタイは、この話から、彼らの身内としての思いを示す言葉を取り除いているのです。そしてマタイがこの話で強調していることがあります。それは、母や兄弟たちが「外に立っている」ということです。その言葉は46節と47節に二回語られていて、この短い話の中で際立っています。母や兄弟たちは、主イエスが群衆に話しておられる、その輪の外に立っているのです。主イエスはこの時、カファルナウムのペトロの家で、集まった人々に教えておられたのかもしれません。あるいは、野外で、集まった群衆たちに語っておられたのかもしれません。いずれにしても、母や兄弟たちは、主イエスの話を聞いている人々の中に入っては来ないで、外に立っているのです。そこに、彼らの主イエスに対する姿勢、思いが象徴的に示されています。彼らは主イエスのことを外から眺めて、その教えを判断し、評価しているのです。そしておそらくはマルコが語っているように、「気が変になっている」と思って「取り押さえに来た」のです。そのように、主イエスのことを外から眺めて判断、評価することは、私たち誰もがしていることです。マタイはこの話から、身内としての思いを語る言葉を取り除くことによて、これを、私たち一人一人と関係する話として語っているのです。これは決して、主イエスの母や兄弟たちに限られたことではないのです。
「距離を置く」ことによって起っていること
「外に立っている」という言葉には、主イエスに対して、ある距離を置いているという意味が込められています。ある距離を置いて、少し離れた所から、主イエスとその教えのことを見ているのです。物事は、そのようにある距離を置いて見た方が、客観的に、正確に見ることができる、ということもあります。「木を見て森を見ない」という言葉があるように、渦中に入ってしまうと目の前のことしか見えなくなって、全体がわからなくなる、正確に捉えることができなくなる、ということは確かにあります。そういう意味では、主イエスとその教えについても、「外に立って」、少し距離を置いて見ることが必要なのかもしれません。けれども、一般論としてそのように言うことはできますが、実際に「外に立って」、距離を置いて主イエスとその教えを見るところに起っているのはどのようなことでしょうか。私たちがこの12章において読んできたファリサイ派の人々の姿がまさにそれを示しているのではないでしょうか。12章の始めのところで、彼らは、主イエスの弟子たちが、安息日に麦の穂を摘んで食べたことを批判しました。また、主イエスが安息日に片手の萎えた人を癒したことに怒り、主イエスを殺そうと相談を始めました。それは彼らが、主イエスの教えやみ業を外から、距離を置いて見ていることから生じたことです。彼らは、自分たちの持っている律法理解、神の掟に従うとはこういうことだという理解から、主イエスの教えやみ業を判断し、批判しているのです。距離を置いて見るところにはそういうことが起るのです。「距離を置いて、客観的に」というのは、実際には、自分の持っている基準に照らして判断する、ということです。しかし自分の理解や基準や常識によって判断しようとすると、主イエスが神の言葉を語っておられ、神の恵みのみ業を行っておられることが見失われてしまう、ということが起るのです。彼らファリサイ派の人々は、安息日に、空腹の人の飢えが満たされることを喜んで下さる神の憐れみのみ心を、また片手の萎えた苦しみの中にある人が癒されることを喜んで下さるみ心を全く見失っています。主イエスの癒しのみ業を、「悪霊の頭ベルゼブルの力によるのだ」と言ったのも、彼らが主イエスに対して距離を置いているからです。彼らは、悪霊に取りつかれて目が見えず、口が利けなかった人が癒され、ものが言えるようになり、目が見えるようになった、という喜ばしい恵みの出来事から距離を置いて、そこになされている神の恵みのみ業を見つめようとしないのです。そこに生まれるのは、これは悪霊の頭が子分に命令しているだけだ、という屁理屈です。つまり彼らは、主イエスのなさっていることからできるだけ距離を置き、外から、遠くから見ることによって、自分に都合のよい、自分が変わらずにすむ理屈をつけようとしているのです。「外に立つ」ことの本質はそこにあると言えるでしょう。外に立つのは、自分が変わりたくないからです。主イエスと関わることによって自分が変えられてしまうのを防ぐために、距離を置こうとするのです。また38節で、主イエスにしるしを求めた人々の姿も、外に立つ人の典型です。外に立つとは、自分の持っている基準で判断しようとすることだと先ほど申しましたが、しるしを求めるというのはまさに、自分の基準に合うしるしを求めるということです。「あなたが神の子であり救い主であることを、私が納得できるように示してくれ」というのはそういうことです。主イエスに対して、外に立ち、距離を置こうとしている者が、そのように言うのです。そして最後に、主イエスに対して外に立とうとしている者の姿を最も端的に示しているのが、43節以下の、「汚れた霊が戻って来る」というたとえ話ではないでしょうか。汚れた霊を追い出して、きれいに掃除をし、整えられている家のたとえです。しかしその家は空き家であり、住む人、所有者がいないのです。それはまさに、主イエスと距離を置き、外に立とうとしている人の姿です。つまり主イエスの教えを学びはするし、尊敬もして、それを参考にして生きていこうとは思うけれども、主イエスを自分の心の家に迎え入れ、自分の心の主人になってもらおうとはしないのです。あまりのめり込むのはやめておいて、少し客観的に、距離を置いてイエス様と付き合おうとしているのです。そういう人の心というのは、守る人のない空き家であって、悪霊の絶好の餌食だ、というのがこの話の教えていることです。主イエスに対して外に立つことによって、悪霊が私たちの内に入ってきて、私たちを支配するのです。そういう繋がりのゆえに、前回と重複していますが、本日も43節からを読んだのです。
ここにわたしの母、わたしの兄弟がいる
主イエスは、外に立っている母や兄弟たちについて、「わたしの母とはだれか。わたしの兄弟とはだれか」と大変厳しいことを言われました。しかしそれはよく読めばわかるように、母や兄弟たちに対して言われたのではありません。むしろこれは主イエスの周りに集って、その教えを聞いている人々、つまり外ではなくて中にいる人々に対して語られたお言葉です。そしてそれは、次の49、50節のみ言葉への導入となっているのです。「そして、弟子たちの方を指して言われた。『見なさい。ここにわたしの母、わたしの兄弟がいる。だれでも、わたしの天の父の御心を行う人が、わたしの兄弟、姉妹、また母である』」。弟子たちこそ、外ではなく中にいる人々です。この弟子たちこそ、わたしの母、わたしの兄弟、つまり主イエスの本当の家族であると言われたのです。つまり主イエスはここで、身内の者たちなど家族ではない、と言われたのではなくて、主イエスの本当の家族とは誰か、を示されたのです。そして、「だれでも、わたしの天の父の御心を行う人が、わたしの兄弟、姉妹、また母である」と言うことによって、だれでも、どんな人でも、つまり私たちも、主イエスの本当の家族になれる、ということを示されたのです。つまりここには主イエスの大いなる招きがあります。あなたも私の本当の家族になれる、私はあなたにも私の家族になってもらいたい、そう主イエスは私たち一人一人に語りかけておられるのです。
神の御心を行う
この招きに応えて主イエスの本当の家族になるには何が必要なのでしょうか。それは「わたしの天の父の御心を行う人」になることです。「わたしの天の父」つまり父なる神の御心を行うことが、主イエスの家族になるためには必要なのです。しかしそこで私たちはよくよく注意しなければなりません。というのは、あのファリサイ派の人々だって、自分たちは神の御心を行っていると思っていたからです。彼らは律法を熱心に学び、それを厳格に守って生活していました。それが神の御心を行うことだと思っていたのです。このことが教えているのは、神の御心を行っていると思っている者が、実際には主イエスの外に立つ者となっている、ということがあり得るということです。それは、神の御心を自分でこうと決めてしまうからです。これが神の御心だ、ということを自分はもう知っている、わかっている、と思い、それを少しも疑わない、その時に私たちは実は、自分の思い、自分の考え、自分の基準を神の御心と勘違いしており、それを主張することによって、主イエスからは距離を置いてしまう、ということが起るのです。ですから、「神の御心を行う」ということにおいて私たちはよほど慎重でなければなりません。そう言っている時にこそ、人間は最も大きな罪を犯すものなのです。神の名によってテロが行われ、神の名によってそれに報復する、ということがこの世界には起っています。自分の思いをそのまま神の御心と思ってしまうところにそういことが起こるのです。
主イエスのもとに集うこと
そういう間違いに陥らないためにはどうしたらよいのでしょうか。そのためにこそ私たちは、外に立つのではなく、中に入らなければならないのです。それは、主イエスのもとに集い、そのみ言葉を聞くということです。主イエスは、「わたしの天の父の御心を行う人が」と言われました。神は、主イエスの天の父であられます。神の御心は、その独り子であられる主イエスによってこそ示されているのです。ですから私たちはいつも、この主イエスのもとに集い、そのみ言葉を聞かなければなりません。しかもできるだけ主イエスの足もと近くに、距離を置かずに、ぴったりと着いて、主イエスの語られることを聞き、なされるみ業を見ることが大事なのです。それは何よりも先ず、礼拝に集い、み言葉聞くこと、それに導かれて、聖書を読み、祈ることです。そのようにしていくことによってこそ、私たちは、神の御心が何であるのか、何をすることが本当に神の御心にかなうことなのかを正しく知ることができるのです。
手を差し伸べて
主イエスはそのように、ご自分のもとに集い、その教えを聞き、み業を間近で見ている弟子たちこそ、ご自分の本当の家族なのだと言われました。しかしここに語られているのはそれだけではありません。49節に、主イエスは弟子たちの方を指して、「見なさい。ここにわたしの母、わたしの兄弟がいる」と言われたとありますが、この「指して」という言葉は、ただ「指差して」ということではありません。聖書協会共同訳ではここは「弟子たちに手を差し伸べて」となっています。こちらの訳の方が原文のニュアンスを伝えています。主イエスは弟子たちに手を差し伸べて、「ここにわたしの家族がいる」と言われたのです。その「手を差し伸べる」というのは、8章3節で、主イエスが重い皮膚病にかかっている人に手を差し伸べてその人に触れ、癒して下さった時のしぐさです。また14章31節には、溺れそうになったペトロに主イエスが手を差し伸べて捕まえ、助けて下さったことが語られています。つまり手を差し伸べるという言葉は、主イエスが救って下さることを意味しているのです。主イエスはそのように弟子たちの方に手を差し伸べて、「ここに私の家族がいる」と言って下さったのです。つまり私たちがみもとに集ってみ言葉を聞く者となることによって主イエスの家族になる、と言うよりも、主イエスが手を差し伸べて私たちを救い、守り、支え、導き、はぐくんで下さることによって、私たちは主イエスの本当の家族として生きることができるのです。
あなたも主イエスの家族になることができる
この主イエスのまことの家族に、誰でもなることができます。難しい条件は何もありません。外に立って主イエスと距離を置こうとすることをやめて、その懐に飛び込み、み言葉を常に聞き続ける者となればよいのです。それが、洗礼を受けて教会に加えられることです。洗礼を志願した方の準備会において必ずお話しすることの一つに、これまではあなたは教会のお客様でした。しかし洗礼を受けることによって、今度はお客様から、家の者、家族の一員になるのです、ということがあります。教会は、お客様を歓迎し、大事にします。できるだけ快適に過ごしていただくためにおもてなしをするのです。けれどもお客様は家族とは違います。洗礼を受けることによって、その人はお客様から家族になります。家族になれば、それなりの務めや役割も生じます。もてなされる側から、もてなす側に変わるのです。その家の歩みに、責任をもって関わる者になります。しかしそれよりも何よりも、このことによって私たちは、主イエスのまことの家族となるのです。そして、主イエスが差し伸べて下さっているみ手に守られ、養われ、はぐくまれる者とされるのです。洗礼を受けた者が聖餐にあずかる、というのはそういうことを表しているのです。
血の繋がりを乗り越えて
主イエスの母と兄弟たちは、外に立つ者となってしまったことによって、主イエスに見捨てられてしまったわけではありません。彼らも後に、主イエスのまことの家族である教会の一員となりました。本日の箇所は、そこに至るまでの間に、彼らが、血の繋がりによる主イエスとの関係を乗り越えて、信仰における関係を結んでいかなければならなかったことを語っていると言うことができるでしょう。母マリアも、主イエスを生んだ、という肉体的な繋がりだけによって主イエスのまことの家族となったわけではないのです。彼女も、外に立つ者から、主イエスのもとに集い、そのみ言葉を聞き、そのみ手の内に置かれる者となることによって、主イエスの本当の母となることができたのです。
主イエスが私たちの救いのために苦しみを受け、十字架にかかって死んで下さったことを覚えるこのレント、受難節の時、自分が変えられることを拒んで主イエスから距離を置こうとする思いを乗り越えて、主イエスのもとに集う信仰を養われていきたいと思います。主イエスはみもとに集う私たちに手を差し伸べて、「見なさい。ここにわたしの母、わたしの兄弟がいる」と語りかけて下さっているのです。