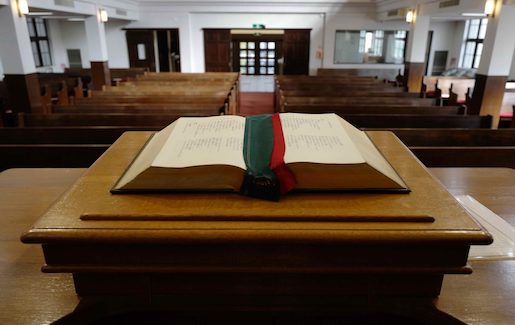説 教 「今日わたしと一緒に楽園に」 副牧師 川嶋章弘
旧 約 詩編第106編1-5節
新 約 ルカによる福音書第23章39-43節
十字架に架けられた二人の犯罪人
ルカによる福音書が語る主イエスの十字架の場面を読み進めています。前回は23章32節から38節を読みました。そこではまさに主イエスが十字架に架けられたことが語られていました。また主イエスのほかにも、二人の犯罪人が主イエスの十字架を中央にして、その右と左で十字架に架けられました。そのとき主イエスは「父よ、彼らをお赦しください。自分が何をしているのか知らないのです」、と祈られたのです。しかし前回の場面では、主イエスと二人の犯罪人について、それ以上のことは語られていませんでした。むしろ主イエスの十字架に立ち会った人たちの姿、「メシアなら、ユダヤ人の王なら自分を救ってみろ」とあざ笑い、侮辱する民衆や議員や兵士たちの姿が語られていたのです。本日の箇所では、再び主イエスと一緒に十字架に架けられた二人の犯罪人へと視線が向けられています。
ところで、この二人の犯罪人は、何故、十字架刑に処せられたのでしょうか。ルカ福音書では「犯罪人」と言われているだけで、何も記されていません。しかしマタイやマルコ福音書では「強盗」と言われています。そしてこの「強盗」という言葉は、単に他人の物を盗む者というより、むしろ反乱を起こす者、革命家を意味します。ですからこの二人の犯罪人も反乱者ないし革命家であったのかもしれません。主イエスの代わりに釈放されたあのバラバは、23章19節で、「都に起こった暴動と殺人のかどで投獄されていた」と言われていました。おそらくバラバはローマ帝国の支配に抵抗して、エルサレムで暴動を起こし、人を殺してしまったために投獄されていたのでしょう。同じようにこの二人の犯罪人もローマ帝国の支配に抵抗して、暴動ないし反乱を起こしたけれど、しかしあえなく逮捕されて投獄され、十字架刑に処せられることになった、ということなのかもしれません。
主イエスをののしる犯罪人
十字架に架けられていた犯罪人の一人が、主イエスを罵ってこのように言いました。「お前はメシアではないか。自分自身と我々を救ってみろ」。直前の場面で、主イエスの十字架のもとで、議員や兵士たちが主イエスに向かって、「お前が救い主なら、お前がユダヤ人の王なら、自分を救ってみろ」とあざ笑い、侮辱していました。この犯罪人も同じことを言ったことになります。十字架のもとには民衆もいました。彼らは数日前まで主イエスが自分たちをローマ帝国の支配から救い出してくれるメシア、救い主であると期待していました。しかしその期待が外れたので、主イエスを「十字架につけろ」と叫んだのです。十字架上の主イエスを見つめる民衆は、自分たちの期待に応えてくれなかった主イエスに対して、議員たちと同じように、「救い主なら、自分を救ってみろ」と、心の中であざ笑っていたのだと思います。しかしこの犯罪人は、主イエスが救い主であると期待していたわけではないでしょう。主イエスのことを知っていたわけでもないかもしれません。まして主イエスが十字架に架けられている自分たちを救うことができる、と期待していたわけではありません。つまり言葉は同じでも、その心にある思いは議員や兵士や民衆たちと同じではなかったのです。この犯罪人がローマ帝国の支配に抵抗して、反乱を起こしたのであれば、ローマ帝国の支配からの解放を主イエスに期待していたはずがありません。自分自身の手でそれを成し遂げようとしていたのです。彼は自分が正しいことをしている、正義を行っている、と思っていたはずです。それなのに反乱は失敗して、逮捕され、十字架刑に処せられることになったのです。ですから彼は十字架上で罪の意識を感じていたのではなく、むしろ正しいことを行ったにもかかわらず、自分が不当にも十字架刑で罰せられていると感じていたのです。このように彼は、自分の期待が裏切られたから主イエスを罵っているのではありません。十字架上の主イエスをあざ笑い、侮辱する議員や兵士たちの言葉を聞いて、それを真似したに過ぎないのです。自分が不当に罰せられていることへの怒り、その苦しみに対する憤り、自分の目的を達成できなかったことへの恨み、ひいては自分の人生が思い通りにいかなかったことへの不満を主イエスにぶつけて、「お前はメシアではないか。自分自身と我々を救ってみろ」と罵ったのです。「ののしった」という言葉は、原文では「ののしり続ける」というニュアンスの言葉です。彼は腹立ち紛れに、自分の怒りや恨みや不満を主イエスにぶつけ続けていたのです。
自分の正しさに固執する
私たちも同じようなことをしてしまうことがあります。私たちは国家の支配に対して反乱を起こしたり、革命を起こしたりすることはないでしょう。しかし自分が志した目標や夢が叶わなかったり、自分の人生が思い通りにいかなかったりすることがあります。そのとき私たちは、自分が不当な扱いを受けているように思うのです。特に自分ではどうすることもできない理由によって苦しまなくてはならないとき、自分の目標や夢を諦めざるを得ないとき、思い描いていた自分の人生が大きく変わってしまうとき、不当な扱いを受けていると思わずにはいられないのです。そのようなとき私たちはその怒り、恨み、不満を主イエスにぶつけてしまうことがある。「あなたは救い主ではないか。なぜ私を救ってくれないのか。なぜ私がこんな不当な目に合わなければならないのか」と罵ってしまうことがあるのです。
さらに、自分が不当な扱いを受けているという思いの根本にあるのは、自分は正しいことをしているという思いであることも、この犯罪人の姿から示されます。自分は正しいことを行っているのに、正しいことを言っているのに、それが拒まれたり、否定されたりするとき、私たちは不当な扱いを受けていると強く感じるのです。そのようなとき私たちはとても攻撃的になります。この犯罪人は、主イエスへの誹謗中傷を聞いて、それに同調して、自分の不満を晴らそうとしました。私たちも同じようなことをしてしまうことがあるし、私たちの身の回りでも同じようなことが起こっています。たとえば自分の不満のはけ口として、大して吟味せずにSNSで氾濫している誹謗中傷に同調するということがあります。私たちは、自分は正しい、という思いからなかなか自由になれません。自分が悪かった、申し訳なかったと思うときですら、どこかで自分にも正しさはあった、と思ってしまうのです。十字架刑に処せられていても、なお罪の意識を感じることなく、自分の正しさに固執し、自分は不当に罰を受けていると感じている犯罪人の姿は、どのような状況にあっても自分の正しさを主張してしまう私たちの姿、自分の罪を本当には認めることができない私たちの姿を示しているのです。
神を恐れる犯罪人
この犯罪人が主イエスを罵っているのを聞いて、もう一人の犯罪人は、このように言いました。「お前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに。我々は、自分のやったことの報いを受けているのだから、当然だ。しかし、この方は何も悪いことをしていない」。二人の犯罪人は、同じようにローマ帝国の支配に抵抗して、反乱を起こし、しかし逮捕されて、十字架刑に処せられたのだと思います。もしかたしたら二人は仲間であったのかもしれません。そのように想像することも許されると思います。しかし一人は十字架刑が不当な罰だと思ったのに、もう一人は十字架刑が当然の報いだと思ったのです。この二人の違いは、どこから生じたのでしょうか。一人は反省しなかったけれど、もう一人は反省した、ということなのでしょうか。もう一人のほうは、ローマ帝国の支配に抵抗して反乱を起こしたのはやっぱり間違いだったと考え直し、だから十字架刑は当然の報いであり、自分のやったことの報いを受けている、と思ったのでしょうか。そうではないと思います。彼も自分は正しいことを行った、正義を行った、と思っていたはずです。不当な刑罰を受けていると感じていたはずです。ですから彼はローマ帝国の法律によって、自分の犯罪に対する正当な刑罰を受けていると感じていたわけではないのです。この点で、二人の犯罪人に違いはないと思います。しかし彼はこう言います。「お前は神をも恐れないのか」。「神様を恐れていないのか」と言うのです。それは裏返せば、彼が神様を恐れていた、ということにほかなりません。彼は十字架上で、自分は神様の怒りを受けている、神様の裁きを受けていると感じていたのです。だから彼は十字架刑が自分のやったことの当然の報いだと言いました。反乱を起こしたのは無謀だったし、間違っていた、だから十字架刑に処せられても仕方がない、当然の報いだと思ったのではなく、神様を恐れたから、神様の怒りと裁きを受けていると感じたから、十字架刑は当然の報いだと言ったのです。
なぜ神を恐れたのか
なぜ彼は神様を恐れたのでしょうか。不当な扱いを受け、自分の夢が叶わず、人生が思い通りにいかないことへの怒りや恨みや不満をぶつけ続けるのではなく、自分の正しさを主張し続けるのでもなく、むしろ自分の正しさを打ち砕かれて神様を恐れたのは、なぜなのでしょうか。彼は「お前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに」と言いました。「同じ刑罰を受けているのに」というのは、二人の犯罪人が同じ刑罰を受けているということではありません。中央の主イエスが、左右の二人の犯罪人と同じ刑罰を受けている、ということです。「何も悪いことをしていない」主イエスが、自分たちと同じ刑罰を受けている、神様の怒りと裁きを受けて十字架に架けられている。だから彼は神様を恐れたのです。「何も悪いことをしていない」というのは、もちろんローマの法律に照らして無罪であるということを言いたいわけではありません。それは総督ピラトにとっては問題であっても、この犯罪人にとっては重要なことではありません。彼自身、自分がローマの法律に照らして有罪であることを気にしていませんでした。そうではなく彼は、主イエスが神様の怒りと裁きを受けなくてはならない罪を何一つ犯していない、と言っているのです。そのことに気づかされたとき彼は、同時に自分が神様の怒りと裁きを受けなくてはならない、とも気づかされました。彼は正しいことをしている、正義を行っていると思っていました。ローマの支配のもとで苦しんでいる人たちを解放したい、と思っていたのかもしれません。しかしそうであったとしても、彼は自分が神様の怒りと裁きを受けなくてはならない、と認めないわけにはいきませんでした。反乱を起こしたからではありません。そうではなく自分が根本的に神様の正しさよりも自分の正しさに固執していることに、神様のみ心を求めるよりも、不当な扱いを受けているという思いにとらわれていることに、つまり神様に背いて生きていることに気づかされたからです。自分は神様の怒りと裁きを受けなくてはならない者であり、神様の前で罪人である、と気づかされたのです。
罪のない神の子との出会い
この犯罪人は、十字架に架けられる前から主イエスを知っていたわけではないと思います。おそらくこのとき初めて主イエスに出会ったのではないでしょうか。では彼はどのようにして主イエスが「何も悪いことをしていない」と知ったのでしょうか。それは、まさに十字架上での主イエスとの出会いを通してです。十字架上の主イエスのお姿を通して、なによりもあの主イエスの祈り、「父よ、彼らをお赦しください。自分が何をしているのか知らないのです」というあの主イエスの祈りによって、主イエスが神の子であり、「何も悪いことをしていない」にもかかわらず、自分たちと一緒に神様に裁かれようとしていることを知ったのです。彼は十字架に架けられたとき、主イエスの祈りを聞いたに違いありません。「父よ」と神様に呼びかけ、自分を十字架に架けた者たちのために、自分をあざ笑い、侮辱する者たちのために、「彼らをお赦しください」と執り成し祈る主イエスのお姿は、まさに何一つ罪を犯していない神の子のお姿であったのです。彼は十字架上で罪のない神の子と出会い、それ故まことの神と出会ったのです。まことの神との出会いが、神様への恐れを生じさせました。神様と出会い、神様を恐れる中で、自分の正しさを打ち砕かれて、自分が神様の怒りと裁きを受けなくてはならない者であることに、神様の前で罪人であることに気づかされたのです。
私たちは十字架上で主イエスと出会うわけではありません。しかし私たちも礼拝で語られるみ言葉によって主イエスと出会います。十字架上で、耐え難い苦しみを味わいながら、しかし「父よ」と神様に呼びかけ、自分を十字架に架けた者のために、自分をあざ笑い、侮辱する者のために、いえ、ほかならぬ私たちのために執り成し祈る主イエスと出会うのです。罪のない神の子イエスとの出会いが、私たちに神様への恐れを生じさせ、その恐れの中で、私たちは自分の正しさを打ち砕かれ、自分が罪人であることに気づかされます。どこまでも頑なに自分の正しさを主張してしまう自分の罪に、不当な扱いを受けているという思いにとらわれて怒りや恨みや不満に駆られてしまう自分の罪に気づかされるのです。
悔い改めへ導かれて
罪のない神の子との出会いによって自分の罪に気づかされることを通して、この犯罪人は悔い改めへと導かれました。悔い改めとは、自分は間違っていた、これからは気をつけようと反省することではありません。反省して何とかなるなら、主イエスが十字架に架かる必要はありませんでした。反省は、まだ自分自身を見つめています。自分自身の中に可能性を見ているのです。しかし自分自身の中に、この犯罪人が、そして私たちが、自分の正しさを頑なに主張してしまうことから解放される可能性はまったくありません。自分自身を見つめているうちは、その可能性はないのです。悔い改めるとは、自分自身を見つめるのをやめて、神様を見つめることです。神様からそっぽを向いていたのに、神様のほうに向き直ることなのです。
わたしを思い出してください
悔い改めて、神様の方に向き直ったから、この犯罪人は主イエスにこのように願うことができました。「イエスよ、あなたの御国においでになるときには、わたしを思い出してください」。共に読まれた旧約聖書詩編106編4節にはこのようにありました。「主よ、あなたが民を喜び迎えられるとき わたしに御心を留めてください。御救いによってわたしに報いてください」。この「わたしに御心を留めてください」が、「わたしを思い出してください」と同じ表現です。つまり「わたしを思い出してください」とは、「私に御心を留めて、救いにあずからせてください」ということなのです。
あなたが来てくださるときに
この「イエスよ、あなたの御国においでになるときには、わたしを思い出してください」は、印象深い言葉です。しかしこの言葉は、主イエスが御国に行くときに、私を思い出して、救いにあずからせてください、と言っているように思えます。しかし聖書は、基本的に主イエスが御国に行くという語り方はしていません。聖書協会共同訳を見るとこの一文に注が付いていて、別の写本の読み方がこのように記されています。「イエスよ、あなたがご支配のうちに来られるときには、私を思い出してください」。聖書全体が告げているのは、むしろこちらのほうです。主イエスが御国に行くことが私たちの救いなのではなく、主イエスが御国と共に、そのご支配と共に、そのご支配のうちに来てくださることが、私たちの救いなのです。マタイ福音書16章28節でも主イエスはこのように言われています。「はっきり言っておく。ここに一緒にいる人々の中には、人の子がその国と共に来るのを見るまでは、決して死なない者がいる」。人の子が、つまり主イエスが「その国と共に来る」とき、私たちは救いの完成にあずかります。十字架で死なれ、復活され、天に昇られた主イエス・キリストが、終わりの日に再びこの地上に来てくださり、そのご支配をこの地上に完成させ、私たちを救いの完成にあずからせてくださるのです。この犯罪人は十字架の激しい苦しみの中で、何一つ罪を犯さなかった神の子イエスが十字架に架けられ、自分の苦しみを共に味わってくださっているのを目の当たりにして、悔い改めて、神様の方に向き直りました。そして苦しみに対する怒りをぶつけるのではなく、自分の人生が思い通りにいかなかったことへの不満をぶつけるのでもなく、ただ主イエスに、「終わりの日に、あなたが来てくださり、そのご支配を完成させるときに、私を思い出して、その救いの完成にあずからせてください」と願ったのです。私たちもそのように願うことができます。十字架に架けられることはなくても、死を迎えるときに、自分の夢が破れたときに、自分の人生が思い通りにいかないときに、あらゆる苦しみの中で、その苦しみを共に担ってくださる罪のない神の子イエスに、「イエス様、あなたが来てくださるときに、私を思い出して、救いの完成にあずからせてください」と祈ることができるのです。
主イエスが一緒にいてくださる
そのように祈るこの犯罪人とそして私たちに、主イエスは宣言されます。「はっきり言っておくが、あなたは今日わたしと一緒に楽園にいる」。この主イエスの宣言も、「あなたは今日わたしと一緒に天国にいる」というように読むべきではありません。「死んだら天国に行く」とか「死んだら天国という楽園にいる」というのは、聖書が語っている救い、福音ではありません。聖書が語っている救いは、福音は、主イエスが終わりの日に再び来てくださるとき、主イエスと結ばれて死んだ者たちが、眠りに就いた者たちが復活と永遠の命にあずかり、主イエスといつまでも一緒にいるようになることだからです。ですから「楽園」はどこにあるのか、と考えても意味はありません。「楽園」は場所ではありません。むしろ「関係」と言ったほうがよい。主イエスは「わたしと一緒に楽園にいる」と宣言されました。主イエスが一緒にいてくださるところ、そこが楽園です。主イエスが私たちと一緒にいてくださるなら、そこが楽園、そこがパラダイスであり、そこにまことの安心、まことの平安があるのです。
今日わたしと一緒に楽園に
主イエスは「今日わたしと一緒に楽園にいる」と、「今日」と言われました。確かに終わりの日に、私たちは復活と永遠の命にあずかり、主イエスといつまでも一緒にいるようになります。そこに私たちの救いの完成があります。しかしそれは、終わりの日まで、主イエスが私たちと一緒にいてくださらない、ということでは決してありません。主イエスは「今日」と言われている。死を迎えようとしている「今日」です。死を迎えるときも、そして死んでからも、主イエスはこの犯罪人と、そして私たちと一緒にいてくださる。だから私たちは、まことの平安の中で死を迎えることができるのです。罪のないまことの神の子イエスとの出会いを与えられ、自分の正しさを打ち砕かれ、自分を見つめて生きるのではなく、神様を見つめて生きる私たちに、この約束が与えられているのです。
詩編106編4節の「わたしに御心を留めてください」は、ユダヤ人のお墓の墓誌によく刻まれているそうです。死んで、時が経てば、自分のことを覚えている人もいなくなる。しかし神様だけは自分を覚えていて、自分に御心を留めてください、という祈りが刻まれているのです。私たちが本当に死ぬのは、死んだときではなく、誰からも忘れられたときだ、と言われることがあります。そのことを私たちは恐れもします。しかし主イエスは、「私は覚えている、決して忘れない」と約束してくださっているのです。終わりの日になって、思い出すというのではありません。死を迎えるときも、死んでからも、主イエスは私たちを覚えていてくださり、心に留めていてくださり、一緒にいてくださるのです。私たちが激しい苦しみの中で、絶望の中で、すべての人に見捨てられたように思うときですら、主イエスは私たちを心に留めていてくださり、一緒にいてくださり、そして宣言してくださるのです。「はっきり言っておくが、あなたは今日わたしと一緒に楽園にいる」。