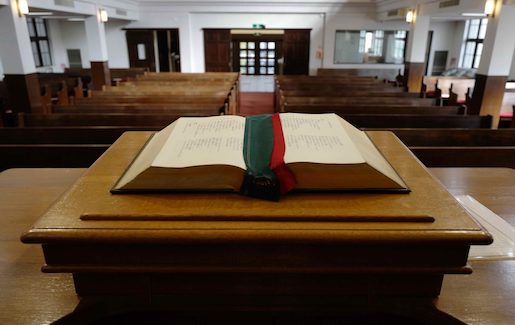説 教 「自分と子供たちのために泣け」 副牧師 川嶋章弘
旧 約 ホセア書第10章1-10節
新 約 ルカによる福音書第23章26-31節
刑場へ連れて行かれる場面
前回読み進めたように総督ピラトは、主イエスが「死刑に当たるようなことは何もしていない」のだから、主イエスを釈放すべきだと主張しました。しかし「十字架につけろ、十字架につけろ」という人々の叫び声はますます強くなり、ついに人々の声がピラトの声にまさり、ピラトの声、ピラトの主張を飲み込んだのです。ピラトは人々の要求を受け入れることにしました。このようにして主イエスは十字架刑に処せられることになったのです。本日の箇所は、その主イエスが十字架刑の執行される刑場へ、ほかの福音書では「ゴルゴタ」と言われている場所へ連れて行かれる場面です。しかし十字架刑は刑場に着いてから始まるのではなく、刑場に向かうところから始まります。十字架につけられる者は、自分がつけられる十字架を背負って刑場まで行くことになっていたからです。ですから本日の箇所からすでに主イエスの十字架刑の場面が始まっているのです。
キレネ人シモン
主イエスは十字架を背負わされ刑場へと歩まれました。しかしその途中で、キレネ人シモンが代わりにその十字架を背負うことになります。主イエスがもはや十字架を背負えないほどに弱っていたからです。マルコ福音書やマタイ福音書によれば、ピラトが主イエスを兵士に渡すと、兵士は主イエスを鞭で打ちました。先ほど十字架を背負って刑場に向かうところから十字架刑は始まると申しましたが、より正確に言えば、この鞭打ちから十字架刑は始まります。そしてこの鞭打ちは、それだけで死んでしまうこともあるほど激しいものであったらしいのです。すでに主イエスは逮捕された後、大祭司の家で見張りの者たちから殴られていました(22章63節)。それに加えて死んでしまうこともあるほどの厳しい鞭打ちを受けられて、主イエスは十字架を背負えないほどに衰弱しておられたのです。そこで兵士たちはキレネ人シモンを捕まえて、主イエスの十字架を背負わせ、主イエスの後ろから運ばせたのです。
このキレネ人シモンがどのような人物なのかはよく分かりません。キレネというのは、現在のリビア(北アフリカ、エジプトの西)のことです。紀元前6世紀にイスラエル王国が滅亡すると、ユダヤ人は各地に離散しましたが、キレネにもユダヤ人の共同体が出来たようです。シモンは過越祭なのでキレネからエルサレムに巡礼に来ていたのかもしれませんし、キレネ出身だけどエルサレムで暮らしていたのかもしれません。「田舎から出て来た」というのは、キレネの田舎からともユダヤの田舎からとも読めます。興味深いことに聖書協会共同訳では「畑から帰って来る」と訳されています。原文の言葉が「田舎」とも「畑」とも訳せるからです。「畑から帰って来る」と理解するなら、シモンはエルサレムで暮らしていたということになるでしょう。いずれにしても大切なことは、シモンにとって思ってもみなかったことが起こったということです。巡礼でエルサレムに来ていたときに、あるいは畑から帰って来たときに、たまたま主イエスが刑場に引かれていくのに出会し、何の気なしにその様子を眺めていたら、突然兵士たちに捕まって、主イエスの代わりに重い十字架を背負わされることになったのです。シモンにとっては、とんでもない災難でしかありません。しかしルカ福音書は、このシモンの姿を通して主イエスの弟子の姿を、主イエスの弟子とはどのように生きることなのかを伝えようとしています。この福音書の9章23節で主イエスは弟子たちに、「わたしについて来たい者は、自分を捨て、日々、自分の十字架を背負って、わたしに従いなさい」と言われていました。また14章27節でも「自分の十字架を背負ってついて来る者でなければ、だれであれ、わたしの弟子ではありえない」と言われていました。ですから主イエスの十字架を背負って歩んだシモンの姿に、主イエスについて行く者の姿が、主イエスの弟子の姿が重ね合わされているのです。キレネ人シモンがどのような人物であるか分からないからこそ、私たちは自分自身をシモンに重ねることができます。シモンの姿は主イエスの弟子である私たち一人ひとりの姿なのです。
背負いたくない十字架を背負わされる
先ほど見たようにシモンは、自分から積極的に主イエスの十字架を背負ったわけではありません。彼は主イエスに会ったこともなかったはずです。毎年のエルサレム巡礼の最中に、あるいは日々の畑仕事の帰りに、つまりいつもと変わらない日常の中で、突然、十字架を背負った主イエスと出会い、主イエスの代わりにその十字架を背負うことになったのです。弱っている主イエスに十字架を背負わせるのはかわいそうだとか、とんでもないことだとか、そのように思い、義憤にかられて代わりに背負ったのではありません。突然、ローマの兵士たちに捕まって背負わされたのです。兵士たちに歯向かって、彼らを怒らせたら何をされるか分からない。その恐れからしぶしぶ背負ったのです。何で自分だけがこんな目に遭わなくてはいけないんだ、まったく自分はついていない、とぶつくさ文句を言いながら、主イエスの後ろから、
主イエスの十字架を背負ってついて行ったのです。
私たちもいつもと変わらない日常の中で、突然、主イエスと出会うのではないでしょうか。正確に言えば、いつもと変わらない日常を生きている私たちに、主イエスが出会ってくださるのです。しかし私たちは主イエスと出会っても、自分から積極的に十字架を背負って歩もう、つまり重荷を背負って歩もう、と決意するわけではないでしょう。むしろ私たちはシモンと同じように、主イエスと出会うことによって背負いたくない十字架を背負わされることがあるのです。積極的な理由からではなく、しぶしぶ仕方がないから重荷を背負うということがある。たとえば選ばれてしまったからとか、ほかに担う人がいないからとか、そのような理由で重荷を背負うことがあるのです。何で自分だけがこんな目に遭わなくてはいけないんだ、こんな重荷を、こんな十字架を自分が背負えるはずがない、と文句を言いながら、不安になりながら足を引きずるようにして歩んでいきます。しかしそのような歩みが、自分の十字架を背負って主イエスについて行く歩み、主イエスの弟子として生きる歩みなのです。
民衆
さて、この場面に登場するのはキレネ人シモンだけではありません。27節にこのようにあります。「民衆と嘆き悲しむ婦人たちが大きな群れを成して、イエスに従った」。シモンだけでなく、大勢の民衆と嘆き悲しむ女性たちも主イエスの後からついて行きました。「民衆」というのは、13節の「祭司長たちと議員たちと民衆」の「民衆」です。この民衆が祭司長や議員たちと共に「十字架につけろ、十字架につけろ」と叫び続け、主イエスを十字架につけるよう総督に要求し続けたのでした。そしてついにはその声がまさり、総督は民衆の要求を受け入れたのです。そのようにして主イエスを十字架に追いやった民衆が、自分たちの要求した十字架刑を見届けるために、刑場に引かれていく主イエスについて行ったのです。
泣き女
民衆のほかにも、嘆き悲しむ女性たちがいました。この女性たちは誰なのか、そして何故泣いているのかについては議論があります。当時は、葬式で仕事として泣く、「泣き女」と呼ばれる女性がいたようです。主イエスはまだ死なれたわけではありませんが、すでに十字架刑が決まり、刑場へと引いて行かれる途上にあって、あたかも主イエスが死んで、その葬式であるかのように、泣き女としての役割を担う女性たちがついて行ったのかもしれません。そうであれば、この女性たちはキレネ人シモンがそうであったように、自分たちから積極的に主イエスについて行ったというより、仕事として義務感で仕方なくついて行ったのです。彼女たちも主イエスに会ったことはなかったはずですが、しかし主イエスのために儀礼的であったとしても嘆き悲しみ、涙を流したのです。
ガリラヤから従って来た女性たち
この女性たちは「泣き女」ではなかったと考える人たちもいます。ある人たちは、この女性たちがガリラヤから主イエスに従って来た女性たちであったと考えます。49節に「ガリラヤから従って来た婦人たちとは遠くに立って」とありますが、この「ガリラヤから従って来た婦人たち」が、刑場に引かれていく主イエスについて行ったと考えるのです。そうであればこの女性たちは主イエスの弟子であり、ガリラヤからエルサレムまでと同じように、刑場への道のりも主イエスの弟子として主イエスに従おうとしたのです。自分たちの先生である主イエスが十字架につけられる悲しみ、主イエスと別れなければならない寂しさ、そして十字架を背負えないほどに弱っている主イエスへの同情の念を抱いて、彼女たちは嘆き悲しみ、涙を流したのです。
エルサレムの娘たち
また別の人たちは、この女性たちはガリラヤから主イエスに従って来た女性たちとは異なる、エルサレムの女性たちであると考えます。この後、主イエスがこの女性たちに「エルサレムの娘たち」と呼びかけておられるからです。そうであればこの女性たちは、主イエスの弟子として主イエスについて行ったのではありません。だからといって、「泣き女」のように義務感でついて行ったのでもありません。主イエスは、エルサレムで話題の人であったはずです。今、話題の主イエスが十字架につけられるのを見てみようという興味本位でついて行ったのではないでしょうか。しかし主イエスの後ろからついて行く中で、十字架を背負えないほどに弱っているにもかかわらず、刑場へと歩まれる主イエスを見て、またその主イエスがこれから十字架につけられることを思って、嘆き悲しんだのではないでしょうか。もともとは興味本位でついて行ったとしても、主イエスのお姿を見て、涙を禁じ得なかったのです。
このように嘆き悲しむ女性たちは、「泣き女」なのかもしれないし、ガリラヤから従って来た女性たちなのかもしれないし、エルサレムの女性たちなのかもしれません。どれか一つに決めるのは難しいようにも思えます。いえ、どれか一つに決めなくて良いのではないでしょうか。私たちはこの嘆き悲しむ女性たちの姿に、「泣き女」の姿を、ガリラヤから従って来た女性たちの姿を、エルサレムの女性たちの姿を見るのです。そしてそのことを通して私たちが受けとめるべきことがあるのです。
泣き方が間違っている
そのことを受けとめる前に、主イエスの言葉に目を向けたいと思います。主イエスはこれまでずっと沈黙されていました。ピラトの尋問に一言お答えになったほかは、ヘロデが色々と尋問しても、人々が「十字架につけろ」と叫んでも沈黙を貫かれたのです。その主イエスが、自分の後からついて来る嘆き悲しむ女性たちの方を向いて、長い沈黙を破って言葉を語りかけられました。そしてこの主イエスの言葉は、主イエスが十字架につけられる前の最後の言葉でもあります。この後、主イエスは十字架上で幾つかの言葉を語られますが、十字架につけられる前の言葉としては最後の言葉なのです。私たちはそのような言葉としてこの主イエスの言葉を大切に聞いていきたいのです。主イエスの言葉は28節から31節まで続く長い言葉ですし、分かりにくいところもありますが、ここで主イエスが言わんとしていることは単純です。主イエスは28節でまず、「エルサレムの娘たち、わたしのために泣くな。むしろ、自分と自分の子供たちのために泣け」と言われています。それは要するに、「あなたたちの泣き方は間違っている」ということです。「あなたたちは私のために泣いているけれど、その泣き方は間違っている。私のためではなく、自分と自分の子供たちのために泣きなさい」と言われたのです。
神様の裁きを見つめよ
その理由、つまり主イエスのためではなく自分と子供たちのために泣く理由が、29節以下で語られています。29節では「人々が、『子を産めない女、産んだことのない胎、乳を飲ませたことのない乳房は幸いだ』と言う日が来る」と言われています。当時は、結婚した女性が子を産むことが幸いである、と考えられていたわけですが、その価値観が逆転して、結婚した女性が子を産まないことが幸いである、と言われる日が来る、と言われているのです。この福音書の21章23節では「それらの日には、身重の女と乳飲み子を持つ女は不幸だ」と言われていました。ここではそれを裏返して言い表しています。さらにそこでは、それらの日に「この地には大きな苦しみがあり、この民には神の怒りが下る」とも言われていました。ですから価値観が逆転して、結婚した女性が子を産まないことが幸いであると言われるようになる日とは、神様の怒りが下る日なのです。続く30節では「そのとき、人々は山に向かっては、『我々の上に崩れ落ちてくれ』と言い、丘に向かっては、『我々を覆ってくれ』と言い始める」と言われています。これは共に読まれた旧約聖書ホセア書10章8節の引用です。そこでは神様の裁き、神様の怒りが下る日が見つめられています。山が私たちの上に崩れ落ちてくれ、丘が私たちを覆ってくれというのは、山や丘が私たちを覆い隠すことで守ってほしい、ということではなく、山や丘が私たちの上に崩れ落ちて、私たちを押し潰してほしい、ということです。神様の裁きの日には、山や丘に押し潰されてあっという間に死んでしまいたい、と人々は叫ぶようになるのです。31節の「『生の木』さえこうされるのなら、『枯れた木』はいったいどうなるのだろうか」という言葉は、謎のような言葉です。おそらく「生の木」は主イエスを指し、「枯れた木」は私たちを指すのだと思います。「生の木」である主イエスがこのように苦しまれるのなら、「枯れた木」である私たちは神様の裁きの日に、どれほど苦しむだろうか、と言われているのです。自分と子供たちのために泣くのは、神様の裁きの日が来るからです。神様の裁きと、その裁きにおける苦しみ、あっという間に死んでしまいたいと叫ぶほどの大きな苦しみを見つめて、自分と子供たちのために泣きなさい、と言われているのです。神様の裁きの日が来るとは、第一には紀元70年にローマの軍隊によってエルサレムが完全に滅ぼされることを指しています。しかしそれだけではありません。それだけなら紀元2025年を生きる私たちには何の関係もないことになります。神様の裁きの日が来るとは、世の終わりに私たちが神様のみ前で自分の罪を裁かれるということです。その神様の裁きを見つめて、自分と子供たちのために泣け、と言われているのです。
キリスト者の人生は悔い改めの人生
それは、神様に裁かれるしかない自分の罪を見つめて、自分の罪を嘆き悲しみなさい、そして悔い改めなさい、ということです。主イエスは、ご自分の後ろからついて来る嘆き悲しむ女性たちに向かって、自分の罪を深く覚えて涙を流して悔い改めよ、と言われたのです。
この女性たちがガリラヤから主イエスに従って来た女性たちであるなら、主イエスはご自分の弟子たちに、キリスト者に、つまり私たちに語りかけています。主イエスに従って生きる者たちに、自分の罪を悔い改めよ、と言われているのです。ガリラヤから従って来た女性たちは、先生である主イエスが十字架につけられる悲しみ、主イエスと別れなければならない寂しさ、弱っている主イエスへの同情の念を抱いて、泣きました。しかしその泣き方は間違っています。同じように私たちが主イエスに従って行く中で、主イエスの十字架を見つめるとき、私たちは主イエスがかわいそうだとか、痛そうだとか、そのようなことを思って嘆き悲しむのではありません。そうではなく私たちの罪のために、救いにあずかってもなお日々罪を犯している私たちのために、主イエスが十字架に架かって死んでくださったことを見つめ、繰り返し自分の罪を示され、悔い改めるのです。私たちキリスト者の人生は、繰り返し主イエスの十字架を見つめ、自分の罪を覚え、涙を流して悔い改める歩みなのです。主イエスはガリラヤから従って来た女性たちに「自分と自分の子供たちのために泣きなさい」と語りかけることを通して、このキリスト者の歩みを示されたのです。
求道者への悔い改めの招き
この女性たちがエルサレムの女性たちであるならば、主イエスはご自分の弟子ではない人たちに、つまりまだキリスト者ではない人たちに、求道者に語りかけています。求道者に自分の罪を悔い改めよ、と語りかけているのです。さらにこの女性たちが「泣き女」であるならば、主イエスは義務感で、仕方なくご自分について来る者たちにも振り向いて目を留めてくださり、自分の罪を悔い改めよ、と語りかけているのです。この夕礼拝にも求道者の方が出席されます。そして誰もがかつては求道者でした。私たちはイエス・キリストに興味を持って、また教会や聖書に興味を持って教会の礼拝に出席する中で、あるいは学校の課題などで仕方なく、また友だちに誘われてしぶしぶ教会の礼拝に出席する中で、主イエスの十字架を知ります。鞭で打たれ十字架で死なれた主イエスに興味を持ち、同情することもあるでしょう。しかしそれが主イエスを信じることではありません。主イエスの十字架の死がほかならぬ自分のためであった、ほかならぬ自分の罪のためであったと受けとめ、自分の罪を悔い改め、洗礼を受けることが、主イエスを信じることなのです。主イエスはエルサレムの女性たちに「自分と自分の子供たちのために泣きなさい」と語りかけることを通して、まだキリスト者でない方々が悔い改めて主イエスを信じ、救いにあずかるよう招いておられるのです。
自分と子供たちのために泣け
まさにキレネ人シモンは、この招きに応えたのではないでしょうか。彼は背負いたくもない十字架を背負って、主イエスの後からついて行くことになりました。何で自分だけがこんな目に遭わなくてはいけないんだ、まったく自分はついていない、とぶつくさ文句を言いながら、十字架を背負って主イエスについて行ったのです。しかしその歩みの中で、十字架に向かわれる主イエスを後ろから見つめる中で、そして十字架で死なれる主イエスを見つめる中で、主イエスの十字架が「この私のためだった」「この私の罪を赦すためだった」と気づかされたのです。そして主イエスの復活と教会の誕生の後に、悔い改めて洗礼を受け、キリスト者となったのではないでしょうか。シモンがどのような人物なのかはよく分かりません。しかしその名前が残っていることが大切です。彼が後に初代の教会において、自分が主イエスの十字架を背負って主イエスの後からついて行く中で、自分の罪に気づかされ、悔い改めて洗礼を受けたことを証ししたから、その名前が残っているのです。そして彼はキリスト者になってからも、繰り返し主イエスの十字架を見つめ、主イエスが自分の罪のために十字架で死んでくださったことを見つめ、自分の罪を深く覚えて、涙を流して悔い改めつつ歩んだに違いないのです。主イエスに従って生きるとは、「自分と子供たちのために泣け」という主イエスの言葉を、十字架に架けられる前の最後の主イエスの言葉として繰り返し受けとめ、主イエスの十字架を見つめ、自分の罪を悔い改めて、神様のほうに向き直って生きていくことなのです。かつて主イエスはエルサレムに近づいたとき、エルサレムのために涙を流されました。エルサレムの滅亡を思って、先に泣かれたのは主イエスであったのです。その主イエスは、私たちが悔い改めて涙を流すのに先立って、私たちを憐れんで涙を流してくださり、どこまでも愛してくださり、私たちを救うために十字架で死んでくださいました。私たちに対する主イエスの愛の涙の中で、私たちは悔い改めの涙を流しつつ、主イエスに従って歩んで行くのです。
これから私たちは聖餐にあずかります。聖餐において私たちは、主イエスが私たちを愛して、私たちのために裂いてくださったその体と、流してくださったその血とにあずかります。私たちは「自分と子供たちのために泣け」という主イエスの言葉をしっかりと受けとめ、自分の罪を深く覚え、涙を流して悔い改めて、この聖餐にあずかるのです。