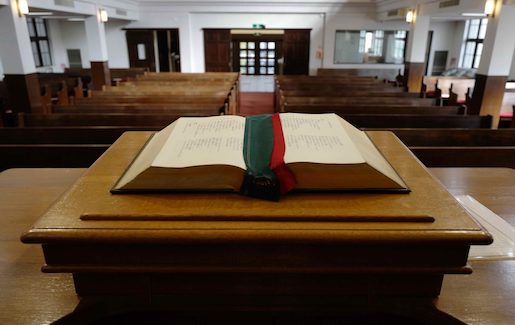説 教 「十字架につけて殺した」 副牧師 川嶋章弘
旧 約 ヨエル書第3章1-5節
新 約 使徒言行録第2章14-23節
聖霊が降り教会が誕生するための準備
使徒言行録を読み始めて、1章を読み終えました。前回、お話ししたように1章では、聖霊が降り教会が誕生するための準備が語られていました。その前半で、主イエスの昇天が語られていましたが、それは、神様側の準備であった、と言えます。主イエスが天に上げられることによって、天から主イエスは聖霊を送ってくださったのです。それに続く後半では、使徒たちの準備が語られていました。使徒たちの準備は、共に祈ることと、神様のみ心を求めることでした。使徒たちを中心に皆が「一つになって」、聖霊が降るのを求めて、心を合わせて熱心に祈り、またユダの代わりに新たな使徒を一人加えるために、神様のみ心を求めてくじを引いたのです。その結果、すでに決まっていた神様のみ心が、くじを引くことで示され、ユダが抜けて「十一人の使徒」であったのが、マティアを加えて「十二人の使徒」となりました。これで使徒たちの準備も完了した、と言えます。後は、聖霊が降るのを待つだけであったのです。
ペンテコステの出来事への反応
待ち望んでいた聖霊が降った出来事が、つまりペンテコステの出来事が、2章1~13節で語られています。前回1章を読み終えたので、本来なら本日は2章1~13節を読み進めるところですが、この箇所はすでに6月8日のペンテコステの夕礼拝で読みました。ですから本日はその先の14節以下を読み進めていきます。とはいえ14節以下も、同じ「五旬祭の日」の出来事、ペンテコステの出来事であり、1~13節の続きです。そこで簡単にペンテコステの出来事を振り返っておきます。使徒たちを中心として弟子たちが「一つになって集まっている」と、聖霊が降りました。主イエスが約束された通り、天に上げられた主イエスが聖霊を送ってくださったのです。弟子たちは聖霊に満たされ、聖霊に導かれて、「神の偉大な業」を語り始めました。しかも世界中の言葉で語り始めたのです。それは、弟子たちが突如として新たな言語を習得した奇跡というより、「神の偉大な業」があらゆる国の人に、すべての人に関わるということを見つめています。「五旬祭」はユダヤ人にとって重要な祭りでしたから、このときエルサレムには世界中からユダヤ人が巡礼に来ていました。彼らは自分たちが暮らしている国の言葉で、弟子たちが神の偉大な業を語っていることに驚きました。その彼らの反応が、12、13節でこのように語られていました。「人々は皆、驚き、とまどい、『いったい、これはどういうことなのか』と互いに言った。しかし、「あの人たちは、新しいぶどう酒に酔っているのだ」と言って、あざける者もいた」。「いったい、これはどういうことなのか」とは、直訳すれば、「これはどういう意味なのか」となります。人々の第一の反応は、今、見聞きしている出来事が何を意味しているのか知りたいというものであり、第二の反応は、「あの人たちは、新しいぶどう酒に酔っている」という嘲りであったのです。
ペトロの説教
人々のこの反応に対して、14節以下で、ペトロが語り始めます。聖書の小見出しには「ペトロの説教」とありますが、このペトロの説教は36節まで続く長い説教です。ペトロはまず、第二の反応に対して弁明しています。15節に、「今は朝の九時ですから、この人たちは、あなたがたが考えているように、酒に酔っているのではありません」とあります。ペトロは、「朝の九時」で、酒を飲むような時間ではないので、この人たちは酒に酔っている訳ではない、と言っているのです。では、いったい何が起こったのか。それを説明することが、第一の反応に対して弁明することでもあります。人々が、今、見聞きしている出来事、つまり聖霊が降り弟子たちが世界中の言葉で神の偉大な業を語り始めたことは何を意味しているのか。16節以下でペトロはこのことを語っているのです。
ヨエルの預言の成就
16節に「これこそ預言者ヨエルを通して言われていたことなのです」とあり、続く17~21節では、共に読まれたヨエル書3章1~5節が引用されています。ペトロは、人々が今、目の当たりにしている出来事は、預言者ヨエルの預言の成就であり、聖霊が弟子たちに注がれることによって、弟子たちが預言し始めた出来事だと語っているのです。「預言する」とは、ここでは未来について語ることではありません。「預言」は、「預かる」「言葉」と書きますから、弟子たちは聖霊によって神様から預かった言葉を語り始めたのです。その神様から預かった言葉こそが、「神の偉大な業」を語る言葉です。弟子たちの内側には、「神の偉大な業」を語る言葉はありませんでした。外から聖霊の働きを受けることによって、弟子たちは「神の偉大な業」を語る新しい言葉を与えられたのです。この「神の偉大な業」とは、独り子イエス・キリストが十字架で死なれ、復活されることによって、神様が私たちを救ってくださった、その偉大な救いのみ業です。弟子たちは聖霊によって神の偉大な救いのみ業を語る言葉を与えられて、それを語り始めたのです。
主の偉大な輝かしい日が来るまで
ペトロが引用しているヨエルの預言で注目すべきなのは、17節の「終わりの時に」という言葉です。共に読まれたヨエル書3章1節では、「その後」と言われていました。しかしペトロは、ペンテコステの出来事によって、「終わりの時」が始まったことを見つめています。しばしばペンテコステは「教会の誕生日」と言われます。教会の働きが始まった日です。しかし同時にペンテコステは、「終わりの時」が始まった日でもあるのです。「終わりの時」が始まった、と言われると、私たちはネガティブな印象、破滅に向かっていくような印象を持つかもしれません。私たちはしばしば「日本は終わりだ」とか「世界は終わりだ」とか思ったり言ったりします。混迷を深め、悪い方向に向かっているように、それこそ破滅に向かっているように思える、この世界の現実を目の当たりにするとき、そう思わずにはいられないのです。しかし「終わりの時」が始まっているとは、そういうことではありません。「終わりの時」が始まったとは、破滅に向かって歩み始めたのではなく、むしろ完成に向かって歩み始めた、ということです。主イエス・キリストの十字架と復活によって実現した救いの完成に向かって歩み始めた、ということなのです。その救いの完成の時が、20節では「主の偉大な輝かしい日」と言われています。そしてその救いの完成の時に、21節にあるように、「主の名を呼び求める者は皆、救われる」のです。つまりペトロは、ヨエルの預言が成就して、キリストによって実現した救いが完成に向かう時代が、「主の偉大な輝かしい日」に向かう時代が始まったことを見つめています。そしてその時代に「神の偉大な業」を宣べ伝えて、一人でも多くの人たちが主イエスの名を呼び求めるようになるために、弟子たちに「神の偉大な業」を語る言葉が聖霊によって与えられた、と語っているのです。ペンテコステの出来事はヨエルの預言の成就であり、「主の偉大な輝かしい日」が来るまで、「主の名を呼び求め」、主イエスを信じる人たちが一人でも多く起こされるために、神の偉大な業を、福音を宣べ伝える教会の働きが始まったことを意味しているのです。
神の民イスラエル
しかしペンテコステの出来事によってヨエルの預言が成就したことも、「主の偉大な輝かしい日」に向かう時代が始まったことも、主イエス・キリストの十字架の死と復活による救いを信じ、受け入れることなしに受けとめることはできません。だからペトロの説教は、22節以下で、主イエスの十字架の死と復活について語っています。本日は23節まで、つまり主イエスの十字架の死について語っているところを見ていきます。
説教の冒頭14節でペトロは、「ユダヤの方々、またエルサレムに住むすべての人たち」と呼びかけていましたが、22節では、「イスラエルの人たち、これから話すことを聞いてください」と呼びかけています。だからといって22節から、別の人たちに向かって語り始めたわけではなく、ユダヤ人に向かって語っています。しかしそのユダヤ人に向かって、「イスラエルの人たち」と呼びかけることには意味があります。ペトロはそのように呼びかけることで、その人たちに、自分たちが「神の民イスラエル」の一員であることを思い起こさせようとしたのです。神の民イスラエルは、神の恵みの契約に入れられ、メシア(救い主)が遣わされるという約束を与えられて歩んできました。ダビデ王朝が滅んでも、神様がイスラエルの民と結んだ契約は破棄されることなく、ダビデの子孫からメシアが生まれ、その救い主によって神の救いのみ業が実現するという約束を与えられていました。イスラエルの民は、この約束の実現を待ち望んで歩んできたのです。ペトロはこの説教を通してイエスこそがそのメシア(救い主)である、と語っていきます。この説教の終わり36節で、「だから、イスラエルの全家は、はっきり知らなくてはなりません。あなたがたが十字架につけて殺したイエスを、神は主とし、またメシアとなさったのです」と言われている通りです。
誰がイエスを殺したのか
しかしペトロは、いきなりイエスがメシアであるとは語らず、22節では、「ナザレの人イエスこそ、神から遣わされた方です」と語っています。このことを神様は、神の民イスラエルであるユダヤ人に、イエスを通して彼らの間で行われた「奇跡と、不思議な業と、しるしとによって」証明されました。だからペトロはユダヤ人に、「あなたがた自身が既に知っているとおりです」と語ります。彼らはすでに、ナザレの人イエスが神から遣わされた方であったと知っている、と言うのです。それは、彼らがイエスをメシア(救い主)だと本当に分かっていた、ということではないでしょう。そこまでは言っていない。だからペトロは慎重に「メシア」という言葉を使わず、「神から遣わされた方」と言っています。しかしユダヤ人は少なくとも、イエスが神から遣わされた方であると知っていたし、自分たちが待ち望んでいたメシアかもしれない、と思っていたのです。
その方が、十字架につけられて殺された。神から遣わされた方であり、自分たちが待ち望んでいたメシアかもしれない方が、ローマ帝国の最も残酷で屈辱的な処刑方法である十字架刑で殺されたのです。このイエスの十字架の死は、ユダヤ人たちの間で話題になっていたはずです。政治的な話題を好む人は、総督ピラトがイエスを殺したと考えたかもしれません。宗教的な話題を好む人は、祭司長たちの謀略がイエスを殺したと考えたかもしれません。あるいはセンセーショナルな話題を好む人は、弟子の一人であるユダの裏切りによってイエスが殺されたと考えたかもしれません。多くのユダヤ人が、イエスの十字架の死について話題にしていたに違いない。誰がイエスを殺したのか、と話していたに違いない。しかし誰も自分がイエスを殺したとは思っていなかったのです。
十字架につけて殺した
けれどもペトロは言います。「あなたがたは律法を知らない者たちの手を借りて、十字架につけて殺してしまったのです」。あなたがたがイエスを十字架につけて殺した、と言うのです。「律法を知らない者たちの手を借りて」というのは、異邦人の手を借りてということです。具体的にはローマ帝国の人たち、特に総督ピラトによって、ということでしょう。しかしその人たちに、イエスを十字架につけて殺した責任があるのではない。そうではなくその責任は、神の民イスラエルであるユダヤ人にある、とペトロは言います。「あなたがたは、神の民イスラエルであるにもかかわらず、神がその民に遣わした方を、自分たちが待ち望んでいた方を十字架につけて殺したのだ」と、ユダヤ人に突きつけたのです。
そのように語ることで、ペトロはユダヤ人にイエスを十字架につけて殺した責任を押しつけようとしているのでしょうか。自分には何の責任もないかのように、他人事のように、高みから、「あなたがたがイエスを十字架につけて殺したのだ」と語っているのでしょうか。そんなはずはありません。なぜならペトロもユダヤ人だからです。神の民イスラエルの一員だからです。しかもペトロは誰よりも主イエスの近くにいました。弟子として地上を歩まれた主イエスと共にいて、主イエスが行った奇跡や不思議な業を目の当たりにしていました。しかしそれにもかかわらず、彼は主イエスが捕らえられると、三度、主イエスを拒みました。自分はイエスなんて知らない、イエスとは関係ない、と言って、主イエスを拒み、裏切りました。神から遣わされた方、神の民イスラエルが待ち望んでいた方を拒み、裏切ったのです。そのペトロが、「あなたがたがイエスを十字架につけて殺した」と語るとき、自分に何の責任もないかのように、他人事のように語っているはずがありません。なによりも自分自身のこととして語っているのです。自分こそがイエスを十字架につけて殺したと弁えて語っているのです。
私たちは、イエスを十字架につけて殺した責任が、ペトロを含むユダヤ人にあるのなら、ユダヤ人ではない自分たちには責任がない、と思うかもしれません。自分たちはイエスを十字架につけて殺したわけではないと考えるのです。しかしそのような理解は、間違っています。そしてこの間違った理解が、キリスト教会の歴史の中で、ユダヤ人に対する差別や迫害を生んだことも忘れてはなりません。このような間違った理解が生まれるのは、私たちも「神の民」であることを見失っているからです。前回、ユダが抜けて「十一人の使徒」であったのが、マティアを加えて「十二人の使徒」となったことを見ました。教会が誕生するためには、使徒は十一人ではなく、十二人である必要があったからです。十二という数は、イスラエル十二部族の象徴であり、神の民イスラエルは、イスラエル十二部族から生まれました。ですから教会が、十二人の使徒を核として誕生したことは、教会が「新しい神の民」であることを意味しているのです。神の民イスラエルと新しい神の民である教会は、切り離されているのではありません。接続しています。ナザレのイエスは、神の民イスラエルだけでなく、新しい神の民である教会にとっても、つまり私たちにとっても、神から遣わされた方であり、待ち望んでいた方なのです。そして私たちもこの方を拒み、裏切ってきました。もちろん私たちは地上を歩まれた主イエスと出会ったわけではありません。ペトロとまったく同じように主イエスを拒み、裏切ったわけではないでしょう。しかし天におられる主イエスは、聖霊の働きによって繰り返し私たちに出会ってくださり、語りかけてくださいました。しかし私たちは、それをある時は完全に無視し、ある時は自分の都合を優先して聞き流していたのではないでしょうか。父なる神と共に生きてほしい、その愛を豊かに受けて生きてほしいと語りかける主イエスを拒んできたのです。ほかならぬ私たちこそ、神から遣わされた方であり、神の民が待ち望んでいたメシアを拒み、裏切ったのです。ほかならぬ私たちこそ、イエスを十字架につけて殺したのです。
教会が語るべきこと
さて、私たちはここまでペトロの説教の前半を読み進めてきました。しかしこの説教を、ペトロ個人の説教として読むだけでは十分ではありません。その意味で、「ペトロの説教」という小見出しは正確ではありません。冒頭14節にこのようにあります。「ペトロは十一人と共に立って、声を張り上げ、話し始めた」。ペトロは「十一人と共に立って」語り始めたのです。それは、ペトロが十二使徒の代表として語った、ということにほかなりません。ですからこの説教は十二使徒の説教なのであり、十二使徒を核とする教会の説教にほかなりません。しかもキリスト教会最初の説教なのです。そしてこのキリスト教会最初の説教に、教会が語るべきことがすべて含まれている、と言っても過言ではないでしょう。教会が語るべきことは何か。それは、主イエス・キリストの十字架の死と復活です。ペトロが代表として語ったキリスト教会最初の説教は、まさに主イエスの十字架の死と復活を語っています。それだけを語っています。主イエスが地上のご生涯で語った教えや行ったみ業については、まったく語っていません。それは、主イエスの教えやみ業がどうでも良いということではありません。しかし、それらの教えやみ業を本当に受けとめるためには、主イエスの十字架と復活から捉える必要があります。だから教会が宣べ伝えるべきことは、何にも増して主イエスの十字架と復活なのです。また十二使徒を代表して、つまり教会を代表して語ったペトロは、自分自身のことを語りませんでした。自分が主イエスを三度、拒み、裏切ったにもかかわらず、十字架で死なれ復活した主イエスが自分に出会ってくださり、自分の罪を赦して、救ってくださった、とは語らなかったのです。そうではなく神の民である私たちが十字架につけて殺したイエスを、神様が復活させてくださった、そのことによって私たちの救いが実現した。そのことを、そのことだけを宣べ伝えたのです。教会が語るべきことは、その誕生の時から、今に至るまでまったく変わりません。私たちの教会は、ただひたすら主イエスの十字架と復活を宣べ伝えます。それによって私たちの救いが実現したことを宣べ伝えていくのです。
全存在をかけて
しかし間違えてはいけません。ペトロが自分自身のことを語らなかったことは、彼が自分自身の救いと切り離して、主イエスの十字架と復活を語ったということではありません。すでにお話ししたようにペトロは、いえペトロだけでなく十二人の使徒は、自分たちこそがイエスを十字架につけて殺したことを弁えていました。しかしその自分たちが、赦されるはずのない、滅びるしかなかった自分たちが、復活の主イエスと出会うことを通して赦され、救われて、そして聖霊によって新しい言葉を与えられたのです。この救いにあずかり、この救いに生かされているからこそ彼らは、全存在をかけて、主イエスの十字架と復活を宣べ伝えることができました。だから主イエスを裏切った自分たちが語る言葉を、誰も聞いてくれないかもしれない、と恐れるのではなく、「声を張り上げ」て、「わたしの言葉に耳を傾けてください」と語ることができたのです。教会は、私たちは、自分たちとは関係がない主イエスの十字架と復活を宣べ伝えているのではありません。イエスを十字架につけて殺した私たちを救ってくださり、今、生かしてくださっている、主イエスの十字架と復活による救いを宣べ伝えているのです。
若者は幻を見、老人は夢を見る
その主イエスの十字架と復活による救いに生かされるとき、ヨエルが告げた、「若者は幻を見、老人は夢を見る」という預言が、確かに実現していきます。今、この世界は混迷を深め、先行きが見えません。その中で、特に若い方たちが将来の幻、将来のビジョンを持ちにくくなっています。しかし主イエスの十字架と復活による救いにあずかり、その救いの恵みの内に生かされている者は、自分の目にはどれほどこの世界が混迷を深めているように見えても、たとえ破滅に向かっているようにすら思えても、この世界は確かに救いの完成へ、「主の偉大な輝かしい日」に向かっていると信じることができます。そのことを信じ、絶望することなく、希望を持って生きることができるのです。この希望によってこそ、混迷を深める時代にあってなお、若い方たちが、いえ私たち皆が、将来の幻、将来のビジョンを持って歩むことができるのです。年老いた者も、キリストの十字架と復活による救いの恵みの内に生かされている者は、良い夢を見ることができます。希望を持って生きることができるのです。高齢になり、弱りを覚え、今までで出来ていたことが出来なくなり、そして死を迎えるとしても、それで終わりではないからです。その死の先で、主の偉大な輝かしい日に、復活と永遠の命にあずかるのです。この約束に希望を置くとき、歳を重ねた者たちも良い夢を見て、安心して希望を持って生きることができるのです。
イエスを十字架につけて殺した私たちであるにもかかわらず、主イエスの十字架と復活によって、私たちは決して失われることのない希望とまことの平安を与えられて生かされているのです。だからこそ私たちは、教会は、この主イエス・キリストの十字架と復活を、それだけを宣べ伝え続けていくのです。