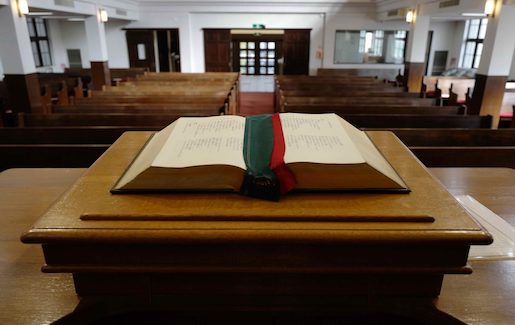説教「羊飼いのいない羊のように」 牧師 藤掛順一
旧約聖書 列王記上第22章1-40節
新約聖書 マタイによる福音書第9章35-38節
アハブの死
私が夕礼拝の説教を担当する日には、旧約聖書列王記上からみ言葉に聞いてきましたが、本日はその最後の22章です。列王記上の第16章29節からこの22章にかけて語られているのは、ダビデ、ソロモンのイスラエル王国が南北に分裂した後の、北王国イスラエルにおける、アハブ王の時代のことです。アハブは、紀元前871年から852年までの19年間イスラエルの王でした。彼は政治家としてはなかなか優れた人だったようで、イスラエル王国は彼の下で繁栄しました。この22章の39節に「彼の建てた象牙の家、彼の建てたすべての町々」とあることにそれが伺えます。しかしこのアハブ王について列王記は、21章の25、26節においてこう語っています。「アハブのように、主の目に悪とされることに身をゆだねた者はいなかった。彼は、その妻イゼベルに唆されたのである。彼は、主がイスラエルの人々の前から追い払われたアモリ人と全く同じように偶像に仕え、甚だしく忌まわしいことを行った」。アハブは、フェニキアのシドンの王の娘であった妻イゼベルの影響を受けて、イスラエルに異教の神また偶像の神であるバアルを持ち込んだのです。政治的には優れた王であったかもしれないが、このことにおいて彼らは、イスラエル王国の歴史における最悪の王と王妃とされています。そしてこのアハブとイゼベル夫妻と対決した主なる神の預言者は、21章までのところにおいてはエリヤでした。しかしアハブの死を語っている本日の22章には、エリヤは登場しません。ここにはもう一人の預言者、イムラの子ミカヤという人が出て来ます。彼が、主なる神のみ心によってアハブが死ぬことを告げ、その預言がその通りに実現したことがここに語られているのです。つまりアハブがその数々の悪行の報いを主なる神から受けたことがこの22章に語られているのです。
北王国イスラエルと南王国ユダ
そのことは、イスラエルとアラムつまりシリアとの戦いの中で実現しました。イスラエルとアラムが戦ったことは、第20章にも語られていました。その戦いは一応イスラエルの勝利に終わりましたが、決着はついていませんでした。三年目になって、その戦いが再開されたことが22章の2節に語られています。その戦いは、アハブが率いる北王国イスラエルのみでなく、南王国ユダをも巻き込んだものとなりました。南王国ユダのこの時の王はヨシャファトでした。北王国におけるアハブの治世と南王国におけるヨシャファトの治世はほぼ重なっています。南王国においてはダビデの子孫によるダビデ王朝が続いており、ヨシャファトはダビデから数えて六代目の王となります。アハブは、アラムとの戦いを再開するに当たって、南王国ユダの王ヨシャファトに、共に出陣してくれないかと持ちかけたのです。それに対してヨシャファトは4節にあるように「わたしはあなたと一体、わたしの民はあなたの民と一体、わたしの馬はあなたの馬と一体です」と答えて、アハブと共に出陣することを受け入れたのです。ここには、分裂したとは言え、北王国と南王国の間には、自分たちは同じ一つの民だ、という意識が強くあったことが示されています。それと同時に、当時の力関係においては、北王国の方が主導的な立場にあったことも伺えます。私たちは、南王国ユダこそ、ダビデの子孫が王として治める神の民イスラエルの正統的な王国だ、と思いがちですが、南王国はイスラエルの十二の部族の内二つのみから成っていたのに対して、残りの十部属が北王国イスラエルに属していることからも分かるように、北王国の方が圧倒的に強い力を持っていたのです。つまり列王記は、政治的に力のある王であったり、経済的に国が繁栄していたとしても、その王や国が神のみ心に従って歩んでいるというわけではない、それは無関係だ、ということを語っているのです。
主の言葉を求める
さてユダの王ヨシャファトは、アハブと共にアラムと戦うことを承知しましたが、そこに一つの条件を付けました。5節にあるように、「まず主の言葉を求めてください」と言ったのです。戦いに臨む前に、主なる神のみ心を求め、これが主の求めておられる戦いなのだ、ということを確かめた上で出陣する、ということが行われていました。ヨシャファトは、ダビデの後継者として、ユダ王国を主なる神の民として治めていこうとしています。そのユダが加わる戦いが主のみ心にかなったものであることを主の言葉によって確かめようとしたのです。そこでアハブは、ヨシャファトの前に約400人の預言者を召集し、「わたしはラモト・ギレアドに行って戦いを挑むべきか、それとも控えるべきか」と問いました。すると彼らは、「攻め上ってください。主は、王の手にこれをお渡しになります」と答えました。400人の預言者が異口同音に、出陣することを勧めたのです。それ自体がかなり胡散臭いことです。みんなが、王の意に沿うことしか言わないのです。そのことに疑いを抱いたヨシャファトは「ここには、このほかに我々が尋ねることのできる主の預言者はいないのですか」と問いました。するとアハブはこう答えました。「もう一人、主の御旨を尋ねることのできる者がいます。しかし、彼はわたしに幸運を預言することがなく、災いばかり預言するので、わたしは彼を憎んでいます。イムラの子ミカヤという者です」。400人の預言者たちが王の意向に沿ったことを言い、幸運を預言していたのに対して、ミカヤだけはいつも、災いを預言していたのです。なのでアハブは彼を憎んでいました。しかしヨシャファトは、「王よ、そのように言ってはなりません」とアハブを諫めました。つまり、そういう預言者の言葉こそちゃんと聞くべきだ、ということです。そこでアハブはミカヤを呼びに行かせます。ミカヤの到着を待っている間、二人の王はイスラエルの首都サマリアの城門のところで王座に着き、その前であの400人の預言者たちが盛んに預言をしていました。その代表格であるケナアナの子ツィドキヤという人は、数本の鉄の角を作って、「主はこう言われる。これをもってアラムを突き、殲滅せよ」と言いました。他の預言者たちも同じように、「ラモト・ギレアドに攻め上って勝利を得てください。主は敵を王の手にお渡しになります」と言いました。皆が威勢のいいことを言って戦いを勧めたのです。
まことの預言者とお抱え預言者
一方ミカヤを呼びに言った使いの者はミカヤに会うとこう言い含めたと13節にあります。「いいですか。預言者たちは口をそろえて、王に幸運を告げています。どうかあなたも、彼らと同じように語り、幸運を告げてください」。それに対してミカヤは「主は生きておられる。主がわたしに言われる事をわたしは告げる」と言いました。ここに、あの400人の預言者とミカヤの違いが示されています。あの400人の預言者は「宮廷預言者」と言って、王の「お抱え預言者」です。彼らは王が求める、王の意向を忖度した預言をするのです。それに対してミカヤは、「主がわたしに言われる事をわたしは告げる」と言っています。こちらの方が本物の預言者です。人間の思いに合わせた預言をするのは本物の預言者ではありません。主なる神の言葉を、たとえそれが人間にとって都合の悪い、「災い」だったとしても、その通りに告げる、それが預言者の使命です。そのように対照的な預言者の姿がここに描かれているのです。そして聖書は注意深く、この400人の預言者については、「主の預言者」とは言っていません。6節にはただ「預言者」とだけ言われていますし、この後の22節では「彼のすべての預言者たち」と言われています。彼とはアハブです。また23節にも「このあなたのすべての預言者」とあります。「あなた」もアハブです。つまりこの400人の預言者たちは、主の預言者ではなくて、アハブの預言者、王の家臣であるお抱え預言者であることが明確に示されているのです。つまりこの22章には、アハブ王のお抱え預言者400人と、主の預言者ミカヤとの対決が語られているのです。
列王記上の18章には、主の預言者エリヤが、バアルの預言者450人と一人で対決したことが語られていました。本日のところもそれと似ていると言えるかもしれません。ただ、あの時は、主なる神の預言者エリヤと、異教の神バアルの預言者の対決でした。本日のところに語られている400人の預言者は、バアルの預言者ではありません。ヨシャファトが求めたように、彼らは主なる神の言葉を求めるために召集されたのです。彼らが語っている預言も、「主の言葉」なのです。11節でツィドキヤは「主はこう言われる。これをもってアラムを突き、殲滅せよ」と言っています。他の預言者たちも、「主は敵を王の手にお渡しになります」と言っています。ですからこの22章に描かれているのは、主なる神とバアルの戦いではありません。同じ主なる神の預言者と言われている人たちの中に、「主がわたしに言われる事をわたしは告げる」というまことの預言者と、王の思いを忖度し、王に幸運を告げるお抱え預言者とがいる、という事態なのです。それはバアルの預言者との対決よりも、ある意味より深刻なことだと言わなければならないでしょう。
主なる神がお語りになる、という感覚の喪失
さて、アハブとヨシャファトの前にきたミカヤにアハブは「ミカヤよ、我々はラモト・ギレアドに行って戦いを挑むべきか、それとも控えるべきか、どちらだ」と問いました。するとミカヤは「攻め上って勝利を得てください。主は敵を王の手にお渡しになります」と答えました。つまりミカヤは、400人のお抱え預言者たちと同じことを言ったのです。それに対するアハブの反応はとても興味深いものです。彼は「何度誓わせたら、お前は主の名によって真実だけをわたしに告げるようになるのか」と言ったのです。つまりアハブは、ミカヤの言葉を信じていないのです。ミカヤは、他の預言者たちと同じことを語りました。使いの者に言い含められた通りに、王の幸運を告げたのです。これまで、幸運を預言することがなく、災いばかり預言してきたミカヤが、今回は幸運を告げたのですから、喜んでもよさそうなものです。しかしアハブはそれを「嘘だろう」と思っています。この男が自分に幸運を告げるはずがない、と思っているのです。このことは何を意味しているのでしょうか。それは要するに、アハブは、主なる神が何かをお語りになるとは全く思っていない、ということでしょう。彼にとっては、400人のお抱え預言者とミカヤの違いは、自分の意に従い、自分に幸運を告げる言葉を語る者と、自分に逆らい、敵対し、災いを語る者との違いです。自分の味方か敵か、ということでしか彼は人間を見ていないのです。そして敵である者が自分の意に沿うことを言っても、それを信用しようとはしないのです。そこには、主なる神がお告げになることを聞こうという姿勢は全くありません。そもそも、主なる神が何かをお語りになる、という感覚すらないのです。すべては人間の言葉であり、その人間は自分の敵か味方かどちらかに色分けされているのです。
このアハブの姿は、現代の社会を生きている人間の姿だと言えます。私たち自身もそれと無関係ではありません。今のこの社会には、神がお告げになることを聞こうという姿勢はありません。そもそも、主なる神が何かをお語りになる、という感覚そのものが失われているのです。すべては人間の言葉であり、そしてその人間は自分の敵か味方かに色分けされています。そして、味方の言葉は喜んで聞くが、敵の言葉には一切耳を傾けずに生きている、それが現代の社会を生きている人々の基本的な姿なのではないでしょうか。預言者の言葉つまり神の言葉もそこでは、自分の思いに合うか合わないかで判断されています。つまりアハブは、神などまともに信じてはいないのです。それは非常に現代的な生き方だと言えるでしょう。それは他人事ではありません。私たちも、主なる神がお語りになる言葉を聞こうという姿勢を失ってしまうなら、このアハブのようになり、全てを人間の言葉としてしか聞かず、自分の意に沿う言葉か、それに反する言葉かで判断するという、現代の社会を支配している感覚に取り込まれていってしまうのです。
羊飼いのいない羊のように
さてミカヤは17節以下で、彼が王の幸運を告げる言葉を語ったことの背後にある主なる神の思い、ご計画を明らかにしていきました。「イスラエル人が皆、羊飼いのいない羊のように山々に散っているのをわたしは見ました。主は、『彼らには主人がいない。彼らをそれぞれ自分の家に無事に帰らせよ』と言われました」。イスラエルの人々が、羊飼いのいない羊のように散らされてしまっている、それが今の現実だと主なる神は見ておられるのです。イスラエルを羊飼いとして守り、養い、導くべき者、それは王です。しかし今や、イスラエルにはそのような王がいない。アハブはイスラエルの民の羊飼いとしての務めを全く果たしていないのです。そのために民は散らされ、苦しみの中に放置されている。主なる神は、そのイスラエルの民をそれぞれ自分の家に無事に帰らせようとしておられるのです。そのために、アハブの400人のお抱え預言者たちも用いられている、というのが19節以下に語られていることです。そこに描かれているのは、主なる神が天の王座に座しておられ、その周りで天の万軍つまり天使たちが話し合っている、という場面です。主なる神はそこで「アハブを唆し、ラモト・ギレアドに攻め上らせて倒れさせるのは誰か」と言われました。その求めに答えてある霊が進み出て「わたしが彼を唆します」と言いました。彼の計画とは、自分がアハブの全ての預言者たちの口を通して偽りを言う霊となり、アハブに出陣を決断させる、というものでした。この霊の働きによって、アハブの400人のお抱え預言者たちは、異口同音に、「ラモト・ギレアドに攻め上って勝利を得てください。主は敵を王の手にお渡しになります」と語ったのです。それは全て、アハブをアラムとの戦場に連れ出してそこで倒れさせようという主なる神のご計画だったのです。23節でミカヤはこう言っています。「今御覧のとおり、主がこのあなたのすべての預言者の口に偽りを言う霊を置かれました。主はあなたに災いを告げておられるのです」。400人の預言者はアハブの幸運を告げたように思えるけれども、実はそれは主なる神が彼らに偽りを語らせているのであって、主はアハブの災いを告げておられるのです。主なる神はこのようにアハブを戦場で倒れさせることによって、羊飼いのいない羊のように散らされてしまっているイスラエルの人々を、それぞれ自分の家に無事に帰らせようとしておられるのです。
神の言葉に聞こうとしないアハブ
ミカヤはこのように、アハブの400人の預言者が出陣を勧めていることと、ミカヤ自身も王の予想に反して出陣を勧めたことの背後にある主なる神の思い、ご計画を明確に告げました。それを聞いたアハブはどうしたでしょうか。彼はミカヤを捕え、獄につなぎ、「わたしが無事に帰って来るまで、わずかな食べ物とわずかな飲み物しか与えるな」と命じました。つまり彼は、ミカヤが告げた災いを全く意に介しておらず、自分がこの戦いで死ぬとは全く思っていないのです。アラムに対して出陣することを彼は最初から決めていたのであって、それを全く変えるつもりはないのです。ユダの王ヨシャファトに求められたから、一応主なる神の言葉を求めてはいますが、それはポーズに過ぎないのであって、主の言葉によって自分の思いや行動を変えるつもりは全くないのです。つまり先ほども申しましたように、彼は主なる神の言葉を聞こうという姿勢を全く持っていないし、そもそも主なる神が何かを語られるとも思っていないのです。彼の行動を決めるのは自分の思いのみであり、それに対して語られる言葉は、その自分に賛成する味方の言葉か、反対する敵の言葉のどちらかなのです。
主のみ心は必ず実現する
このようにしてアハブは、ミカヤの預言を無視して出陣しました。しかも彼は狡賢く、ヨシャファトには王としての装いで戦いに出るように言い、自分は変装して王であることが分からないようにして戦いに臨みました。なのでアラムの兵たちは、ヨシャファトを「これこそイスラエルの王にちがいない」と思って攻めかかりましたが、ヨシャファトが助けを求めて叫んだことによって、イスラエルの王ではないことが分かり、追うのをやめました。ところが、一人の兵が何気なく、ということはアハブを狙ったわけではなく、弓を引いて射た矢がアハブに当たり、その傷によってアハブは命を落としました。こうして、アハブを戦場で倒れさせるという主なる神のご計画が実現したのです。ここには、主なる神のご計画、み心は、人間のどのような思いをも超えて必ず実現することが語られています。アハブは策略をめぐらして、敵の攻撃がヨシャファトに集中するようにし、自分は一兵卒の姿で出陣しました。しかし結局、誰をも狙ったわけではない矢が彼に当り、彼は死にました。人間の意図、思い、策略を超えて、主なる神のみ心が行われたのです。そのみ心を妨げようとする人間の目論見はことごとく失敗したのです。またここには、神はご自身のご計画を、偽りを語る霊をも用いて実現なさる、ということが語られています。アハブは、自らのお抱え預言者たちに主が語らせた偽りの預言に騙されて出陣し、命を落としたように見えるのです。主なる神が嘘を言って人を騙すなんて、と思うかもしれません。しかし見てきたように、アハブは主なる神のみ言葉を聞いてどうこうしようとは全く思っていません。彼は、最初から決めていた自分の思いを実行したに過ぎないのです。そのことの中で、主のみ心が実現したのです。そのみ心とは、羊飼いのいない羊のように散らされてしまっているイスラエルの人々を、それぞれ自分の家に無事に帰らせようという、主の憐れみのみ心です。アハブの戦死によって、イスラエルの人々はアラムとの戦場を離脱して、おのおの自分の町、自分の国に帰ることができたことが36節に語られているのです。
飼い主のいない羊を深く憐れむ主イエスのみ心
本日共に読まれた新約聖書の箇所、マタイによる福音書第9章35節以下には、主イエス・キリストが、人々が飼い主のいない羊のように弱り果て、打ちひしがれているのを見て、深く憐れまれ、み国の福音を告げ知らせたことが語られています。主イエスはその憐れみのみ心によってこの世を歩み、十字架の苦しみと死にまで至って下さいました。そのようにして、まことの羊飼いとして私たちを養い、守り、導いて下さっているのです。その主の憐れみのみ心は、人間が主イエスを十字架につけて殺したことによっても妨げられることなく、それによってかえって実現しました。受難週からイースターに向けて、私たちはそのことを覚えつつ歩みます。そして主は、その恵みと憐れみのみ心を、ご自分の預言者によって告げて下さっています。主が語られることを聞く、という姿勢を失うことなく、「主がわたしに言われる事をわたしは告げる」ということに徹していくなら、私たち自身が、主の憐れみのみ心を告げ知らせる預言者、「収穫のための働き手」となることができるのです。