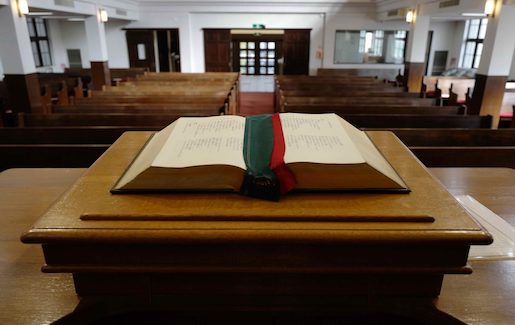説 教 「裁くのは主」副牧師 川嶋章弘
旧 約 エレミヤ書第20章7-13節
新 約 コリントの信徒への手紙一第4章1-5節
伝道者とは何であるのか
私が主日礼拝の担当をするときはコリントの信徒への手紙一を読み進めています。本日から第4章に入ります。その冒頭でパウロは、「こういうわけですから、人はわたしたちをキリストに仕える者、神の秘められた計画をゆだねられた管理者と考えるべきです」と言っています。「こういうわけですから」とありますから、パウロはこれまでに語ってきたことのまとめとして、このことを語っているのです。すでにお話ししてきたように、コリント教会では分派争いが起こっていました。コリント教会の人たちはそれぞれが異なる伝道者を支持して、パウロ派、アポロ派、ケファ派などの分派を形成し、互いに争っていたのです。そのような分派争いが起こった一つの原因は、コリント教会の人たちが伝道者とは何であるのか、ということを分かっていなかったからです。だからパウロは3章5節以下で自分やアポロは何者なのかを語ってきました。5節では、アポロもパウロもコリント教会の人たちを「信仰に導くためにそれぞれ主がお与えになった分に応じて仕えた者」であると語り、また9節では、パウロとアポロは担った働きは違っても、どちらも「神のために力を合わせて働く者」であると語っていました。そのように語ってきたことのまとめとして、本日の箇所の冒頭でパウロは、コリント教会の人たちがパウロやアポロのことを、つまり伝道者のことを、「キリストに仕える者、神の秘められた計画をゆだねられた管理者と考えるべきです」、と言っているのです。
伝道者とは何であるのかということは、コリント教会だけでなく、私たちの教会にも関わりがあることです。もちろん私自身を含む伝道者自身に、また佐藤神学生のように伝道者として立てられようとしている者に、あるいは伝道者への志を与えられている者に、関わりがあるのは言うまでもありません。伝道者ないしその志を与えられている者にとって、伝道者とは何であるのかと問うことは、自分自身が何者なのかと問うことでもあるからです。しかしこのことは教会にも関わりがあることです。教会にとっても伝道者とは何であるのかという問いに向き合い、このことを繰り返し確認していくのは大切なことなのです。コリント教会はこのことにしっかり向き合い、確認できていなかったから、自分たちの教会にとって伝道者とは何であるのかが分からなくなっていました。その結果、それぞれが異なる伝道者を支持し、分派争いをしていたのです。
キリストに仕える者
パウロはコリント教会の人たちに、また私たちに、伝道者が「キリストに仕える者」であると言います。何だそんなことか、そんなことは当たり前だ、と思われるかもしれません。確かに、伝道者はキリストに仕える者です。当たり前のことを言っています。しかしこの「仕える者」と訳された言葉は、味わい深い言葉です。先ほど見た3章5節でも「この二人は、あなたがたを信仰に導くためにそれぞれ主がお与えになった分に応じて仕えた者です」と言われていて、「仕えた者」とありました。「仕える者」と「仕えた者」、日本語としては同じですが、実は原文では違う言葉です。3章5節の「仕えた者」が「給仕をする僕」を表すのに対して、本日の箇所の「仕える者」は、「下で」と「櫓を漕ぐ」を組み合わせた言葉で、「船底で櫓を漕ぐ奴隷」を表します。ある改革教会の信仰告白で、この言葉が次のように解説されていました。「これ[この言葉]は目を船長に注ぐ舟漕ぎ奴隷のことである。この奴隷は己のため、あるいは己の意志によってでなく、他の人の、すなわち主人の意志、その命令に全面的に依存しているのである」(「第二スイス信仰告白」第一八)。それが「仕える者」だ、と言います。ですから伝道者がキリストに仕える者であるとは、船漕ぎ奴隷がいつも船長に目を向けているように、伝道者がいつも主人であるキリストに目を向けて、自分の思いや考えに頼るのではなく、主人であるキリストのご意志、そのご命令に全面的に依存することなのです。
しかし考えてみれば、キリストに仕える者であるのは伝道者に限ったことではありません。私たちキリスト者は誰もがキリストに仕える者に違いない。教会を舟にたとえるなら、そのメンバーである私たちは教会という舟の櫓を漕ぐ者たち、と言うことができるのではないでしょうか。もし私たちが自分の思いや考えだけで自分の好き勝手に櫓を漕ぐなら、どんなに漕ぎ手が多くても、教会という舟が前進することはありません。皆がてんでんばらばらに漕げば、舟はまったく進まないか、迷走するしかないでしょう。私たちは教会の頭であるキリスト、船長であるキリストに目を向けて、船長であるキリストの思いを受けとめて、そのご命令に従って櫓を漕ぐのです。そうすることによって私たちは教会という舟を前進させていくことができるのです。
神の秘められた計画をゆだねられた管理者
パウロは伝道者が「神の秘められた計画をゆだねられた管理者」である、とも言っています。「神の秘められた計画」とは、キリストの十字架による福音であり、ご自分の独り子を十字架に架けることによって私たち罪人を救う、その救いのご計画です。「秘められた計画」という言葉はもともと密儀宗教などでは、人々には隠されていた儀式を意味しました。同じように「神の秘められた計画」もかつては隠されていましたが、今やキリストが世に来てくださり、十字架で死んでくださったことによって明らかになったのです。伝道者は、この「神の秘められた計画をゆだねられた管理者」と言われています。それは、隠されていたキリストの十字架による福音を示された伝道者が、それを宣べ伝える務めを担っている、ということです。伝道者はキリストの十字架による福音を宣べ伝えます。神の独り子イエス・キリストが十字架に架けられ死なれることによって、私たちの罪が赦され、救われたという良い知らせを宣べ伝えるのです。
キリストに忠実であること
そのように「神の秘められた計画をゆだねられた管理者」である伝道者に「要求されるのは忠実であること」だと、パウロは2節で語ります。福音を宣べ伝えるために要求されるのは、キリストに忠実であることなのです。それは、伝道者が「キリストに仕える者」である、と言われていたことと重なります。キリストに忠実であるとは、伝道者がいつも主人であるキリストに目を注いで、自分の思いや考えに従うのではなく、主人であるキリストのご意志、そのご命令に従っていくことです。このことが伝道者に求められているのです。パウロとアポロでは、コリント教会における働きに違いがありました。パウロは植え、アポロは水を注いだ、と言われている通りです。またパウロとアポロでは賜物にも違いがありました。しかしそのような働きや賜物の違いが問題なのではなく、キリストに忠実であるかどうか、ということが重要なのです。キリストに忠実であれば、働きや賜物の違いは問題になるのではなく、むしろより豊かに用いられていくのです。
キリストに忠実であることも、伝道者だけに求められているのではありません。私たちキリスト者は誰もがキリストに忠実であることを求められています。私たちはそれぞれ異なるバラエティーに富んだ賜物を与えられ、教会においてもそれぞれに異なる働きを担っています。この3月はそのことが目に見える形で分かるときかもしれません。本日の礼拝では、長老・執事の任職が行われますし、来週の礼拝では教会学校教師の任職、再来週の礼拝では奏楽者の任職や聖歌隊のための祈りがあります。また今、次年度に向けて、それぞれの委員会や奉仕の会のメンバーが決まりつつあります。奉仕によっては専門的な技術や知識が求められることもありますし、そこまでではなくても、奉仕による向き不向きも確かにあります。しかしどの委員会どの奉仕であっても、何よりも求められているのは、キリストに忠実である、ということです。あえて言えば、キリストに忠実であることだけが要求されている、と言ってもよい。私たちがキリストに忠実であるなら、それぞれの異なる働き、異なる賜物は豊かに用いられていくに違いありません。しかし私たちがキリストに忠実でないなら、たとえどれほどすぐれた賜物を与えられていても、どれほど熱意があったとしても、教会という舟を前進させていくことはできません。船長であるキリストの思いを無視するなら、教会という舟はあらぬ方向へ進むだけです。それでは教会を建て上げていくことはできません。私たちがキリストに忠実であるとき、それぞれの異なる働きと賜物が豊かに用いられて、私たちは教会という舟を前進させ、教会を建て上げていくことができるのです。
キリストに忠実であることだけが求められている。しかしそれは簡単なことではありません。私たちは自分の力によってキリストに忠実であることができるわけではありません。むしろ自分の力に頼ってキリストに背いてばかりいます。そのような私たちがキリストに忠実に生きる者とされていくのは、どのようにしてなのでしょうか。このことが3節以下から示されていきます。
裁かれても少しも問題ではない
パウロは3節でこのように言っています。「わたしにとっては、あなたがたから裁かれようと、人間の法廷で裁かれようと、少しも問題ではありません」。この3節からパウロは自分のことを語り始めます。1、2節で、伝道者に要求されているのはキリストに忠実であることだと語っていましたから、その文脈を考えれば、ここでパウロが、いかに自分はキリストに忠実であるかを語り始めても不思議ではないように思えます。ところがパウロはそのように語りません。「あなたがたから」、つまりコリント教会の人たちから裁かれても少しも問題ではない、と語るのです。ということはコリント教会の人たちがパウロを裁いていたということです。コリント教会における分派争いの実体は、裁き合いであったのです。当然、パウロ以外の指導者を支持するグループの人たちはパウロを批判しました。パウロが使徒にふさわしくないと批判したようです。それにもかかわらずパウロが、そのような批判は少しも問題ではないと言うことができたのは、パウロ派の支持を頼みとしたからではありません。おそらくパウロ派の人たちも、ほかのグループの指導者を批判していたに違いありません。ですからもしパウロが、パウロ派の支持や力を頼みとしていたなら、パウロ自身が分派争いに、裁き合いにコミットしていることになります。しかしパウロは分派争いそのものを退けます。分派争いをすればキリストが「幾つにも分けられて」しまうことになるからです(1章13節)。それゆえパウロがコリント教会の人たちから裁かれると言うとき、それは彼らから批判されることだけでなく、支持されることをも含んでいます。批判であれ支持であれ、どんな形で裁かれても少しも問題ではない、と言っているのです。別の言い方をすれば、コリント教会の人たちからどんな点数をつけられても、悪い点であろうと良い点であろうと気にしない、と言っているのです。
私たちにとっては大問題
しかし私たちにとっては、自分がほかの人からどんな点数をつけられているのか、自分がどのように評価されているのかは、少しも問題ではないどころか大問題です。私たちは評価される社会で育ち、今もその社会で生き、絶えず自分がどう評価されているかを気にしながら生きています。もちろん評価することがすべて誤りだということではありません。むしろ適切な判断は、適切な評価に基づきます。評価と判断なしには社会は成り立ちません。教会においても評価と判断がまったく必要ない、ということではありません。たとえばある人の賜物が最大限活かされる奉仕を考えるというのも、ある評価と判断を伴っています。社会においてはもちろんのこと、教会においても評価と判断が必要ないということではないのです。しかし問題は、評価がすべてになってしまっていないか、ということです。ほかの人からの評価を絶えず気にしているということは、自分も絶えずほかの人を評価しているということです。人との関わりが、相手に点数をつけ、相手を評価することだけになってしまう。評価して、「この人はこういう人だ」と判断して、白黒つけてしまう。それが「裁く」ということです。私たちは人から評価され、判断され、白黒つけられて裁かれることに絶えず不安になり、怯えています。と同時に、私たちも人を評価し、判断し、白黒つけて、裁いています。そのようにして私たちは裁き合っているのです。
また私たちは人から裁かれ、人を裁いているだけではなく、自分自身をも裁いています。人からの評価を絶えず気にして、また自分も絶えず人を評価して生きるとき、そこに起こるのは自分とほかの人を比べることです。絶えず自分とほかの人を比べることで、自分はよくやっていると評価したり、あるいは自分は駄目だ、価値がないと評価したりして、自分自身を裁いているのです。そうやって自分自身を裁くことで、私たちは優越感に浸ったり劣等感に苛まれたりして、心穏やかではない日々を過ごしています。しかしパウロは3節で「わたしは、自分で自分を裁くことすらしません」とも言います。自分とほかの人を比べて、自分を評価して、判断して、自分自身を裁くこともしない、と言うのです。
鋼のメンタルを身に着ける?
パウロが、ほかの人から裁かれても少しも問題ではないと、自分で自分を裁くことすらしない、と言うことができたのは何故でしょうか。パウロの信念が確固としたものであったからでしょうか。自分の信念がしっかりしているから、ほかの人から何を言われても気にならないし、自分とほかの人を比べて自分自身を裁くこともない、ということなのでしょうか。そうであれば、私たちもパウロと同じように強い信念を持つことによって、ほかの人から何を言われても気にしないようになりなさい、ということになります。平たく言えば、強い信念を持って、強靭なメンタル、鋼のメンタルを身に着けなさい、ということです。しかしそんなことを言われても、私のように鋼のメンタルからほど遠い人間は困ってしまいます。パウロ先生のマネはできません、と思ってあきらめて終わりです。でも、思うのです。パウロも鋼のメンタルではなかったのではないか。人から裁かれてへっちゃらだった、というわけではなかったのではないか。そう思います。パウロの手紙を読むと、パウロも結構、人から言われたことを気にしているように思えるからです。
裁くのは主
そのパウロが4節でこのように言っています。「自分には何もやましいところはないが、それでわたしが義とされているわけではありません。わたしを裁くのは主なのです」。「わたしを裁くのは主」。だからほかの人から裁かれても少しも問題ではないと、自分で自分を裁くことすらしない、とパウロは言えるのです。「自分には何もやましいところはないかもしれない、信念を持っているかもしれない、それなりに働きを担っているかもしれない、しかしそれで自分は義とされ救われたのではない。ただ神が一方的な恵みによって御子キリストをこの世に遣わしてくださり、十字架に架けてくださったことによって自分は義とされ救われた。そして十字架で死んでくださったキリストが終わりの日に、再びこの世に来てくださり、すべてをお裁きになる」。パウロはこのことを信じて生きました。自分の信念を頼みとしたのではなく、このことを確信して生きたのです。だからパウロは5節で「ですから、主が来られるまでは、先走って何も裁いてはいけません」と言うのです。裁くのは主です。主イエス・キリストが私たちをお裁きになります。だから私たちは主が来られる前に、終わりの日が来る前に、先走ってほかの人を裁いたり、自分自身を裁いたりしてはならないのです。私たちは裁きを主にお任せして生きます。終わりの日に再び来てくださる主イエス・キリストに裁きをお任せして、委ねて生きるのです。
葛藤しつつ
しかし裁きを主に委ねて生きることは、葛藤を伴うことでもあります。このことが共に読まれた旧約聖書エレミヤ書20章7節以下のエレミヤの祈りから示されます。預言者エレミヤは主の言葉を語ったがゆえに多くの人から非難されました。10節にこのようにあります。「わたしには聞こえています 多くの人の非難が。『恐怖が四方から迫る』と彼らは言う。『共に彼を弾劾しよう』と。わたしの味方だった者も皆 わたしがつまずくのを待ち構えている」。多くの人から非難され、味方だった者にも裏切られて、エレミヤは言葉を発すれば、「『不法だ、暴力だ』と叫ばずにはいられ」ない深い嘆きの中にありました(8節)。12節にあるように「わたしに見させてください あなたが彼らに復讐されるのを」と、自分を苦しめる者への復讐を主に願ってすらいます。しかしそのエレミヤが12節の終わりでこのように祈っています。「わたしの訴えをあなたに打ち明け お任せします」。主にお任せします、と祈ったのです。苦しみと嘆き、怒りと憎しみに駆られて、自分で裁いてしまいそうになる中で、エレミヤは「裁くのは主」と信じ、裁きを主にお任せしたのです。裁きを主に任せて生きるとは、葛藤なしに生きることではありません。むしろ自分で裁いてしまいそうになるときも、葛藤しつつ主に裁きをお任せして生きることなのです。
神からおほめにあずかる
パウロは5節の後半でこのように言っています。「主は闇の中に隠されている秘密を明るみに出し、人の心の企てをも明らかにされます。そのとき、おのおのは神からおほめにあずかります」。私たちは終わりの日の主の裁きに委ねて生きます。その主の裁きにおいて、私たちが隠していた秘密が明るみに出され、私たちの心の中の企ても明らかにされます。そうであれば私たちは滅ぼされるしかないように思えます。私たちが隠している秘密や心の中の企ては裁かれるしかない醜いもの、罪にまみれたものばかりだからです。ところがパウロは、その主の裁きのときに、「おのおのは神からおほめにあずかります」と言うのです。それぞれが神から褒めていただける、キリストに「よくやった」と言っていただけるのです。パウロがそう言えるのは、自分には隠している秘密もないし、心の中の企ても明らかにされても困らないものばかりなので、自分は裁きに耐えられると思っていたからではありません。別の手紙で「わたしは自分の望む善は行わず、望まない悪を行っている」と言っているパウロが、自分には裁かれる罪がないと思っていたはずがありません。そうではなく裁く主が、パウロのために、そして私たちのために十字架に架かって死んでくださった方だから、主イエス・キリストだからです。私たちの罪をすべて背負って、私たちの代わりに十字架で死んでくださったキリストが、それほどまでに私たちを愛し、大切にしてくださったキリストが、終わりの日に再び来てくださり、私たちを裁いてくださる。だから私たちは不安になったり恐れたりすることなく、安心して、キリストに「よくやった」と言っていただけるのを楽しみにして、主に裁きをお任せして生きるのです。
主に裁きを委ねて生きることによって
そのように裁きを主にお任せして、終わりの日の主の裁きを待ち望んで生きる私たちに、キリストに忠実に生きる歩みが与えられていきます。私たちは自分の力を頼みとしてキリストに忠実に生きることなどできません。自分の力を頼みとするなら、私たちはキリストの思いに目を向けるのではなく、ほかの人からの評価や自分自身による評価ばかり気にして、人を裁き、自分自身をも裁いてしまうのです。しかし自分で裁くのはもうやめて、自分で裁いてしまいそうになるときも、葛藤しつつも主に裁きをお任せします。主に裁きを委ねて生きるところに、ほかの人の評価や自分自身による評価ばかり気にして生きることからの解放が、人を裁き自分自身を裁くことからの解放が与えられていくのです。もう人から裁かれても気にしなくてよい。もう人を裁かなくてよい。もう自分自身を裁かなくてよい。この解放によってこそ、私たちはキリストの思いに目を向け、キリストに忠実に生きる者とされていきます。主に裁きを委ねて生きることによってこそ、私たちは船長であるキリストにだけ目を向けて、船長であるキリストの思いを受けとめて、そのご命令に従って櫓を漕ぎ、教会という舟を前進させていくことが、教会を建て上げていくことができるのです。