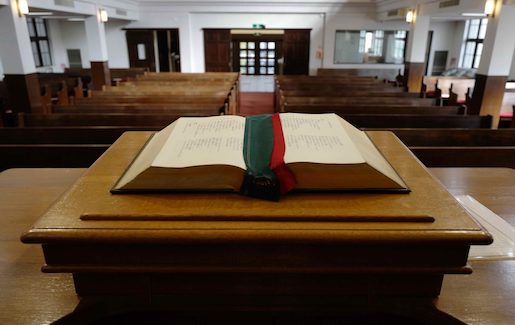説教「この世に蒔かれた小さな種」 牧師 藤掛順一
旧約聖書 詩編第126編1-6節
新約聖書 マタイによる福音書第13章31-35節
「種」のたとえ
マタイによる福音書の第13章には、主イエスがお語りになったたとえ話が集められています。3〜9節には先ず、「種を蒔く人」のたとえがありました。18〜23節には主イエスご自身によるそのたとえの説明が語られていました。24節以下には「毒麦」のたとえが語られました。そして本日の31節には「イエスは、別のたとえを持ち出して、彼らに言われた」とあって、「からし種」と「パン種」のたとえが語られていきます。これらのたとえに用いられている題材にはある共通性があります。小さな種が蒔かれ、育っていって実を結ぶ、ということです。「パン種」は植物の種とは違いますが、見つめられているのは同じようなことだと言えるでしょう。蒔かれた時は小さなものが、育っていって、良きにつけ悪しきにつけ、大きな影響を及ぼすようになることを、これらのたとえは示しているのです。
からし種とパン種
本日の箇所のたとえですが、先ず、「天の国はからし種に似ている。人がこれを取って畑に蒔けば、どんな種よりも小さいのに、成長するとどの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来て枝に巣を作るほどの木になる」とあります。からし種というのは本当に小さい、粉のような種です。地面に落ちたらもうどこにあるかわかりません。それが成長すると、どの野菜よりも大きくなり、空の鳥が枝に巣を作るほどになる、それほどに大きくなるのです。
次に「パン種」のたとえです。「天の国はパン種に似ている。女がこれを取って三サトンの粉に混ぜると、やがて全体が膨れる」。パン種とは、小麦粉を発酵させ、ふっくらとしたパンにするパン酵母、イースト菌のことです。それは小麦粉全体の量と比べれば、ほんの一握りです。それがパン生地に混ぜ合わされ、こねられ、寝かされているうちに、生地全体が膨らんでくるのです。ほんの僅かなパン種ですが、それがなければおいしいパンは焼けないのです。
二千年前と現在
私たちはこれらのたとえを、およそ二千年前に、ユダヤのベツレヘムという小さな町で生まれ、数年間の伝道の活動の末に十字架につけられた主イエス・キリストのことが、今や、全世界に宣べ伝えられ、多くの人々が主イエスを救い主と信じて、教会に連なって生きている、という事実と重ね合わせて読むことができます。主イエスが地上を歩まれたユダヤの地とは遠く離れたこの日本においても、今日のこの主の日に、私たちがこうして教会に集まり、主イエスの父である神を礼拝しています。先週のイースターには三百名を超える者たちが集いました。小さなからし種が、そこまで大きな木となったのです。
また「パン種」のたとえも、二千年前に、この世という生地の中にそっと入れられたパン種である主イエス・キリストが、世界の歴史に大きな影響を及ぼし、世界を変えていった、ということと重ね合わせることができます。これらのたとえは、主イエスと、主イエスを信じる者の群れである教会のその後の歩みを予告している、と言うことができるのです。
このように、二千年前と現在とを比べてみる時に、私たちはまさにこれらのたとえに語られている通りのことが起っていると実感することができます。しかしこのたとえを実際に聞いた人々の中に、主イエスのことが将来世界中に知られ、信じられるようになると思った人は一人もいなかったでしょう。これらのたとえによって主イエスが、私が宣べ伝えている天の国は、つまり神の救いは、今はからし種のように小さいが、やがては見上げるような木になる、パン種が少量でも粉全体を膨らませるように、この世界全体に影響を及ぼしていくのだ、と語られたのだと思った人がいたとしても、その人々はよくて半信半疑、たいていの人は「何を夢のようなたわ言を言っているんだ」としか思わなかったでしょう。つまりこれらのたとえ話は、当時の人々にとって、決してわかりやすい、なるほどと感じられるようなものではなかったのです。むしろ何を言っているのかよく分からない、というのが、これを聞いた人々の反応だったのではないでしょうか。そしてそのことは、実は、私たちにおいても同じなのではないでしょうか。
天の国、神のご支配のたとえ
この二つのたとえはいずれも、「天の国はこれこれに似ている」と語り始められています。それは24節以下の「毒麦のたとえ」も同じでした。その時にも申しましたが、「天の国」というのは、死んだ後行く「天国」のことではありません。これは「神のご支配」という意味の言葉です。神のご支配が私たちの上に、この世界に確立する、それが私たちの救いなのです。ですから「天の国はこのようなものだ」というのは、神の救いとはこのようなもので、このように実現する、ということです。神の救いは、からし種のように、あるいはパン種のように私たちに与えられる、と主イエスはおっしゃったのです。
私たちの現実は
天の国、即ち神のご支配、つまり救いが、私たちに実現するとは、私たちの上に神のご支配が確立すること、私たちが神のご支配を信じ受け入れ、それに服する者となることです。それによって神の救いは私たちの現実となるのです。そのことのしるしが洗礼です。洗礼を受けて教会の群れに加えられるというのは、天の国、神のご支配が主イエスによって実現していることを信じてそれを受け入れ、その神のご支配に従って生きる者となることです。先週のイースターの礼拝において、三名の方々がその洗礼を受けて教会に加えられました。三名同時の成人の洗礼はかなり久しぶりで、本当に嬉しいことですが、それは裏を返せば、洗礼を受ける人がいかに少ないか、ということでもあります。主イエスの父である神のご支配を信じ受け入れて洗礼を受ける人は、今この日本において、本当に少ないのです。それが私たちの置かれている現実です。つまり、二千年前に蒔かれたからし種が、今は見上げるような木になっている、とは言えないような現実を私たちは生きているのです。主イエス・キリストというからし種は、本当に鳥が巣を作ることができるような大木となっているのか、主イエス・キリストというパン種は、この世界全体に本当に良い影響を与え、おいしいパンへと膨らませているのか、私たちにとってもそれは半信半疑のことであり、ともすれば、そんなことは大ぶろしきのたわ言だと感じずにはおれないような現実の中に私たちはいるのではないでしょうか。つまり私たちは、この二千年の世界全体の歴史を見つめるならば、これらのたとえによって語られたことがある意味で実現している、と言うことができますが、私たちの置かれている現実においては、これらのたとえが実現しているとはとても感じられないのです。
天の国は、小さなからし種から始まる
しかしここではっきり言っておきたいことがあります。主イエス・キリストがこれらのたとえによって語っておられるのは、「私の教えは今は吹けば飛ぶような小さなものだが、やがて大きな木となり、世界全体に影響を及ぼすようになるのだ」ということではありません。いや、そういうことも含まれてはいます。しかしそういう「今に見ていろ」みたいなことがこのたとえの中心ではないのです。このたとえから私たちが読み取らなければならない最も大事なことは、天の国は、つまり神のご支配は、即ち私たちの救いは、最初はからし種のように小さいということです。まさに吹けば飛ぶような、蒔かれたらもうどこにあるのかもわからなくなってしまうような、そんな小さな種から天の国は始まるのだ、ということです。天の国は、神の国、神のご支配なのですから、それが鳥が巣を作るほど大きな木にたとえられるのはむしろ当然です。そうでなければ天の国とは言えないでしょう。つまりこのたとえが語ろうとしているのは、天の国は大きな木となる、ということではなくて、その大きな木である天の国が、あのように小さな、目立たないからし種から始まるのだ、ということなのです。それはただ最初は小さい、ということだけを言っているのではありません。パン種のたとえがそこで生きてきます。パン種は生地に混ぜられると、もう見えなくなるのです。どこにあるのかわからなくなるのです。隠されてしまうのです。33節に「女がこれを取って三サトンの粉に混ぜると」とある、その「混ぜる」という言葉は、「隠す」という意味でもあります。パン種は生地の中に隠されるが、その隠されたものが全体を膨らませていくのです。天の国、神のご支配もこのように隠されている、「ここにある、あそこにある」と見えるものではないのです。だから、そんなもの本当にあるのか、と疑えばいくらでも疑えるのです。しかしその今は隠されている神の国、神のご支配が、確実に力を発揮して、私たちを、この世界を大きく変えていく、天の国はそのような力を秘めたものなのだ、ということをこのたとえは語っているのです。
天の国の秘密
このようにこれらのたとえは、天の国は、神のご支配は、今は隠されている、ということを語っているのです。そしてこのことは、主イエスが天の国のことをたとえによって語られた理由とも繋がっています。13章の10節以下で、なぜたとえを用いて語るのか、という問いに対して主イエスはこうおっしゃいました。「あなたがたには天の国の秘密を悟ることが許されているが、あの人たちには許されていないからである。持っている人は更に与えられて豊かになるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられる。だから、彼らにはたとえを用いて話すのだ。見ても見ず、聞いても聞かず、理解できないからである」。つまり、たとえで語るのは、難しいことを誰もが分かるように説明するためではないのです。たとえが語っているのは「天の国の秘密」であり、それを悟ることが許されているいる人と許されていない人がいるのです。つまり、分かる人には分かるが、分からない人にはますます分からなくなる、それが主イエスのたとえです。ですからそれは「謎かけ」と言い換えてもいいものです。隠されている答えが分かる人には、謎全体がよく分かるのです。しかし分からない人には、謎は謎のままで、いったい何を言っているのか、ちんぷんかんぷんなのです。そのように主イエスのたとえは、事柄を明らかにする働きと隠す働きを同時にしています。天の国のことがそのようなたとえによって語られるのは、天の国、神のご支配そのものが、隠されているからです。それは説明されれば誰でもわかるものではないし、証拠をあげて証明してみせることができるものでもないのです。隠されているものは、隠されているものとして語るしかないのです。本日のところの34節以下に語られているのもそのことでしょう。「イエスはこれらのことをみな、たとえを用いて群衆に語られ、たとえを用いないでは何も語られなかった。それは、預言者を通して言われていたことが実現するためであった。『わたしは口を開いてたとえを用い、天地創造の時から隠されていたことを告げる』」。「天地創造の時から隠されていたこと」、それが天の国、神のご支配です。それを語るのに一番ふさわしい手段が、たとえだったのです。
私たちの信仰と礼拝を支えているもの
天の国、神のご支配、私たちの救いは、私たちにも隠されています。二千年前は隠されていたが、今は顕わになっている、というわけではありません。二千年前と今とを比べれば、確かに今は、全世界に教会が存在しており、キリストを救い主と信じている人も世界中に何億人とおり、キリスト教がこの世界に大きな影響を及ぼしています。それは二千年前には考えられなかったことです。しかし果してこの世界は、人間は、それによって大きく変わり、神の国、神のご支配に服するようになったでしょうか。むしろいろいろな技術が進んだだけ、人間の罪の及ぼす影響が大きくなり、より悲惨な出来事が頻繁に起こるようになっていると言わなければならないでしょう。私たちの心に根深く巣食う罪、妬みや憎しみ、自分の欲望の実現ばかりを追い求める心はむしろより大きくなっているのではないでしょうか。人間の罪とそれによる悲惨な現実に覆われたこの世界のどこに、天の国、神のご支配などあるか、そんなものは人間の願望が生み出したたわ言ではないのか、と思わずにはおれません。そういう現実の中で、天の国、神の支配などというありもしないものを見つめるよりも、目の前の現実の問題に取組むべきだ、という声が、私たちの外からも内からも起ってくるのです。私たちは先週のイースターに、主イエス・キリストの復活を喜び祝いました。しかしイースターをどんなに盛大に祝ったところで、私たちの、またこの世の罪に満ちた悲惨な現実が変わるわけではありません。それぞれが個人的に抱えている様々な苦しみ、悲しみ、心配が無くなるわけでもありません。そのような中で、私たちの信仰が、イースターの祝いが、本当に意味あるものとなるためには、ここに語られているからし種のたとえ、パン種のたとえをしっかり受け止めることが大事なのです。つまり、天の国、神のご支配は、二千年前も今も、からし種のように小さくて、パン種のように隠されている、しかし、この天の国、神のご支配は必ず大きな木となり、私たちとこの世界を大きく変えていくのだ、ということです。主イエス・キリストがこの世に来られ、十字架の死に至るご生涯を歩まれ、そして復活なさったことは、この世界に、私たちの心に、まことに小さなからし種が、パン種が蒔かれたということです。この種は、本当に小さな、吹けば飛ぶようなもので、これが蒔かれたところでこの世界がどうなるものでもない、何の力も、影響もない、と思われるようなものです。私たちのこの礼拝も、一歩教会の外に出れば、世界は、そんなこととは関わりなく、関心もなく、動いているのです。しかし私たちには今、このたとえによって、神の国の秘密が示されました。この小さな、取るに足らない、目立たない種は、空の鳥が来て枝に巣を作るほど大きな木になるのです。このパン種が私たちの心という、またこの世界という、まことに頑なな粉の塊を、やわらかく発酵させ、よい香を放つおいしいパンにしていくのです。そのために、からし種は蒔かれてその姿を失っていきます。パン種も粉の中に混ぜられ、隠されて、見えなくなります。どちらも、自らの姿を失い、消えうせていくのです。そのことを通して、大きな木が育っていき、おいしいパンが膨らんでいくのです。それは、主イエス・キリストが、十字架にかかって死んで下さったことを象徴しています。主イエスがからし種として、パン種としてこの世に蒔かれたというのは、ただこの世に来られたというだけではなくて、私たちのために、私たちの罪を全て背負って十字架にかかって死んで下さったことを意味しています。ヨハネ福音書の12章24節に「一粒の麦は、地に落ちて死ななければ、一粒のままである。だが、死ねば、多くの実を結ぶ」と言われているのはそのことです。天の国、神のご支配は、この主イエスの十字架の死を通して、私たちの中に既に蒔かれ、育っているのです。そのことの一つの現れが、私たちが神のご支配を信じて、洗礼を受け、教会に加えられることです。そのようにして天の国、神のご支配は、私たちの中にも蒔かれ、成長し始めているのです。それはやがていつか、鳥が巣を作るような大木となります。粉の全体を脹らませ、おいしいパンにします。神によって造られたこの世界に、主イエスの父である神のご支配が完成し、私たちの救いも完成するのです。そのことを、私たちはまだ見てはいません。私たちが今目にしているのは、小さなからし種であり、ひとつまみのパン種です。しかしそれは天の国の、神のご支配の種です。それは神によって必ず、大きな木へと成長させられていくし、私たちとこの世界全体とを、み心に叶うものへと変えていくのです。私たちの信仰と礼拝を支えているのは、この約束であり、これらのたとえはその約束を告げているのです。
涙と共に種を蒔く人は
私たちは、この礼拝において、天の国、主イエス・キリストによって成し遂げられた神の恵みのご支配、私たちの救いを、からし種として、パン種として心に蒔かれて、そしてそれぞれの生活へと、この世へと遣わされていきます。この世は、主イエスによって実現している救いを意識しておらず、それとは全く別の思いによって営まれています。この世においては、神のご支配は隠されていて見えず、ただ信仰によってそれを受け止めるしかありません。しかし私たちはそこで希望を失うことはありません。神のご支配は、独り子主イエスの誕生と、十字架の死、そして復活と昇天を通して、確実に私たちに与えられ進展しているのです。その揺るぎ無い希望がこのたとえによって示されています。私たちはこの礼拝においてそのみ言葉を聞いて、それぞれの生活へと旅立っていくのです。その時、本日共に読まれた詩編126編が、私たちの信仰の歌となります。他国に捕え移されている捕囚の苦しみの中で、何の希望も見出せないように見える現実の中で、神の救いの約束、捕囚からの帰還を告げる言葉を聞いて、そこに希望を見出し、喜ぶ歌です。
主がシオンの捕われ人を連れ帰られると聞いて、わたしたちは夢を見ている人のようになった。そのときには、わたしたちの口に笑いが、舌に喜びの歌が満ちるであろう。そのときには、国々も言うであろう「主はこの人々に、大きな業を成し遂げられた」と。
主よ、わたしたちのために大きな業を成し遂げてください。わたしたちは喜び祝うでしょう。主よ、ネゲブに川の流れを導くかのように、わたしたちの捕われ人を連れ帰ってください。
涙と共に種を蒔く人は、喜びの歌と共に刈り入れる。
種の袋を背負い、泣きながら出て行った人は、束ねた穂を背負い、喜びの歌をうたいながら帰ってくる。
「涙と共に種を蒔く」「種の袋を背負い、泣きながら出て行く」それが私たちの信仰の現実です。そこには、将来この種が大きな木になり、空の鳥が来て枝に巣を作るほどになることは全く見えていません。しかし主は、「からし種」と「パン種」のたとえによって、その私たちが、「喜びの歌と共に刈り入れる」ことを、「束ねた穂を背負い、喜びの歌をうたいながら帰ってくる」ことを、約束して下さっているのです。天地創造の時から隠されており、しかし必ず実現する神の国、神のご支配を信じて、その希望に支えられて、私たちは今週も、自分に託されている種の袋を背負って種蒔きに出かけて行くのです。