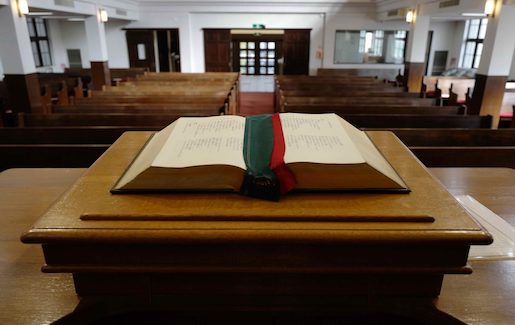説教「墓に葬られる」 副牧師 川嶋章弘
旧約聖書 イザヤ書第53章1-12節
新約聖書 ルカによる福音書第23章50-56a節
主イエスの十字架の出来事と共に
主イエス・キリストの苦しみと十字架の死を覚えるレント(受難節)を歩んでいます。来週の主の日は、教会の暦では「棕櫚の主日」と呼ばれ、この日から受難週が始まり、主イエスの地上のご生涯の最後の一週間を覚えます。夕礼拝ではルカによる福音書を読み進めてきて、このレントの期間にルカ福音書が語る主イエスの十字架の場面の一つひとつを深く味わってきました。主イエスの十字架の出来事と共にこのレントを歩んできたのです。先週の箇所で、ついに主イエスは十字架上で息を引き取られました。そして本日の箇所で、そのご遺体が墓に葬られます。受難週の出来事は、主イエスの十字架の出来事は、主イエスの死で終わるのではありません。主イエスの埋葬が続きます。このことは、どの福音書も、視点の違いがありながらも、主イエスの十字架の死を語った後に、そのご遺体が墓に葬られたことを語っていることからも分かります。主イエスの埋葬は、主イエスの十字架の出来事において欠かすことができないのです。
アリマタヤのヨセフ
さて、主イエスの埋葬において一人の人物が登場します。アリマタヤという町の出身のヨセフという人物です。50、51節にこのようにあります。「さて、ヨセフという議員がいたが、善良な正しい人で、同僚の決議や行動には同意しなかった。ユダヤ人の町アリマタヤの出身で、神の国を待ち望んでいたのである」。ヨセフはユダヤ人で、アリマタヤの出身でした。アリマタヤの確実な場所は特定されていませんが、おそらくサムエル記上1章1節に出てくる「エフライムの山地ラマタイム・ツォフィム」ではないかと考えられています。このラマタイム・ツォフィムは、あのサムエルの誕生の地で、エルサレムから北西に直線距離で30キロメートルのところにあります。聖書の後ろにある付録の聖書地図6「新約時代のパレスチナ」にもその位置に、アリマタヤと記されています。おそらくヨセフの先祖がこのアリマタヤに住んでいたのでしょう。もしかするとヨセフ自身もアリマタヤで生まれたのかもしれません。しかし本日の箇所を読み進めると分かるように、彼はエルサレムに自分の墓を持っていましたから、おそらくエルサレムで暮らしていたのだと思います。また、後々生まれ故郷に帰ろうと思っていたのではなく、死ぬまで首都エルサレムで過ごそうと思っていたはずです。だから自分の墓をエルサレムに準備したのです。現代の日本社会でも似たようなことは起こります。私自身は地方から出てきたわけではありませんが、私の祖父は地方から東京に出てきて、それから神奈川に引っ越し、そこで地上の生涯を終えました。そのためある時点で、自分たちの墓をこちらに造りました。アリマタヤのヨセフと同じように、祖父も故郷に帰ることはまったく考えていなかったので、自分たちが死んだ後のことを考えて墓を準備したのです。似たような経験をされている方は少なくないのではないでしょうか。日本社会にあって私たちは、自分や家族の墓の問題で頭を悩ますことも多いのですが、いずれにしても墓を準備することは死に備えることです。アリマタヤのヨセフの年齢は分かりませんが、ある程度、今後の人生が見通せるような年齢であり、また自分の死を意識するような年齢であったのだと思います。彼は自分の死に備えて、自分の墓を準備していたのです。
同僚の決議や行動に同意しなかった
このヨセフは議員であった、と言われています。それは、ユダヤ教の最高法院の議員であった、ということです。彼は「同僚の決議や行動には同意しなかった」とも言われています。これまでお話ししてきたように、主イエスは捕らえられ、ユダヤ教の最高法院で裁判を受けました。22章66~71節で、その最高法院の場面が語られています。そこで議員たちは、主イエスが神の子を自称し、神を冒瀆しているとして、かなり強引に主イエスの死刑を決議しました。もっとも最高法院は死刑を執行することができなかったので、主イエスは総督ピラトのもとに連れて行かれたのです。しかしヨセフは最高法院の議員の一人であったにもかかわらず、この強引な決議に同意していませんでした。決議だけでなく、ほかの議員たちが主イエスに対して取った行動全体に同意していませんでした。だから「同僚の決議」だけでなく、その「行動」にも「同意しなかった」と言われているのです。議員たちの「行動」というのは、なにか特定の行動、特定の行為を指しているというより、主イエスの逮捕に始まり、最高法院における裁判、総督ピラトのもとへの移送、そして主イエスの処刑に至る、その全体を指しているのでしょう。ほかの議員たちの主イエスに対する行動、その計画と決定のすべてに同意していなかったのです。
神の国を待ち望んでいた
そのようにヨセフが同僚の決議や行動に同意しなかったのは、彼が「神の国を待ち望んでいた」からだ、と説明されています。実は、ルカ福音書の初めに、ヨセフと同じように「正しい人」と呼ばれている人物が登場していました。場所も同じエルサレムです。2章25、26節にこのようにあります。「そのとき、エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい人で信仰があつく、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていた。そして、主が遣わすメシアに会うまでは決して死なない、とのお告げを聖霊から受けていた」。そしてシメオンは神殿で幼子イエスと出会ったのです。主イエスの地上の生涯の始まりにシメオンがいて、その終わりにはアリマタヤのヨセフがいます。どちらも「正しい人」であり、神の国を待ち望み、イスラエルの慰められるのを待ち望んでいました。ヨセフは主イエスによって神の国、神のご支配が実現し、自分自身が、またイスラエルの民が慰めを与えられると信じていたのです。ですから彼も主イエスを信じ、主イエスに従った者の一人であった、と言えるでしょう。ガリラヤから主イエスと共に過ごしてきたわけではなかったとしても、彼もまた主イエスの弟子の一人であり、主イエスの十字架の死に立ち会い、その遺体を葬ったのです。
無力感と失望に直面した
しかしそれは、ヨセフが立派な弟子であった、ということではないでしょう。確かにペトロを始めとする十一人はここにいません。ガリラヤから主イエスに従って来た女性の弟子たちは、遠くから見守っているだけです。なによりヨセフは最高法院で、イエスに敵対するほかの多くの議員たちの中で、正しさを貫いた立派な人物であったようにも思えます。しかし本当にそうなのでしょうか。ヨセフは確かにほかの議員たちの決議や行動に同意してはいませんでしたが、しかし彼らの決議に反対し、その行動を押し止めようと抵抗した、というわけではないでしょう。同意はしていなくても、圧倒的多数の意見に従わざるを得なかった、その行動を認めざるを得なかったのではないでしょうか。ヨセフは正しさを貫いたというより、むしろ正しさを貫けなかった、その自分の無力さに直面していたのです。主イエスによる神のご支配の実現を待ち望んでいたのに、その主イエスが十字架で処刑されることに対して、自分が何もできなかった無力感を味わっていたのです。私たちもヨセフと同じような経験をすることがあります。これは間違っているのではないか、と思うことに直面したとき、反対意見を述べたり、その間違いを正す行動を取れることもあるかもしれません。しかし多くの場合、私たちはなかなか反対意見を述べることができなかったり、間違いを正す行動を控えざるを得なかったりするのです。状況が許さないということがあります。私たちの弱さのためでもあります。私たちもヨセフと同じように、多数の意見に従わざるを得なかったり、その行動を認めざるを得なかったりするのです。アリマタヤのヨセフは立派な弟子ではなく、状況のゆえに、あるいは自分の弱さのゆえに正しさを貫くことができず、自分の無力さに直面している弟子であり、ほからならぬ私たちの姿であると思うのです。またヨセフの姿は大切な人の死に対して無力な私たちの姿でもあります。ヨセフにとって主イエスは大切な師、先生でした。愛していたと言ってもよい。だからほかの多くの議員たちに同調しなかったのです。しかしそれでも彼が主イエスの死に対してできたことは何もありませんでした。ヨセフも、そして私たちも大切な人の死の前に全くの無力なのです。それだけではありません。主イエスの死は、彼にとって、主イエスによる神のご支配の実現が叶わなかった、ということを意味します。神の国を待ち望んでいた、その望みが、その希望がついえた、ということを意味するのです。ヨセフは自分の無力さと、自分の希望がついえた深い失望に直面していたのです。
主イエスの埋葬を願い出る
その無力感と深い失望の中で、ヨセフはせめて主イエスの遺体を埋葬しようとしました。そのようにヨセフが思ったのは、旧約聖書の律法によれば、木にかけられた死体は、その日のうちに埋めなければならなかったからです。申命記21章22、23節にこのようにあります。「ある人が死刑に当たる罪を犯して処刑され、あなたがその人を木にかけるならば、死体を木にかけたまま夜を過ごすことなく、必ずその日のうちに埋めねばならない。木にかけられた者は、神に呪われたものだからである。あなたは、あなたの神、主が嗣業として与えられる土地を汚してはならない」。ユダヤ人の律法ではこのように定められていましたが、他方ローマの法によれば、死刑に処せられた者は埋葬されないことになっていたようです。それゆえヨセフは、「ピラトのところに行き、イエスの遺体を渡してくれるようにと願い出」たのです。マルコ福音書はこの箇所で、ヨセフが「勇気を出してピラトのところへ行き、イエスの遺体を渡してくれるようにと願い出た」(15章43節)と記しています。ローマの法に従うのではなく、律法に従って主イエスを埋葬したい、と総督ピラトに願い出るのは、確かに勇気が必要だったに違いありません。けれどもヨセフは、単に律法を守るためだけに、あるいは主イエスが十字架に架けられたままではかわいそうだ、申し訳ないという気持ちのゆえに、主イエスの遺体を渡してくれるよう願い出たのではないと思います。ヨセフは無力感と深い失望の中にあって、律法に従って主イエスを埋葬することで、主イエスの死を認め、受け入れようとしたのではないでしょうか。それは、私たちにとっても同じです。私たちが家族や友人や知人、大切な人を葬ることは、その人の死を認め、受け入れる営みなのです。
主イエスの埋葬
しかし主イエスの埋葬は、時間がない中での慌ただしい埋葬でした。54節にあるように、「その日は準備の日であり、安息日が始まろうとしていた」からです。「準備の日」とは安息日の前日、金曜日のことです。ユダヤの一日は日没から始まるので、「金曜日の日没、安息日である土曜日が始まる夕方になろうとしていた」と言われていることになります。44節によれば、主イエスが十字架で死なれたのは金曜日の午後3時のことでした。ですからヨセフは、午後3時から日没までの短い時間の間に主イエスを埋葬しなくてはならなかったのです。それでも彼は、53節にあるように主イエスの「遺体を十字架から降ろして亜麻布で包み、まだだれも葬られたことのない、岩に掘った墓の中に納め」ました。当時のユダヤでは、岩を掘って墓を造り、そこに遺体を納めましたが、一人だけではなく、何人かの遺体を納めることができる墓もあったようです。「まだだれも葬られたことのない」というのは、新しい墓であったということです。ほかの誰かが持っている新しい墓ではないでしょう。そこに勝手に十字架で処刑された人を入れられるはずがないからです。ですからこの墓はヨセフ自身の墓であったに違いありません。マタイ福音書には「自分の新しい墓」(27章60節)と記されています。ヨセフは自分のために造った墓に、自分がいずれ入ることになる墓に、主イエスのご遺体をお納めしたのです。本来であれば、遺体の腐敗を防ぐために、遺体に香油を塗り、香料を添えてから亜麻布で包んで埋葬する必要がありました。しかしそれらを準備する時間がなかったので、ヨセフは亜麻布に包んだだけで、主イエスの遺体を葬ったのです。時間がない中で、無力感と深い失望の中で、ヨセフはこのようにして主イエスを葬りました。その葬りの営みを通して、主イエスの死を認め、受け入れようとしたのです。
主イエスの埋葬を見届ける
さて、この主イエスの埋葬を見ていた人たちがいました。55、56節にこのようにあります。「イエスと一緒にガリラヤから来た婦人たちは、ヨセフの後について行き、墓と、イエスの遺体が納められている有様とを見届け、家に帰って、香料と香油を準備した」。49節には、「ガリラヤから従って来た婦人たちとは遠くに立って、これらのことを見ていた」とありました。ガリラヤから主イエスに従って来た女性の弟子たちは、「遠くに立って」、主イエスが十字架で死なれるのを見つめ、その後も、そこに留まり続けました。そしてアリマタヤのヨセフが主イエスの遺体を引き取るのを見て、ヨセフの後について行き、主イエスの埋葬を見届けたのです。「見届けた」と訳された言葉は、ボーッと眺めるのではなく、「注意して見る」ことを意味します。彼女たちが注意して見ていたのは、主イエスが葬られた墓と、どのようにして主イエスがその墓に葬られたか、でした。墓を注意して見ていたのは、どこが主イエスの墓なのか、どこに主イエスが葬られたのかを確認するためです。彼女たちは安息日が終わったら主イエスの墓を訪れようと考えていました。だから主イエスの墓の場所をしっかり確認しておく必要があったのです。彼女たちがそのように考えていたのは、どのようにして主イエスが墓に葬られたかを注意して見ていたからこそです。彼女たちはヨセフが、主イエスの遺体に香油を塗ることができず、香料を添えることができなかったのを見て、安息日が終わったら、自分たちが主イエスの遺体に香油を塗ろうと、香料を添えようと思っていたのです。だから彼女たちは、56節にあるように家に帰ると、「香料と香油を準備し」ました。この女性の弟子たちもまた、主イエスを失った深い悲しみと嘆きの中で、主イエスを葬ることを通して、主イエスの死を認め、受け入れようとしていたのです。
墓に葬られる
このように主イエスが墓に葬られたことは、何を意味しているのでしょうか。それは、主イエスが本当に死なれたことを意味しています。この後の24章で語られるように、安息日が終わって週の初めの日に、主イエスは復活されます。その主イエスの復活は、仮死状態からの蘇生などではなく、本当に死からの復活であったのです。主イエスが死んで、墓に葬られたことによって、主イエスの復活が、真実に死からの復活であったこと、真実に死への勝利であったことを告げているのです。そして主イエスが死なれ、墓に葬られたことは、私たちにとってまことに大きな慰めです。私たちも数十年の地上の生涯を終えて、死を迎え、墓に葬られます。しかしそのすべては、すでに主イエスが経験してくださったことです。私たちの死は、すでに主イエスが死んでくださった死です。私たちの葬りは、すでに主イエスが経験してくださった葬りです。私たちは主イエスと無関係に死を迎え、墓に葬られることはないのです。
すでに主イエスが葬られ、復活された墓に
アリマタヤのヨセフはまさにこのことを経験したに違いありません。彼もやがて地上の生涯を終えて、死を迎え、自分が準備していたあの墓に葬られたことでしょう。しかしヨセフにとって、そのことの意味は、自分のために新しい墓を造ったときとは、まったく異なっていたのです。墓を造ったとき彼は、死はすべての終わりであると、墓はその象徴であると考えていました。自分の墓を準備することは、ただ自分の死を意識するだけのことでしかなかったはずです。けれどもヨセフが実際に死を迎え、墓に葬られたとき、その墓は、すでに主イエスが葬られ、そして復活された墓であったのです。まさに主イエスが葬られ、復活された墓に、ヨセフは葬られたのです。そうであればヨセフにとって、死はもはやすべての終わりではありません。墓に葬られることも、もはやその象徴ではありません。地上の生涯を終えて、死んで、墓に葬られても、それで終わりではない。主イエスが死んで、葬られ、しかし復活されたように、ヨセフも世の終わりに復活させられ、彼自身が待ち望んでいた神のご支配の完成にあずかり、まことの慰めを与えられるのです。ヨセフはこのことに希望を置いて生きることができ、また死を迎えることができるようになったのです。
私たちもヨセフと同じです。私たちが葬られる墓は、主イエスが葬られ、復活された墓そのものではありません。しかし私たちが墓に葬られることの意味は、ヨセフとなんら変わりません。私たちが死んで葬られるその墓は、すでに主イエスが葬られ、しかし復活されたところ、そう言って良いのです。ヨセフは主イエスの復活の後に、自分の墓を見る目が変わったに違いありません。私たちも主イエスが墓に葬られ、しかし復活されたことによって、自分の墓を、あるいは大切な人の墓を見る目が変わります。その墓が、死がすべての終わりであることの象徴だ、と思うことはもはやありません。ましてその墓が、私たちの「終の住処」だ、と思うことも決してありません。そうではなく私たちは、自分自身や大切な人の墓を見るとき、墓に葬られ、しかし復活された主イエス・キリストを思うのです。そしてすでに死んだ者たちにも、これから死ぬ者たちにも、主イエスが復活されたように世の終わりに復活させられて、神のご支配の完成とまことの慰めにあずかる約束が与えられていることに目を向けるのです。この約束に希望をおいて、この約束が与える慰めと平安の内に、私たちは生きることができるし、死ぬことができます。あのシメオンは、「主よ、今こそあなたは、お言葉どおり この僕を安らかに去らせてくださいます。わたしはこの目であなたの救いを見たからです」(2章29、30節)と神様を賛美しました。主イエスの十字架と復活による救いにあずかり、主イエスに結ばれて生きる私たちも、「この僕を安らかに去らせてくださいます」という確信を与えられて死を迎えることができるのです。
悲しみと嘆きの中にある慰めと希望
だから私たちにとって葬りの営みは、その人の死を認め、受け入れるためだけのものではありません。確かに大切な人の死は、地上における大切な人との別れは、私たちに言葉にならない悲しみと嘆き、喪失感をもたらします。しかしなおその深い悲しみと嘆き、喪失感の中で、私たちは主イエスが十字架で死なれ、墓に葬られ、しかし復活されたことを見つめます。主イエスの十字架と復活によって与えられている、世の終わりの復活と永遠の命の約束を見つめるのです。そのことを通して、私たちは深い悲しみと嘆きの中にあってなお、大きな慰めと希望を与えられます。家族や友人や知人、大切な人を葬ることを通して、私たちは単にその人の死を認め、受け入れるだけでなく、主イエスによるこの大きな慰めと希望にあずかることができるのです。アリマタヤのヨセフは、自分の無力さの中で、自分の希望がついえた深い失望の中で、主イエスを埋葬しました。しかし神様はそのヨセフを用いて、救いのみ業を前進させてくださいました。ヨセフが神のご支配の実現がついえたと思ったまさにそこで、神様は主イエスを復活させることによって、そのご支配を実現してくだったのです。そしてヨセフは、主イエスの復活によって、決して失われることのない本当の希望を与えられたのです。死んで、墓に葬られて、それで終わりではない。世の終わりに復活させられ、神のご支配の完成にあずかる。この失われることのない希望を与えられたのです。私たちも葬りの営みを通して、この希望を与えられます。大切な人の死に対する自分の無力さに直面する中で、深い喪失の悲しみを味わう中で、この希望を与えられ、慰めを与えられるのです。
これから聖餐にあずかります。聖餐において私たちは、主イエスが十字架で死んで、墓に葬られ、復活されたことによって、私たちが失われることのない希望と慰めの内に地上の生涯を歩み、そして死を迎えることができる、その計り知れない救いの恵みを体全体で味わうのです。