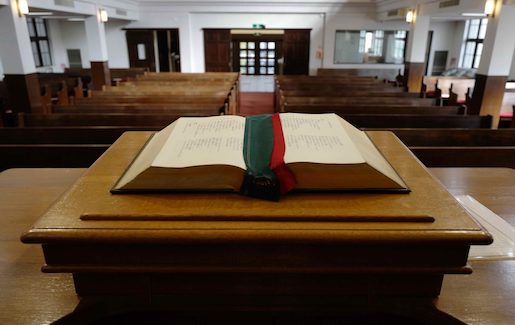説 教 「父よ、彼らをお赦しください」副牧師 川嶋章弘
旧 約 詩編第22編1-9節
新 約 ルカによる福音書第23章32-38節
受難節に主イエスの十字架の場面を読み進める
先々週の水曜日5日から受難節(レント)に入りました。今年は4月20日がキリストのご復活を祝うイースターです。それまでの期間(日曜日を除いて40日間)、この受難節に、私たちは主イエス・キリストが苦しみを受けられ、十字架で死なれたことを覚え、そしてその十字架の死の先にあるキリストの復活を見つめつつ過ごしていきたいと願います。しかしそう願いつつも、私たちはまことに弱い者であり、自分勝手な者であることを思わないわけにはいきません。慌ただしい日々の中にあって、私たちは受難節であっても、主イエスの十字架の死を忘れてしまうことがあります。そもそも受難節であることすら忘れてしまうこともあります。主イエスの十字架の死に目を向けるより、自分がやらなければいけないことばかりに目を向け、また自分の苦しみや悲しみ、あるいは喜びや楽しみばかりに目を向けてしまいます。キリストの十字架を見失い、軽んじてしまうのです。そのように受難節であってもなかなか主イエスの十字架に目を向けようとしない私たちに、まことにふさわしい聖書箇所が与えられています。この夕礼拝では私が担当するときはルカによる福音書を読み進めてきました。そして今、まさに主イエスの十字架の場面を読み進めています。前回は、主イエスが十字架に架けられる刑場へと連れて行かれる場面を読みました。本日は主イエスが十字架に架けられる場面を読みます。そして来週は、主イエスが十字架に架けられている最中(さなか)での場面、再来週は、主イエスが十字架上で息を引き取られる場面、さらにその次の週は、主イエスが墓に葬られる場面を読む予定です。この受難節に、夕礼拝では主イエスの十字架の場面をじっくり読み進めていくことができます。聖霊のお働きによって受難節を歩む私たちにまことにふさわしい聖書箇所が与えられているのです。
二人の犯罪人を左右にして
さて、本日の箇所に目を向けていきます。主イエスは十字架につけられる刑場へと引いて行かれました。しかし主イエスお一人が引いて行かれたのではありません。32節に「ほかにも、二人の犯罪人が、イエスと一緒に死刑にされるために、引かれて行った」とあります。続く33節には、「『されこうべ』と呼ばれている所に来ると、そこで人々はイエスを十字架につけた。犯罪人も、一人は右に一人は左に、十字架につけた」とあります。主イエスは「されこうべ」のような形をした丘の上で十字架につけられました。その左と右で二人の犯罪人も十字架につけられました。主イエスの頭の上には、十字架のてっぺんには、38節にあるように、「これはユダヤ人の王」と書いた札も掲げられました。この札は主イエスの罪状を記しています。主イエスはユダヤ人の王を語った罪で十字架刑に処せられたのです。主イエスを中央にして、その左右で二人の犯罪人が十字架につけられたのも、王を自称した主イエスを侮辱するためであったのではないでしょうか。主イエスが王で、二人の犯罪人が王の左右に侍る家来であるかのように見せたのです。そのように見せておきながら、しかし実際のところは、主イエスは二人の犯罪人に囲まれているに過ぎません。王を自称したけれど、実際は犯罪人の一人に過ぎなかった、という主イエスに対する侮辱が、二人の犯罪人を左右にして主イエスを十字架につけたことに込められているのです。もっともこの主イエスの十字架刑を決めた総督ピラトは、主イエスがユダヤ人の王を自称したと考えていたわけではありません。主イエスが王を自称しているというユダヤ人宗教指導者たちの訴えは、自分たちの宗教的な権威を守るためだということを見抜いていたからです。しかしこれまで見てきたように宗教指導者だけでなく、民衆も主イエスを十字架につけろと要求し続けたために、ついにピラトはその要求を飲んだのです。人々からユダヤ人の王を自称していると訴えられ、しかし王と言えるような力を何ら持つことなく、無力の中で犯罪人の一人として十字架につけられることになった主イエスを、ピラトは侮辱してこのような形で主イエスを十字架につけたのです。
神のご計画が実現している
しかしこのピラトの侮辱のこもった仕打ちにおいて、神様のご計画が実現していることを見逃すわけにはいきません。主イエスは22章37節で、旧約聖書イザヤ書53章12節を引用して、このように言われていました。「言っておくが、『その人は犯罪人の一人に数えられた』と書かれていることは、わたしの身に必ず実現する」。この主イエスの言葉が、さらに言えば主イエスが引用した預言者イザヤの言葉が、ピラトによって実現します。イザヤは、「彼が自らをなげうち、死んで 罪人のひとりに数えられたからだ」と預言しました。この神様のご計画が、主イエスが「犯罪人の一人」として、「罪人のひとり」として十字架につけられて、死なれることによって実現するのです。ピラトの主イエスに対する侮辱が極まっているこの十字架刑において、しかし神様のご計画が実現しているのです。
それぞれの場面に主イエスの言葉がある
主イエスは十字架につけられるとこう言われました。34節の前半です。「父よ、彼らをお赦しください。自分が何をしているのか知らないのです」。ルカ福音書は主イエスの十字架上の言葉を三つ記していますが、その最初の言葉がこの言葉です。私たちがこの受難節に繰り返し聞いていきたい主イエスの言葉です。しかし聖書をよく見ると、34節前半が括弧で括られていることに気づきます。これは幾つかの有力な写本に34節前半がないことを示しています。そのためある人たちは、34節前半はもともとのルカ福音書にはなくて後から付け加えられたと考えます。しかし別の人たちは、34節前半はもともとのルカ福音書にあったけれど、後から削除されて、34節前半の欠けている写本が生じたと考えます。それぞれそのように考える理由があり、複雑な議論がなされています。私自身は34節前半をルカ福音書の一部として読むほうが良いと考えています。なぜなら34節前半はルカ福音書の構成において不可欠だと思うからです。ルカ福音書は主イエスの十字架の場面を段階的に語っています。まず主イエスが刑場に引かれて行く場面、次に主イエスが十字架に架けられる場面、次に主イエスが十字架に架けられている最中での場面、そして主イエスが十字架上で息を引き取られる場面です。そしてそれぞれの場面に主イエスの言葉が一つあります。前回見たように、主イエスは刑場に引かれて行く途中で、ご自分について来る女性たちに向かって、「わたしのために泣くな。むしろ、自分と自分の子供たちのために泣け」と言われました。また次回読みますが、十字架上で主イエスは犯罪人の一人に、「はっきり言っておくが、あなたは今日わたしと一緒に楽園にいる」と言われます。そして主イエスは十字架上で息を引き取られるとき、「父よ、わたしの霊を御手にゆだねます」と言われるのです。ですからもし34節前半がなかったとしたら、この場面だけ主イエスの言葉がないことになってしまいます。しかしそれはありそうにないことです。34節前半がルカ福音書の構成において不可欠だ、というのはそういうことです。
本当に問うべきこと
このように34節前半は、ルカ福音書の一部として読むほうが良いと思いますが、しかし本当の問題は、本当に問うべきことは別にあります。先ほど紹介した、34節前半が後から付け加えられたのか、それとも後から削除されたのかという議論は、結局、「父よ、彼らをお赦しください」の「彼ら」とは誰か、という議論に結びついています。詳しい議論は省きますが、「彼ら」がローマ人なら後から付け加えられたのであり、ユダヤ人なら後から削除されたと考えるのです。しかしそのように考えている内は、この十字架上の主イエスの言葉は他人事でしかありません。自分に関わりのある言葉として受けとめていないのです。このことは、たとえ私たちが34節前半をルカ福音書の一部として読んだとしても、他人事として読んでいるなら、34節前半が後から付け加えられたとか、後から削除されたとか、そのような議論している人たちと大して違わない、ということでもあります。「父よ、彼らをお赦しください」と主イエスが祈られたとき、その「彼ら」とは誰なのか。「自分が何をしているのかを知らないのです」と言われた「自分」とは誰なのか。私たちはそのことを真剣に問わなければならないのです。そのためにも私たちは、主イエスが十字架につけられたとき、そこに立ち会った人たちの姿を見ていきたいのです。
主イエスの十字架を無視する
34節の後半に「人々はくじを引いて、イエスの服を分け合った」とあります。「人々」というのは主イエスを十字架につけたローマの兵士たちのことです。当時、兵士たちが死刑囚の服を、「くじを引いて」分け合うのは習慣であったようです。主イエスは服を脱がされ、手と足に釘を打たれて十字架につけられました。その足元で兵士たちがくじを引いて、主イエスの服を分け合っています。すぐそばで十字架上の主イエスが血を流され、苦しまれているのに気にもとめません。十字架につけられた人の服までも自分のものにしようとする、その欲に駆られているのです。それは物欲というより名誉欲なのかもしれません。自分たちが十字架につけた人の服の一部を持っていることが、何らかの名誉であったのかもしれません。いずれにしても十字架につけられた主イエスの足元では、欲に駆られた兵士たちが、目の前の主イエスの十字架を見ようともせず、主イエスの服を分け合っていたのです。
私たちはなんてひどいことを、残酷なことをするのだろうと思います。いや、しかしこの兵士たちの姿は、私たちの姿なのではないでしょうか。私たちは受難節であってもしばしば主イエスの十字架を忘れます。「あれ今、受難節だったけ」と思うことすらあります。毎日、忙しいから。慌ただしいから。やらなければいけないことで一杯一杯だから。自分の喜びや楽しみを求めるので精一杯だから。あるいは自分の苦しみや悲しみを抑え込むので精一杯だから。だから私たちは主イエスの十字架を忘れてしまう。主イエスの十字架などないかのように生きてしまうのです。そのような私たちは、主イエスの十字架の足元で、主イエスの十字架を見ようとせず、自分の欲に駆られている兵士たちと何が違うのでしょうか。私たちこそ主イエスの十字架を無視して、自分の忙しさに、自分の欲や思いに心を奪われている者なのです。
神が遣わした救い主なら
35節にはこのようにあります。「民衆は立って見つめていた。議員たちも、あざ笑って言った。『他人を救ったのだ。もし神からのメシアで、選ばれた者なら、自分を救うがよい』」。主イエスの十字架に立ち会った民衆と議員たちの姿が描かれています。「民衆」は、数日前まで夢中になって主イエスを支持していたのに、主イエスが自分たちの期待に沿わないと分かると、手の平を返して、主イエスを「十字架につけろ、十字架につけろ」と叫び続けました。そのようにして主イエスを十字架刑に追い込んだ民衆は、実際に主イエスが十字架につけられるのを見物しようと思って、刑場に連れて行かれる主イエスについて来ました。民衆は「立って」、主イエスの十字架を「見つめて」いました。それは、主イエスの十字架を見つめて、心を痛めて沈黙していた、ということでないでしょう。むしろ民衆は心の中で主イエスをあざ笑っていたのではないでしょうか。彼ら彼女たちは、主イエスが自分たちをローマ帝国の支配から解放してくれると期待していました。それなのに主イエスは自分たちを解放するどころか、ローマ帝国によって十字架につけられてしまった。その無力な姿、無様な姿を見て、声には出さなくても心の中であざ笑っていたのです。議員たちは、「他人を救ったのだ。もし神からのメシアで、選ばれた者なら、自分を救うがよい」と主イエスをあざ笑いました。きっと民衆も心の中で同じようにあざ笑っていたに違いないのです。これまで多くの病人を癒し、時には死者をも甦らせて、人々を救ってきたのに、自分を救えない主イエスをあざ笑っていたのです。メシアはヘブライ語で「油を注がれた者」を意味し、やがて「救い主」を意味するようになりました。メシアをギリシア語にするとキリストになります。つまり民衆も議員たちも、「もし神によって油を注がれた者、選ばれた者なら、つまり神が遣わしたメシア、キリスト、救い主なら自分を救うがよい」とあざ笑ったのです。ユダヤ教の宗教指導者や民衆にとって、神が遣わしたメシア、救い主であるにもかかわらず自分を救えないというのは、滑稽なことでしかなかったからです。
ユダヤ人の王なら
ローマの兵士たちも同じように主イエスを侮辱しました。36節にこのようにあります。「兵士たちもイエスに近寄り、酸いぶどう酒を突きつけながら侮辱して、言った。『お前がユダヤ人の王なら、自分を救ってみろ』」。「酸いぶどう酒」は本来、痛み止めのために与えられるものですが、兵士たちはむしろ主イエスを侮辱してそれを突きつけました。そして「お前がユダヤ人の王なら、自分を救ってみろ」と言います。ローマの兵士たちにとって、主イエスが神の遣わしたメシア、救い主であるかどうかは関係ありません。それはユダヤ人の問題でした。それよりもユダヤ人の王であるかどうかが問題でした。「これはユダヤ人の王」と書いた札が掲げられたように、主イエスはユダヤ人の王を自称した罪で十字架につけられたのです。だから兵士たちは「お前がユダヤ人の王なら」と言います。「もしお前がユダヤ人の王だと言うなら、その王としての力を使って、自分を救ってみろ」と侮辱したのです。
私たちの姿
このように主イエスの十字架に立ち会った人たちは、誰も彼も主イエスをあざ笑い、侮辱しました。その中心にあるのは、「自分を救ってみろ」という嘲りです。「お前が救い主だと言うなら、お前が王だと言うなら、自分を救ってみろ」と、「自分自身を救えないのに、救い主のはずがない、王のはずがない」と侮辱しているのです。十字架につけられ血を流しながら苦しまれている主イエスに向かって、そのような言葉を投げつける。声に出して、あるいは心の中で侮辱し、あざ笑う。その情景を思い浮かべると目をそむけたくなります。まことにむごたらしい場面です。けれどもこの民衆や議員や兵士たちの姿も、私たちの姿なのではないでしょうか。私たちは自分の忙しさに心を奪われ、自分の思いに心を奪われているときは、主イエスの十字架を見ようとしません。しかし困難な現実に直面するとき、苦しみの中で主イエスに助けを求めて祈ります。その祈りが聞き届けられ、苦しみが取り除かれることもあるでしょう。しかしそうではないこともあります。そのとき私たちは主イエスに、「救い主のはずなのに、なぜ救ってくれないのか」という言葉を投げつけます。「苦しんでいる自分を助けてくれないのに、主イエスが救い主のはずがない」とすら思ってしまうのです。私たち一人ひとりの人生にも、この世界にも不条理な苦しみが満ちています。なぜ自分が苦しまなくてはならないのか。なぜこの世界に、戦争や災害や貧困といった不条理な苦しみが溢れているのか。主イエスがまことの王としてこの世界を支配しているなら、このようにはならないはずではないかと思い、主イエスは本当にまことの王なのだろうかと疑います。無力な姿で、無様な姿で十字架につけられて死なれた主イエスが、自分自身を救うことができなかった主イエスが、本当に救い主なのだろうかと疑い、信じられなくなるのです。私たちはまことに弱い者であり、自分勝手な者です。しばしば主イエスの十字架を無視し、しかし苦しみに直面すると主イエスに助けを求め、それなのに苦しみが取り除かれないと、もう主イエスを信じられないと思ってしまうのです。そのような私たちは、十字架につけられた主イエスに、「自分を救ってみろ」と言っている人たちと、そう違わないのではないでしょうか。主イエスの十字架の足元で、主イエスの十字架を見ようともせず、主イエスの服を分け合う兵士たちの姿も、十字架につけられた主イエスに向かって、「自分を救ってみろ」と侮辱し、あざ笑う者たちの姿も、ほかならぬ私たちの姿なのです。
私たちのための祈り
そのことを突きつけられるとき、私たちは「父よ、彼らをお赦しください。自分が何をしているのか知らないのです」という主イエスの祈りが、私たちのための祈りであったことに気づかされます。そうです。「父よ、彼らをお赦しください」の「彼ら」とは、「自分が何をしているのか知らないのです」と言われる「自分」とは、ほかならぬ私たちです。自分の思いや欲に心を奪われて主イエスの十字架を無視する私たちのために、苦しみの中で主イエスがまことの救い主、まことの王だと信じられなくなり、主イエスをあざ笑ってしまう私たちのために、「父よ、彼らをお赦しください」、と主イエスは執り成し祈ってくださったのです。そして主イエスは、この執り成しの祈りが聞き届けられるために、十字架で死んでくださったのです。
主イエスの十字架を見失う
主イエスは「自分が何をしているのか知らないのです」とも祈られました。私たちが「自分が何をしているのか知らない」としたら、それは主イエスの十字架を見失い、分からなくなっているからです。主イエスは自分を救えなかったのではなく、あえて自分を救おうとされませんでした。人々の侮辱や嘲りに反論するのではなく、それをすべて受けとめることによって、身体的にも精神的にも誰も味わったことのない苦しみを十字架上で味わってくださいました。そして私たちの罪をすべて背負って、私たちの代わりに十字架で死んでくださることによって、私たちの罪を赦し、私たちを救ってくださいました。主イエスはあえて自分を救わないことで、私たちを救ってくださったのです。十字架上で苦しみを味わい尽くしてくださった主イエスは、苦しみの中にある私たちと共にいてくださり、私たちの苦しみを共に負ってくださいます。十字架上で誰も味わうことのない苦しみを味わってくださった主イエスが共にいてくださるから、私たちはどのような苦しみの中にあっても絶望せずに生きることができるのです。このことのために主イエスはあえて自分を救うことなく、十字架で苦しみを受けて死なれたのです。私たちはしばしばこのことを見失い、分からなくなり、主イエスの十字架を無視し、軽んじてしまうのです。
父よ、彼らをお赦しください
共に読まれた旧約聖書詩編22編8、9節にこのようにあります。「わたしを見る人は皆、わたしを嘲笑い 唇を突き出し、頭を振る。『主に頼んで救ってもらうがよい。主が愛しておられるなら 助けてくださるだろう』」。22編は主イエスの十字架を指し示している詩編ですが、この8、9節も、本日の箇所で語られている主イエスの十字架に立ち会った人たちの姿を指し示しています。いえそれだけでなく、主イエスの十字架を無視し、軽んじてしまう私たちの姿をも指し示しているのです。しかし主イエスはその私たちのために、「父よ、彼らをお赦しください」と祈ってくださいました。私たちが悔い改めたから、そう祈ってくださったのではありません。悔い改める気なんて全然ないときに、むしろ主イエスの十字架を拒み、嘲笑い、侮辱しているときに、「父よ、彼らをお赦しください」と祈ってくださったのです。私たちが悔い改めるより先に、信じるより先に、主イエスが私たちの赦しのために祈ってくださり、そして十字架で死んでくださったのです。私たちの悔い改めや信仰は、この主イエスの執り成しの祈りによって支えられています。この主イエスの祈りなしに、私たちは悔い改めることも信じることもできません。私たちの信仰生活のすべてが、この祈りによって支えられているのです。私たちは救われてもなお、日々罪を犯し続けています。受難節であっても主イエスの十字架を見失うことがあり、主イエスが救い主であることを疑うこともあります。しかしそのような私たちも、「父よ、彼らをお赦しください」という主イエスの祈りの中に入れられています。この祈りの中に生かされています。だから私たちは主イエスの十字架を見失っても、再び見つめることができるのです。「父よ、彼らをお赦しください」。この主イエスの祈りの中で、この祈りに支えられて、私たちは主イエスの十字架を見つめて歩んでいきたいのです。この受難節、繰り返し「父よ、彼らをお赦しください」という主イエスの祈りに聞きつつ、私たちのために主イエスが苦しみを受けて、十字架で死なれたことを覚えて歩んでいくのです。