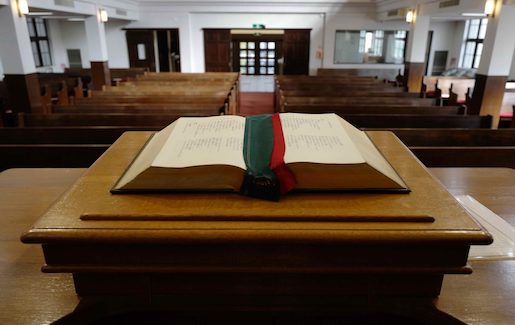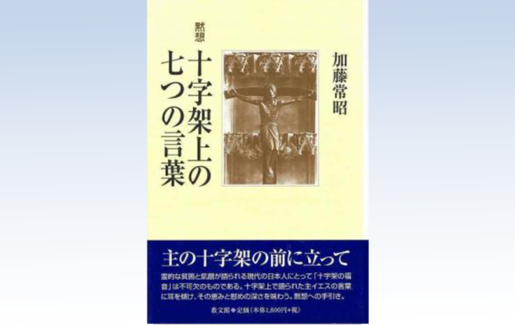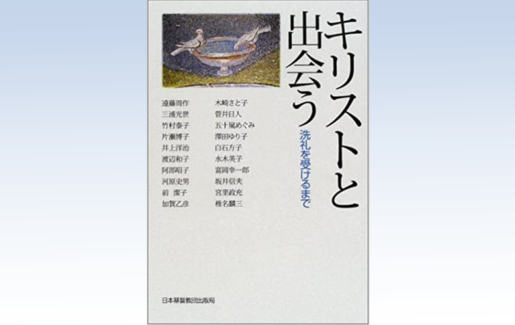【2024年12月奨励】「見よ、おとめが身ごもって、男の子を産み その名をインマヌエルと呼ぶ。」奨励 牧師 藤掛順一
(イザヤ書第7章14節)
12月にふさわしい聖句
12月の聖句を「見よ、おとめが身ごもって、男の子を産み その名をインマヌエルと呼ぶ。」(14節)としました。マタイによる福音書第1章22節以下において、マリアが身ごもって救い主イエス・キリストを産むことを天使がヨセフに告げたところにこの言葉が引用されています。イザヤ書のこの言葉は、主イエスの誕生によって、インマヌエル(神は我々と共におられる)の恵みが実現するという預言として、そして「主は聖霊によりてやどり、処女(をとめ)マリアより生れ」(使徒信条)という「処女降誕」の奇跡の預言として読まれてきたのです。主イエスのご降誕を喜び祝うクリスマスを迎える12月の聖句としてふさわしい箇所だと言えます。しかし本日は、この箇所を含むイザヤ書第7章が何を語っているのか、その中でこの言葉がどういう意味を持っているのか、を見ていきたいと思います。クリスマスという文脈をはずしてこの箇所を読んでみよう、ということです。
シリア・エフライム戦争
7章1節に「ユダの王ウジヤの孫であり、ヨタムの子であるアハズの治世のことである」とあります。イザヤが預言者としての召命を受けて活動を開始したのは、6章1節にあるように「ウジヤ王が死んだ年」ですが、その活動がはっきり記されているのはこのアハズ王の治世からです。その治世の中で起った重大な出来事がここに記されています。「アラムの王レツィンとレマルヤの子、イスラエルの王ペカが、エルサレムを攻めるために上って来た」のです。これは、「シリア・エフライム戦争」と呼ばれているもので、紀元前732年のことです。アラムとは、ダマスコを首都とするシリアのことで、これは異邦人の国です。エフライムとは、ソロモン王の死後イスラエル王国が南北に分裂した、北王国イスラエルを指しています。この時その王だったのが、「レマルヤの子ペカ」だったのです。南王国ユダにおいては、ダビデの子孫が王位を継承する「ダビデ王朝」がずっと続いていました。アハズもダビデの子孫です。しかし北王国イスラエルでは、次々と王朝が変わっていました。ペカも、前の王であるペカフヤの侍従だったのが、謀反を起こしてペカフヤを殺して王となったのです(列王記下第15章23節以下)。そしてこのペカは北王国イスラエルの最後から二番目の王となりました。彼も謀反によって殺され、彼に代って王になったホシェアの時に、イスラエルはアッシリア帝国によって滅ぼされるのです。つまりこのイザヤ書7章に語られているのは、北王国の末期の出来事です。既にアッシリア帝国の圧迫を受けていたアラム(シリア)と北王国イスラエル(エフライム)が、反アッシリア同盟に南王国ユダをも巻き込もうとしたのです。そのために、この両国がユダに攻めてきました。同盟に加えるために攻め込むというのはよく分からない感じがしますが、6節に「ユダに攻め上って脅かし、我々に従わせ、タベアルの子をそこに王として即位させよう」と彼らが言っていることが語られています。つまりアラムの王レツィンとイスラエルの王ペカは、ユダ王国を脅して、自分たちの思い通りになる新しい王を即位させることによって、ユダ王国をもアッシリアに対抗する同盟に加わらせようとしたのです。
森の木々が風に揺れ動くように動揺した
そのようにして、アラムとイスラエルの連合軍がエルサレムに攻めて来ました。1節の終わりにあるように、実際に攻撃を仕掛けることはできなかったようですが、2節にこうあります。「しかし、アラムがエフライムと同盟したという知らせは、ダビデの家に伝えられ、王の心も民の心も、森の木々が風に揺れ動くように動揺した」。アラム(シリア)は異邦人の国ですが、北王国イスラエルは、分裂したとは言え、南王国ユダとは兄弟の国のはずです。その兄弟国が、異邦人の国アラムと同盟してユダを攻めて来たことで、アハズ王の心も、ユダの人々の心も、「森の木々が風に揺れ動くように動揺」したのです。
落ち着いて、静かにしていなさい
この状況の中で、主なる神がイザヤに、アハズ王に会いに行って主の言葉を告げるようにお命じになります。イザヤが主の命令によって語ったのは、4節以下の「落ち着いて、静かにしていなさい。恐れることはない。アラムを率いるレツィンとレマルヤの子が激しても、この二つの燃え残ってくすぶる切り株のゆえに心を弱くしてはならない。…」ということでした。さらに7節には、ユダに傀儡政権を打ち立てようという彼らの計画は実現しない、と語られています。そして最後の9節は「信じなければ、あなたがたは確かにされない」と結ばれています。イザヤはアハズ王に、主なる神が必ず守って下さるのだから、主に信頼して、周囲の国々の動向によって慌てふためくことなく、落ち着いて、静かにしていなさい。」と語ったのです。
イザヤを通して語られたこの主のみ言葉を、私たちもしっかりと聞きたいと思います。この世界の目に見える現実においては、私たちも、この時のユダ王国と同じように、国々の様々な動向によって翻弄されています。以前の東西冷戦の時代には、二つの大きな陣営が対峙していて、今にして思えばある意味安定がありました。冷戦が終わって世界が平和になるかと思ったら、むしろ様々な勢力の対立が生じてきました。その中で国々はいろいろな同盟関係を結んで身を守ろうとしており、世界はとても複雑になっています。そして同盟を結ぶことは敵対関係に巻き込まれることでもあり、それによってかえって国の安全が脅かされることも起っています。NATOに加盟しようとしたためにロシアに攻撃されているウクライナがいい例です。アラム、イスラエル、ユダという小さな国が、超大国アッシリアの脅威に立ち向かおうとして右往左往しているのと同じようなことが、今も起っているのです。そういうこの世の現実の中で、私たちの心も、「森の木々が風に揺れ動くように動揺」しています。しかしそこに、聖書を通して主の言葉が響いています。「落ち着いて、静かにしていなさい。恐れることはない」。
主なる神に信頼すること
私たちはこのみ言葉を、「周囲の国からどんな誘いや圧力を受けても、同盟を結ぶことなく、中立を守るべきだ」という外交政策への指示として読むべきではないでしょう。紀元前のイザヤの言葉をそのまま現代の政策にすることが求められているのではありません。私たちがこのみ言葉から聞くべきことは、この世界には様々な勢力が起ってきて私たちを脅かすが、最終的に支配しておられるのは主なる神なのだ、ということです。そのことを信じるなら、この世の現実によって様々に動揺させられても、根本的には「落ち着いて、静かにしている」ことができるのです。そして「恐れることなく」歩むことができるのです。イザヤがアハズ王に語ったのも、基本的にはそういうことでした。つまりイザヤは、外交政策の提言をしたと言うよりも、主なる神に信頼することを求めたのです。「信じなければ、あなたがたは確かにされない」という言葉はそのことを語っているのです。
しるしを求めないアハズ
その上で主はさらにイザヤを通してアハズに、「主なるあなたの神に、しるしを求めよ」と語りかけました(11節)。この「しるし」は、主なる神が守ってくださる、ということのしるし、言い換えれば証拠です。アラムとエフライムが何を計画しても、それは実現しない、主なる神のみ心こそが実現するのだ、ということの目に見えるしるしを私が与えるから、それを求めよ、と主はおっしゃったのです。アハズはそれに対してこう答えました。「わたしは求めない。主を試すようなことはしない」(12節)。これは一見すると、信仰的に正しい言葉のように感じられます。しるし(証拠)を求めることをしないというのは、「見ないのに信じる人は、幸いである」(ヨハネ20・29)と同じことではないかと思うのです。しかしこのアハズの答えに対してイザヤはこう言っています。「ダビデの家よ聞け。あなたたちは人間にもどかしい思いをさせるだけでは足りず/わたしの神にももどかしい思いをさせるのか」。ここは聖書協会共同訳では「人間を煩わすだけでは足りず、私の神をも煩わすのか」となっています。主なる神はアハズのこの答えにもどかしい思いをし、煩わされているのです。つまり主はこの言葉を喜んでおられないのです。それはなぜかと言うと、ここでは主なる神ご自身が「しるしを求めよ」と言っておられるからです。主なる神は、危機の中で動揺しているアハズに、「落ち着いて、静かにしていなさい。恐れることはない」と語り、ご自身を信じることを求めておられます。そして彼が主を信頼して生きることができるように、主の守りのしるしを与えようとしておられるのです。しるしを与えることによってアハズとユダの人々を支えようとしておられるのです。だからこの場合には、主が与えてくださろうとしているしるしを求めることこそが、み心にかなうことなのです。それを、「主を試すようなことはしない」と言って拒むのは、主の恵みを求めようとしないということであり、それは、主の恵みを信じていない、という不信仰なのです。危機の中で動揺しながらも主の恵みを信じて求めようとしないアハズに、主は「もどかしい思い」を抱き、「煩わされて」おられるのです。
主自らがしるしを与える
このことに続いて14節が語られています。「それゆえ、わたしの主が御自らあなたたちにしるしを与えられる。見よ、おとめが身ごもって、男の子を産み/その名をインマヌエルと呼ぶ」。つまり14節のみ言葉は、しるしを求めようとしないアハズ王に「もどかしい思い」を抱いておられる主が語られたものです。アハズが求めないなら、主ご自身が自らしるしを与える。そのしるしが、「おとめが身ごもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ」ことだったのです。この「おとめ」は本来は「若い女性」という意味の言葉です。ですから元々はここにいわゆる「処女降誕」という奇跡の意味はありません。そして15節以下に語られているのは、生まれて来るその子が「災いを退け、幸いを選ぶことを知るようになる」までに(ここは聖書協会共同訳では「悪を退け善を選ぶことを知るようになるまで」となっており、その子が分別のつく年になるまでに、という意味だと考えられます)、「あなたの恐れる二人の王の領土は必ず捨てられる」、つまり、今ユダを脅かしているアラム(シリア)とエフライム(北王国イスラエル)が滅亡するということです。それはアッシリアによってです。それによってユダ王国はこの二人の王の脅威から救われるのです。しかしそれと共に17節には、「主は、あなたとあなたの民と父祖の家の上に、エフライムがユダから分かれて以来、臨んだことのないような日々を臨ませる。アッシリアの王がそれだ」と語られています。つまりアラムとエフライムを滅ぼしたアッシリアの脅威を、今度はユダ王国が直接受けることになるのです。小さな危機が去って、もっと大きな危機が来るということです。ですからこの預言は、しるしを求めようとしないアハズ王に対して、主自らが救いのしるしを与えて下さる、という恵みを語っていると同時に、主なる神の恵みを求めようとせず、それを信じないアハズに対する神の怒りと裁きを語ってもいるのです。しかしその怒りと裁きの中で、「インマヌエル(神は我々と共におられる)」という恵みが実現することもまた語られているのです。
主イエス・キリストによる救いを指し示している
これが、14節の預言のイザヤ書7章における意味です。ここには、危機の中で動揺しながらも、主なる神の恵みを信じようとせず、求めようとしない人間の罪が語られています。それが私たちの現実だと言えるでしょう。私たちは、苦しみ悲しみの中で必ずしも神の救いを求めるわけではありません。むしろ苦しみの中で神の恵みを疑い、それを信じて求めようとしないことが多いのです。そのような私たちに、神はもどかしい思いを抱いておられます。そして、それならこちらから恵みのしるしを与えるとおっしゃるのです。そのようにして主はご自分の独り子イエス・キリストをこの世に遣わして下さったのです。だから14節は確かに救い主イエス・キリストの誕生の預言だと言えるのです。その主イエスによって実現する救いは、ただ苦しみや悲しみを取り除いて下さる、というだけのものではありません。そこには、神の恵みを無にしている人間の罪に対する神の怒りと裁きも伴うのです。それゆえに北王国イスラエルはアッシリアによって、南王国ユダはその後バビロニアによって、滅ぼされたのです。しかしその神による裁きの中で、「インマヌエル」ということが実現する、とイザヤ書7章は告げています。私たちはそこに、主イエス・キリストによる救いの預言を読み取ることができます。神の救いの恵みを求めようとしていない私たちに、神は、「それならこちらから救いを実現する」とおっしゃって、主イエスを送って下さいました。主イエスにおいて、私たちの罪に対する神の怒りと裁きは貫かれています。しかしその怒りと裁きを、主イエスはご自分の上に引き受けて下さって、十字架にかかって死んで下さったのです。この主イエスによって、「インマヌエル(神は我々と共におられる)」の恵みが私たちに与えられたのです。このように、イザヤ書第7章1〜17節は、14節のみでなくその全体において、神が主イエス・キリストを遣わして下さったことによって私たちに与えられた救いを指し示しているのです。