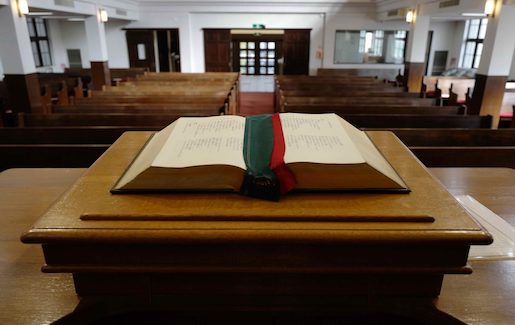説教「主イエスの十字架」 副牧師 川嶋章弘
旧約聖書 詩編第22編1-22節
新約聖書 マルコによる福音書第15章21-32節
十字架につけられる場面
「棕櫚の主日」を迎えました。本日から受難週が始まります。主イエスの地上のご生涯の最後の一週間を覚えるときです。主イエスはこの週の金曜日に十字架につけられて死なれました。私たちはこの棕櫚の主日に、マルコによる福音書が語る、主イエスの十字架の場面に、まさに主イエスが十字架につけられる、その場面に目を向けていきたいと思います。
たった二語をもって
24節の前半に「それから、兵士たちはイエスを十字架につけて」とあります。本日の箇所全体が、主イエスが十字架につけられた場面ではありますが、主イエスを十字架につけたことそれ自体について記しているのは、この一言だけです。原文のギリシア語ではたった二語、二つの単語をもって記されています。あまりにも簡潔に語られている、と思います。少々変な言い方かもしれませんが、拍子抜けするような、物足りないような記述です。主イエスの十字架は、言うまでもなくこの福音書のクライマックスです。小説であればクライマックスを描くのに何ページも使うでしょうし、映画であれば何カットも使うでしょう。ところがマルコ福音書は「兵士たちはイエスを十字架につけて」としか語っていないのです。もっと劇的に、たとえば、主イエスが釘を打たれ、血を流されつつ、激しく苦しまれて十字架につけられた、と語っても良いはずです。しかしマルコ福音書は、どのように主イエスが十字架につけられたのか、あるいは、そのとき主イエスがどれほどの痛みや苦しみを覚えられたのかをまったく語っていません。十字架刑がいかに残酷な刑であるかを描こうとはしないのです。
人間の罪の残酷さ
しかしそれは、主イエスが十字架につけられた場面の残酷さをやわらげるためではありません。「兵士たちは血まみれで苦しんでいる主イエスを十字架につけた」と語ると、あまりに残酷なので、それを避けたということではないのです。いやむしろ、十字架刑そのものの残酷さよりも、より残酷なものがここで語られています。十字架刑による肉体の痛みや苦しみの残酷さよりも、もっと残酷なものが見つめられているのです。それは、私たち人間の罪の残酷さです。私たちは十字架刑の残酷さは多少なりとも分かります。調べれば、当時のローマ帝国の十字架刑がどのようなものであるかもある程度は分かります。それを読んで、こんなに残酷な方法で主イエスは処刑されたのか、と思わずにはいられません。あるいは私たちは自分のであれ、ほかの人のであれ、肉体の痛みや苦しみには割と敏感です。ちょっとした痛みでも大騒ぎしてしまうことがありますし、ほかの人の肉体的な痛みを、自分の痛みのように感じることもあります。しかし私たちは人間の罪についてはまことに鈍感です。とりわけ自分の罪について、その残酷さについては極めて鈍感なのです。マルコ福音書は、たった二語をもってして、主イエスが十字架につけられたことを語りました。しかしその後に、その主イエスの十字架に立ち会った人たちの姿を描きます。そのことを通して、十字架刑の残酷さや、それによる肉体的な痛みや苦しみの残酷さにはるかにまさる、人間の罪の残酷さを描いているのです。
主イエスの服を分け合う
24節の後半に、主イエスを十字架につけた兵士たちの姿が、「その服を分け合った、だれが何を取るかをくじ引きで決めてから」と語られています。兵士たちは主イエスからはぎ取った服を分け合いました。それは主イエスのときだけ特別にそうしたということではなく、当時、死刑を執行した人は、処刑された人のものを自分のものにするのが習慣であったようです。主イエスの十字架の足もとで、兵士たちは十字架上の主イエスを見上げようともせず、物欲に駆られて、主イエスの服を分け合っていました。しかも「だれが何を取るかをくじ引きで決めてから」と言われているように、彼らはそれをゲーム感覚で行っていたのです。私たちは、このように物欲に駆られ、ゲーム感覚で主イエスの服を分け合う、醜い兵士たちの姿から目を背けたくなります。主イエスが十字架上で血を流され、苦しまれているのに、その足もとで、なんでこんなひどいことができるのだ、と憤りすら覚えるのです。
十字架のもとで欲に駆られて
しかしこの箇所を繰り返し読む中で、私たちは気づかされます。この兵士たちの姿は、ほかならぬ私たちの姿ではないか、と気づかされるのです。主イエスが十字架で苦しみを受けられ、死なれたことによって、私たちは救われました。その救いの恵みのもとで、私たちは生かされています。私たちも主イエスの十字架のもとで生かされているのです。それは、決して主イエスが十字架にかけられたまま、という意味ではありません。しかし主イエスの十字架の死によって実現した救いの恵みのもとにいる、その意味で、私たちも主イエスの十字架のもとで生かされているのです。それにもかかわらず私たちは、主イエスの十字架のもとで、十字架上の主イエスを見上げようとしません。私たちのために十字架に架かり、苦しまれ、死んでくださった主イエスを想い起こすよりも、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようか、何を買おうか、と自分の欲望に駆られています。物とは限りません。名誉や達成感を求めることに駆られていることもあります。このように言われると、それなら禁欲して生きるしかないではないか、と思われるかもしれません。食事や服に興味を持たず、名誉や達成感を求めずに生きれば、そのような禁欲生活を送れば良い、ということなのでしょうか。そうではないと思います。本当の問題は、禁欲するかしないかではありません。そうではなく、何を食べるのか何を着るのかに心を向けたのと同じぐらい、いやそれ以上に主イエスの十字架に心を向けたか、ということです。名誉や達成感を求める以上に、主イエスの十字架を求めたか、ということです。たとえ禁欲をしても、主イエスの十字架を見上げないなら、それは一種の自己満足に過ぎないのです。昨日までの一週間を振り返っても、私たちはどれだけ主イエスの十字架を見上げることができたのでしょうか。この一週間も、私たちは主イエスの十字架のもとで、十字架上の主イエスを見上げようとせず、自分の欲に駆られて生きていたのです。そうであれば目を背けたくなるような醜いあの兵士たちの姿は、ほかならぬ私たち自身の姿に違いありません。あの兵士たちの残酷な振る舞いは、私たち自身の、私たち罪人の残酷さにほかならないのです。
主イエスをののしり、侮辱する
兵士たちのほかにも、主イエスの十字架に立ち会った人たちがいました。29節には主イエスが十字架につけられたとき、そこを通りかかった人々についてこのように言われています。「通りかかった人々は、頭を振りながらイエスをののしって言った。『おやおや、神殿を打ち倒し、三日で建てる者、十字架から降りて自分を救ってみろ』」。また31、32節では祭司長たちや律法学者たちについてこのように言われています。「同じように、祭司長たちも律法学者たちと一緒になって、代わる代わるイエスを侮辱して言った。『他人は救ったのに、自分は救えない。メシア、イスラエルの王、今すぐ十字架から降りるがいい。それを見たら、信じてやろう』」。さらに32節の後半では「一緒に十字架につけられた者たちも、イエスをののしった」と言われています。「一緒に十字架につけられた者たち」とは、27節にあるように、主イエスを中央にして、その右と左で十字架につけられた二人の強盗のことです。このように通りかかった人たちも、祭司長たちや律法学者たちも、二人の強盗も、十字架につけられた主イエスをののしり、侮辱しました。そこで繰り返し言われているのは、「十字架から降りて自分を救ってみろ」ということです。本当にメシアなら、救い主なら、イスラエルの王なら、今すぐ十字架から降りて、自分を救ってみろ、それを見たら、信じてやろう、と言われているのです。
自分の期待に応えてくれる神を求める
要するにこの人たちは、「私たちの言う通りにしてくれたら、信じてやろう」と言っています。「私たちの言う通りに、今すぐ十字架から降りて、自分を救ったら、信じてやろう」と言っているのです。それは自分の期待に応えてくれるのでなければ、自分の願いを叶えてくれるのでなければ、イエスを救い主として認めない、信じない、ということです。イエスが救い主であるかどうかは、自分たちが判断できる、判断してやる、と思っているのです。まことに自分勝手で、傲慢な姿と言わなければなりません。しかし私たちも、しばしば同じようなことをしているのではないでしょうか。私たちは神様を信じて生きていると思っています。主イエスに向かって、「十字架から降りて自分を救ってみろ」と言うはずがないと思っています。しかし私たちも自分の期待に応えてくれるなら、自分の願いを叶えてくれるなら神様を信じるけれど、そうでなければ神様を信じない、とどこかで思っていないでしょうか。だから神様が自分の願いを叶えてくれないなら、もう神様を信じるのはやめよう、願いを叶えてくれない神様なんて信じても意味がない、と思ったりするのです。
また、この世界には悲惨な現実が溢れています。戦争があり、災害があり、富の格差があります。そのような現実に直面するとき、私たちはなぜ神様は何もしてくださらないのか、なぜこのような悲惨な現実をお許しになるのか、と思います。この問いそのものは真剣かつ深刻な問いであり、私たちはこの問いを問うていく必要があります。しかしこの問いの背後にも、どこかに私たちが神様をコントロールしたいという思いが、私たちが神様を判断しようとする思いがあるのではないでしょうか。このような悲惨な現実をお許しになる神様は認めない、という思いがあるのです。しかしそれは、結局、神様を信じているのではなくて、自分が神になろうとしているのです。私たちこそ、自分の期待に応え、願いを叶えてくれる神様を求め、主イエスに向かって、「十字架から降りて自分を救ってみろ、そうしたら信じてやる」と言っている者なのです。
詩編22編の引用
このように主イエスが十字架につけられたとき、そこには私たち人間の罪が溢れかえっていました。十字架のもとで、自分の欲望に駆られる私たち罪人の醜い姿が、自分が神になろうとする私たち罪人の残酷な振る舞いが示されています。十字架刑の残酷さや、それによる主イエスの肉体的な痛みや苦しみの残酷さにはるかにまさる、私たち罪人の残酷さがはっきりと示されているのです。しかしこの箇所で示されているのはそれだけでしょうか。マルコ福音書は私たちに、私たちの罪の悲惨さを突きつけているだけなのでしょうか。もしそうであれば、私たちは打ちのめされるしかありません。自分の欲望に駆られ、自分が神になろうとしてしまう自分自身に対して幻滅するしかないのです。けれどもマルコ福音書はこの箇所で、私たち人間の罪の悲惨さを突きつけるだけでなく、神の救いのご計画が進んでいることを見つめています。一見、少しもそのようなことは語られていないように思えます。一体、どのようにしてそのことを見つめているのでしょうか。それは、共に読まれた詩編22編を引用することによってです。本日の箇所のすぐ後で、主イエスは十字架上で「わが神、わが神、なぜわたしをお見捨てになったのですか」と叫ばれました。この叫びが、22編2節の言葉であることはよく知られています。しかしそれだけでなく、本日の箇所でも22編からの引用があります。24節で兵士たちが、「その服を分け合った、だれが何を取るかをくじ引きで決めてから」と言われていましたが、これは22編19節の「わたしの着物を分け 衣を取ろうとしてくじを引く」からの引用です。少し前の17節からお読みするとこのように言われています。「犬どもがわたしを取り囲み さいなむ者が群がってわたしを囲み 獅子のようにわたしの手足を砕く。骨が数えられる程になったわたしのからだを 彼らはさらしものにして眺め わたしの着物を分け 衣を取ろうとしてくじを引く」。まさに兵士たちは、主イエスの手足に釘を打って十字架に架け、その手足を砕き、その服をはぎ取って、骨が見えるほどやせ衰えた主イエスの体をさらしものにして眺め、その服をくじを引いて分け合ったのです。また29節で「通りかかった人々は、頭を振りながらイエスをののしって言った」と、「頭を振りながら」と言われていましたが、これは22編8節の「わたしを見る人は皆、わたしを嘲笑い 唇を突き出し、頭を振る」から来ています。そして続く9節には「主に頼んで救ってもらうがよい。主が愛しておられるなら 助けてくださるだろう」とも言われています。この言葉は、主イエスの十字架に立ち会った人々の「十字架から降りて自分を救ってみろ」と重なるのです。
なお神のご計画は前進している
確かにこの場面は私たち人間の罪の残酷さに満ちています。しかしそれは、思いがけずに起こったことでも、神様の御手の外で起こったことでもありません。すでに詩編22編が、聖書が指し示していたことなのです。神のみ心がまったく見えないような、神のご計画が頓挫したようにすら思えるこの場面にあっても、なお22編が指し示している神のご計画は前進しているのです。22編はメシア(救い主)のことを語っていると受けとめられていました。そこに示されている神のみ心、神のご計画が、メシア(救い主)が苦しみを受け、死なれることです。そのことを通して私たち罪人を救うことです。この場面でこの神のご計画が前進しているのです。23節にあるように、主イエスは「没薬を混ぜたぶどう酒」をお受けになりませんでした。「没薬を混ぜたぶどう酒」は痛みをやわらげるためのものです。それをお受けにならなかったということは、主イエスがこの神の御心を受け入れられた、ということです。ご自分が十字架で死なれる苦しみを割り引くことなく、余すところなく引き受けられた、ということなのです。もちろん神の救いのご計画が実現するのは、主イエスの十字架の死と復活においてです。しかしその十字架の死に至る本日の箇所でも、私たち人間の罪の残酷さしか見えないように思えるこの箇所でも、その救いの計画は確かに前進しているのです。
罪を赦そうとする神の愛
私たちはこの場面で、自分自身の罪を突きつけられます。私たち自身の罪がどれほど醜く、残酷で、悲惨なのかを突きつけられます。私たちはその突きつけられた自分自身の罪を真剣に受けとめなければなりません。しかしそれでも私たちは、なお自分の罪に鈍感であり続けます。本当には自分の罪がなかなか分からないのです。なぜなら私たちは人間の罪の残酷さを見つめることによって、自分自身の罪が本当に分かるようになるわけではないからです。私たちがこの場面で本当に目を向けるべきなのは、人間の罪ではなくて、その人間の罪を赦そうとする神の愛です。表面的には人間の罪が猛威をふるう中で、しかしその背後でその罪の猛威に決して屈することのない神の愛が圧倒していることにこそ目を向けるのです。私たちは人間の罪に溢れているこの場面で、なお神のみ心が貫かれていることに、神の救いのみ業が行われていることに触れます。私たち罪人を救うために独り子イエス・キリストを十字架に架ける神の愛と、その救いのみ業に触れるのです。
神の愛に触れたシモン
実はこの箇所には、この神の愛に、神の救いのみ業に触れた人物が登場します。それが21節の「アレクサンドロとルフォスとの父でシモンというキレネ人」です。このように記したということは、マルコ福音書が生まれ、読まれた教会で、アレクサンドロとルフォスがよく知られていたということです。そしてこの二人が、父シモンのことを証ししたのではないでしょうか。父シモンが、主イエスの代わりにその十字架を背負ったこと、その後、教会が誕生し、そこで主イエスの十字架と復活による救いを告げる説教を聞いて、シモンが洗礼を受け、教会のメンバーとなり、キリスト者となったこと、そのシモンの信仰を受け継いで、自分たちもキリスト者となったことを証ししたのです。
キレネ人シモンは、自分から進んで主イエスの十字架を担ったわけではありませんでした。彼はたまたま主イエスが十字架を背負ってゴルゴタに歩んで行くところに通りかかっただけです。衰弱して十字架を背負えない主イエスを見て、助けようと思ったのでもありません。21節には「兵士たちはイエスの十字架を無理に担がせた」とあります。シモンは無理矢理主イエスの十字架を担ぐことになりました。準備なんか何もしていなかったのに、主イエスの十字架を背負って歩くことになったのです。嫌々だったに違いありません。逆らえば兵士たちに何をされるか分からないという恐れもあったに違いありません。しかしそのように強いられて主イエスの十字架を背負って歩く中で、シモンは人間の罪の猛威に屈することのない神の愛に、その救いのみ業に触れたのです。自分が背負った十字架の重みが、人間の罪の重みであり、その罪を赦す神の愛の重みであることを経験したのです。シモンがそのことにはっきりと気づかされるのは、教会が誕生した後に、そこで十字架と復活による救いを告げる説教を聞くことによってであったに違いありません。しかしそれに先んじて、主イエスの十字架を背負って歩む中で、主イエスが人間の罪を赦すために、その罪をすべて背負って十字架に架けられたことに、そこに示されている神の愛に触れたのです。主イエスはかつて弟子たちにこのように言われました。「わたしの後に従いたい者は、自分を捨て、自分の十字架を背負って、わたしに従いなさい」(8章34節)。主イエスに従って生きるとは、主イエスを信じて生きるとは、このシモンのように、主イエスの十字架を背負って歩むことなのです。
十字架を背負って歩む中で
私たちの信仰生活は、主イエスの十字架を背負って歩んでいく生活です。自分から進んで背負うというより、シモンと同じように、私たちも強いられて十字架を背負います。まだ準備ができていないと、できれば背負いたくないと思いつつ、あるいは背負えるわけがないと恐れつつも、私たちは十字架を背負って歩んでいきます。しかしその中でこそ、私たちは神の愛に触れるのです。主イエスが受けられた苦しみの一端を担うことを通して、主イエスが味わった苦しみを僅かばかり味わうことを通して、私たちのためにそれほどの苦しみを受けられた主イエスの愛に、神の愛に触れていきます。私たちの罪の重みと、その罪を赦す神の愛の重みを味わっていくのです。
十字架に立ち会った人々は「今すぐ十字架から降りるがいい。それを見たら、信じてやろう」と主イエスをののしりました。しかしこの人たちは、仮に主イエスが十字架から降りたのを見ても、信じることはなかったはずです。私たちは見て、信じるのではありません。見ないで、信じるのです。そのことを後に、ペトロはこのように言いました。「あなたがたは、キリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせないすばらしい喜びに満ちあふれています」(ペトロの手紙一1:8)。私たちは主イエスの十字架を背負って歩む中で、主イエスの苦しみの一端を担う中で、神様の私たちへの計り知れない愛を知らされ、見たことがない主イエス・キリストをますます愛し、信じる者とされていくのです。主イエスの十字架を背負って生きる私たちの歩みにこそ、言葉では言い尽くせないすばらしい喜びが満ち溢れるのです。この歩みを私たちに与えるために、主イエスは十字架の死の苦しみを余すところなく引き受けてくださり、死んでくださったのです。この歩みこそ、主イエスの十字架を見つめる歩みです。この歩みの中でこそ私たちは、自分が今、食事や服装を楽しみつつ生きられるのも、名誉や達成感を求めつつ生きられるのも、主イエスが自分のために十字架で苦しまれ、死んでくださったからだ、その救いの恵みのもとに生かされているからだと気づかされて、救いの恵みに心から感謝して生きていくのです。